相続法改正 新しい相続実務の徹底解説 概説と事例QA

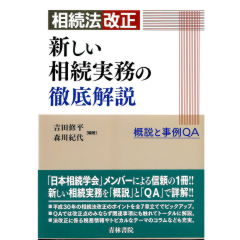
販売価格: 4,400円 税込
「日本相続学会」メンバーによる信頼の1冊!! 新しい相続実務を
「概説」と「QA」で詳解!!
■平成30年の相続法改正のポイントを全7章立てでピックアップ。
■QAでは改正点のみならず関連事項にも触れてトータルに解説。
■法改正に係る税務情報やトピカルなテーマのコラムなども充実。
第1章 相続法改正の経緯
【概 説】
Ⅰ 相続法改正の経緯
? 従来の主要な改正 ? 今回の改正の経緯 ? 中間試案の内容
? 追加試案の内容
Ⅱ 今回の相続法改正の概要
? 配偶者の居住を保護するための方策 ? 遺産分割等に関する見直し ? 遺言制度に関する見直し ? 遺留分制度に関する見直し ? 相続の効力等に関する見直し ? 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 ? 施行期日
Ⅲ ま と め
第2章 配偶者の居住権
第1節 配偶者居住権
【概 説】
Ⅰ 配偶者居住権とは
Ⅱ 改正前の問題点
Ⅲ 配偶者居住権の成立要件
Ⅳ 配偶者居住権の消滅
Ⅴ 審判による配偶者居住権の取得
Ⅵ 配偶者居住権の存続期間
Ⅶ 配偶者居住権の登記等
? 登記請求権 ? 第三者対抗要件 ? 妨害の停止の請求等
Ⅷ 配偶者による使用及び収益
? 用法遵守義務 ? 譲渡禁止 ? 改築・増築,第三者の使用・収益
Ⅸ 居住建物の修繕等
Ⅹ 居住建物の費用の負担
? 居住建物の返還等
? 居住建物の返還 ? 損害賠償及び費用償還請求
? 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
XIII 配偶者居住権の法的性質
〔1〕 配偶者居住権の内容及び成立要件
〔2〕 配偶者居住権の効力
[コラム1]配偶者居住権の評価について
〔3〕 配偶者居住権の消滅
第2節 配偶者短期居住権
【概 説】
Ⅰ 配偶者短期居住権とは
? 配偶者短期居住権 ? 改正前の問題点
Ⅱ 配偶者短期居住権の内容
? 法的性質 ? 成立要件等 ? 存続期間 ? 権利の内容
? 居住建物取得者による消滅申入権 ? 相続財産との関係
Ⅲ 配偶者短期居住権の効力
? 使用借権と同様の規律 ? 用法遵守義務及び善管注意義務
? 無断で第三者に使用させることの禁止 ? 居住建物の修繕等
? 居住建物の費用の負担
Ⅳ 配偶者短期居住権の消滅
? 消滅原因 ? 消滅の効果 ? 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第3章 遺産分割等に関する見直し
第1節 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
【概 説】
Ⅰ はじめに
? 概 要 ? 改正の趣旨
Ⅱ 従前の規定
? 特別受益における持戻し計算 ? 従前の配偶者救済方法
Ⅲ 持戻免除の意思表示の推定規定の概要
? 条 文 ? 持戻免除の意思表示の推定規定の概要
? 遺留分との関係 ? 実務への影響 ? 配偶者居住権への準用
Ⅳ 施行時期及び適用範囲
第2節 預貯金の払戻し
【概 説】
Ⅰ 家庭裁判所の手続を経ない預貯金の引出し
? 制度創設の経緯 ? 払戻しできる額 ? 払戻しの効果
? 払戻請求権の譲渡,差押え,相殺 ? 共同相続人の債権者による預貯金
債権の差押え ? 経過規定
Ⅱ 預貯金債権の仮分割の仮処分
? 制度創設の経緯 ? 仮分割の要件 ? 仮分割の額
? 本分割との関係 ? 債務者(金融機関)との関係
第3節 遺産の一部分割
【概 説】
Ⅰ これまでの一部分割の取扱い
? 一部分割の必要性 ? 改正前の民法での取扱い
Ⅱ 一部分割の明文化
Ⅲ 一部分割の要件
? 遺言で禁止されていないこと(改正民907条1項)
? 協議・調停の場合
? 審判の場合
Ⅳ 一部分割の調停・審判の申立てをする場合
? 遺産の範囲の特定 ? 審判が却下される場合 ? 申立てが競合した場合
Ⅴ 家事事件手続法73条2項との関係
第4節 遺産分割前に財産が処分された場合の遺産の範囲
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 従前の取扱い
Ⅲ 改正民法による新規定
? 条 文 ? 新規定の概要
Ⅳ 実務への影響
第4 章 遺言制度に関する見直し
第1節 自筆証書遺言の方式
【概 説】
Ⅰ 遺言制度について
Ⅱ 自筆証書遺言の方式
? 自書を要件とする理由 ? 自書の負担と必要性 ? 改正法による自書要件の緩和 ? 要件緩和の効果 ? 改正前の判例の参酌
Ⅲ 目録の作成方法
? 改正法の規定 ? 財産目録の対象となる財産 ? 財産目録に記載すべき財産 ? 財産目録を添付する方法 ? 財産目録の作成方法 ? 財産目録への署名押印 ? 財産目録中の加除その他の変更
Ⅳ 遺言書の作成例
第2節 遺贈義務者の引渡義務等
【概 説】
Ⅰ 遺贈義務者の引渡義務についての改正
? 遺贈の目的となる物又は権利が相続財産に属するものである場合
? 遺贈の目的となる物又は権利が遺言者の死亡時において相続財産に属しない場合
Ⅱ 債権法改正との関係
? 遺贈の目的となる物又は権利が相続財産に属するものである場合
? 遺贈の目的となる物又は権利が遺言者の死亡時において相続財産に属しない場合
第3節 遺言執行者の権限の明確化
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 遺言執行者の任務の開始
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅲ 遺言執行者の権利義務
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅳ 遺言の執行の妨害行為の禁止
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅴ 特定財産に関する遺言の執行
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅵ 遺言執行者の地位
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅶ 遺言執行者の復任権
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅷ 実務への影響
第4節 法務局における自筆証書遺言書の保管等
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 自筆証書遺言書の保管の現状と問題点
Ⅲ 法務局における遺言書の保管制度の創設意義
? 自筆証書遺言書作成の促進と相続人間の紛争防止 ? 全国一律サービス ? 相続登記の促進
Ⅳ 遺言書保管法の期待と不安
? 検認手続の省略化
? 遺言書情報証明書(遺言書保管法9条)の交付
? 遺言書情報証明書交付のための必要書類
? 公正証書遺言との比較
Ⅴ 遺言書保管法による保管の概要
? 遺言書の保管の申請
? 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
? 遺言書保管事実証明書(遺言書保管法10条)の交付 ? 手数料
第5章 遺留分制度に関する見直し
第1節 遺留分制度と遺留分を算定するための財産
【概 説】
Ⅰ 遺留分請求の性質
? 遺留分制度 ? 改正前の遺留分の取扱いと問題点
? 改正民法における遺留分の取扱い ? 遺留分請求の期間制限
Ⅱ 「遺留分を算定するための財産」の計算方法
? 対象となる贈与の範囲(改正民1044条)
? 負担付贈与(改正民1045条1項)? 不相当な対価による有償行為(改正民1045条2項)
Ⅲ 遺留分権利者及び遺留分割合
第2節 遺留分の請求
【概 説】
Ⅰ 遺留分額(改正民1042条)
? 遺留分額の算定方法 ? 改正前の民法からの変更点
Ⅱ 遺留分侵害額(改正民1046条2項)
? 遺留分侵害額の算定方法
? 遺留分権利者が受けた改正民法903条1項に規定する贈与(特別受益)の価額
? 民法899条の規定により遺留分権利者が承継する債務
? 改正前の民法からの変更点
Ⅲ 受遺者の範囲(改正民1046条1項)
? 改正民法における明確化 ? 改正前の民法からの変更点
Ⅳ 受遺者又は受贈者の負担額(改正民1047条)
? 改正民法における規律 ? 改正民法1047条1項各号の規定
? 負担の順序 ? 遺贈又は贈与の範囲 ? 改正前民法からの変更点
Ⅴ 相続人が受遺者又は受贈者である場合の「目的の価額」(改正民1047条
1項柱書)
? 改正民法1047条1項柱書の規律
? 改正前民法からの変更点
Ⅵ 「目的の価額」の算定方法(改正民1047条2項)
Ⅶ 受遺者又は受贈者が遺留分権利者承継債務を消滅させた場合(改正民
1047条3項)
? 改正民法
「概説」と「QA」で詳解!!
■平成30年の相続法改正のポイントを全7章立てでピックアップ。
■QAでは改正点のみならず関連事項にも触れてトータルに解説。
■法改正に係る税務情報やトピカルなテーマのコラムなども充実。
第1章 相続法改正の経緯
【概 説】
Ⅰ 相続法改正の経緯
? 従来の主要な改正 ? 今回の改正の経緯 ? 中間試案の内容
? 追加試案の内容
Ⅱ 今回の相続法改正の概要
? 配偶者の居住を保護するための方策 ? 遺産分割等に関する見直し ? 遺言制度に関する見直し ? 遺留分制度に関する見直し ? 相続の効力等に関する見直し ? 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 ? 施行期日
Ⅲ ま と め
第2章 配偶者の居住権
第1節 配偶者居住権
【概 説】
Ⅰ 配偶者居住権とは
Ⅱ 改正前の問題点
Ⅲ 配偶者居住権の成立要件
Ⅳ 配偶者居住権の消滅
Ⅴ 審判による配偶者居住権の取得
Ⅵ 配偶者居住権の存続期間
Ⅶ 配偶者居住権の登記等
? 登記請求権 ? 第三者対抗要件 ? 妨害の停止の請求等
Ⅷ 配偶者による使用及び収益
? 用法遵守義務 ? 譲渡禁止 ? 改築・増築,第三者の使用・収益
Ⅸ 居住建物の修繕等
Ⅹ 居住建物の費用の負担
? 居住建物の返還等
? 居住建物の返還 ? 損害賠償及び費用償還請求
? 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
XIII 配偶者居住権の法的性質
〔1〕 配偶者居住権の内容及び成立要件
〔2〕 配偶者居住権の効力
[コラム1]配偶者居住権の評価について
〔3〕 配偶者居住権の消滅
第2節 配偶者短期居住権
【概 説】
Ⅰ 配偶者短期居住権とは
? 配偶者短期居住権 ? 改正前の問題点
Ⅱ 配偶者短期居住権の内容
? 法的性質 ? 成立要件等 ? 存続期間 ? 権利の内容
? 居住建物取得者による消滅申入権 ? 相続財産との関係
Ⅲ 配偶者短期居住権の効力
? 使用借権と同様の規律 ? 用法遵守義務及び善管注意義務
? 無断で第三者に使用させることの禁止 ? 居住建物の修繕等
? 居住建物の費用の負担
Ⅳ 配偶者短期居住権の消滅
? 消滅原因 ? 消滅の効果 ? 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第3章 遺産分割等に関する見直し
第1節 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与
【概 説】
Ⅰ はじめに
? 概 要 ? 改正の趣旨
Ⅱ 従前の規定
? 特別受益における持戻し計算 ? 従前の配偶者救済方法
Ⅲ 持戻免除の意思表示の推定規定の概要
? 条 文 ? 持戻免除の意思表示の推定規定の概要
? 遺留分との関係 ? 実務への影響 ? 配偶者居住権への準用
Ⅳ 施行時期及び適用範囲
第2節 預貯金の払戻し
【概 説】
Ⅰ 家庭裁判所の手続を経ない預貯金の引出し
? 制度創設の経緯 ? 払戻しできる額 ? 払戻しの効果
? 払戻請求権の譲渡,差押え,相殺 ? 共同相続人の債権者による預貯金
債権の差押え ? 経過規定
Ⅱ 預貯金債権の仮分割の仮処分
? 制度創設の経緯 ? 仮分割の要件 ? 仮分割の額
? 本分割との関係 ? 債務者(金融機関)との関係
第3節 遺産の一部分割
【概 説】
Ⅰ これまでの一部分割の取扱い
? 一部分割の必要性 ? 改正前の民法での取扱い
Ⅱ 一部分割の明文化
Ⅲ 一部分割の要件
? 遺言で禁止されていないこと(改正民907条1項)
? 協議・調停の場合
? 審判の場合
Ⅳ 一部分割の調停・審判の申立てをする場合
? 遺産の範囲の特定 ? 審判が却下される場合 ? 申立てが競合した場合
Ⅴ 家事事件手続法73条2項との関係
第4節 遺産分割前に財産が処分された場合の遺産の範囲
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 従前の取扱い
Ⅲ 改正民法による新規定
? 条 文 ? 新規定の概要
Ⅳ 実務への影響
第4 章 遺言制度に関する見直し
第1節 自筆証書遺言の方式
【概 説】
Ⅰ 遺言制度について
Ⅱ 自筆証書遺言の方式
? 自書を要件とする理由 ? 自書の負担と必要性 ? 改正法による自書要件の緩和 ? 要件緩和の効果 ? 改正前の判例の参酌
Ⅲ 目録の作成方法
? 改正法の規定 ? 財産目録の対象となる財産 ? 財産目録に記載すべき財産 ? 財産目録を添付する方法 ? 財産目録の作成方法 ? 財産目録への署名押印 ? 財産目録中の加除その他の変更
Ⅳ 遺言書の作成例
第2節 遺贈義務者の引渡義務等
【概 説】
Ⅰ 遺贈義務者の引渡義務についての改正
? 遺贈の目的となる物又は権利が相続財産に属するものである場合
? 遺贈の目的となる物又は権利が遺言者の死亡時において相続財産に属しない場合
Ⅱ 債権法改正との関係
? 遺贈の目的となる物又は権利が相続財産に属するものである場合
? 遺贈の目的となる物又は権利が遺言者の死亡時において相続財産に属しない場合
第3節 遺言執行者の権限の明確化
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 遺言執行者の任務の開始
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅲ 遺言執行者の権利義務
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅳ 遺言の執行の妨害行為の禁止
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅴ 特定財産に関する遺言の執行
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅵ 遺言執行者の地位
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅶ 遺言執行者の復任権
? 条 文 ? 改正の概要
Ⅷ 実務への影響
第4節 法務局における自筆証書遺言書の保管等
【概 説】
Ⅰ はじめに
Ⅱ 自筆証書遺言書の保管の現状と問題点
Ⅲ 法務局における遺言書の保管制度の創設意義
? 自筆証書遺言書作成の促進と相続人間の紛争防止 ? 全国一律サービス ? 相続登記の促進
Ⅳ 遺言書保管法の期待と不安
? 検認手続の省略化
? 遺言書情報証明書(遺言書保管法9条)の交付
? 遺言書情報証明書交付のための必要書類
? 公正証書遺言との比較
Ⅴ 遺言書保管法による保管の概要
? 遺言書の保管の申請
? 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回
? 遺言書保管事実証明書(遺言書保管法10条)の交付 ? 手数料
第5章 遺留分制度に関する見直し
第1節 遺留分制度と遺留分を算定するための財産
【概 説】
Ⅰ 遺留分請求の性質
? 遺留分制度 ? 改正前の遺留分の取扱いと問題点
? 改正民法における遺留分の取扱い ? 遺留分請求の期間制限
Ⅱ 「遺留分を算定するための財産」の計算方法
? 対象となる贈与の範囲(改正民1044条)
? 負担付贈与(改正民1045条1項)? 不相当な対価による有償行為(改正民1045条2項)
Ⅲ 遺留分権利者及び遺留分割合
第2節 遺留分の請求
【概 説】
Ⅰ 遺留分額(改正民1042条)
? 遺留分額の算定方法 ? 改正前の民法からの変更点
Ⅱ 遺留分侵害額(改正民1046条2項)
? 遺留分侵害額の算定方法
? 遺留分権利者が受けた改正民法903条1項に規定する贈与(特別受益)の価額
? 民法899条の規定により遺留分権利者が承継する債務
? 改正前の民法からの変更点
Ⅲ 受遺者の範囲(改正民1046条1項)
? 改正民法における明確化 ? 改正前の民法からの変更点
Ⅳ 受遺者又は受贈者の負担額(改正民1047条)
? 改正民法における規律 ? 改正民法1047条1項各号の規定
? 負担の順序 ? 遺贈又は贈与の範囲 ? 改正前民法からの変更点
Ⅴ 相続人が受遺者又は受贈者である場合の「目的の価額」(改正民1047条
1項柱書)
? 改正民法1047条1項柱書の規律
? 改正前民法からの変更点
Ⅵ 「目的の価額」の算定方法(改正民1047条2項)
Ⅶ 受遺者又は受贈者が遺留分権利者承継債務を消滅させた場合(改正民
1047条3項)
? 改正民法