地球社会の人権論 (芹田健太郎著作集 第2巻)
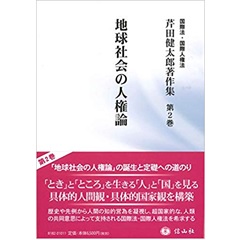
販売価格: 7,150円 税込
◆「人」と「国」を見る国際法・国際人権法 ― 芹田健太郎著作集 第2巻!◆
「とき」と「ところ」を背景に「人」と「国」を見る、具体的人間観、具体的国家観を構築。歴史や先例から人間の知的営為を凝視し、超国家的な人類の共同意思によって支持される国際法・国際人権法を希求する。
第2巻は「国際人権」という言葉だけの一人歩きを脱すべく、「地球社会の人権論」として人権保障を考究し、誕生させ、定礎へと至る道のりを纏めた。論文、書評、講演記録等々収録。
【目 次】
著作集 はしがき
はしがき
◇Ⅰ 国際人権の意義◇
1 人権保障の国際義務の成立
一 国際的人権保障の意味
二 人権の一般法
三 人権諸条約による発展
四 おわりに
2 国際人権の意義について
一 はじめに
二 国際人権法学会の発足
三 国際人権規約発効後の研究状況
四 「国際人権」の登場
五 「国際人権」の意義
六 「国際人権」再論
3 国際人権保障――ヨーロッパの視点から――〔講演録〕
4 (書評)高野雄一著『国際社会における人権』
5 (書評)土井たか子編『「国籍」を考える』
6 (書評)久保田洋著『実践国際人権法』
7 (書評)大沼保昭著『人権、国家、文明』
◇Ⅱ 地球社会の人権◇
8 国家主権と人権
一 人権の国際的保障の必要性
二 戦後人権保障関係小史(一九四五 ― 一九八〇)
三 人権概念の多様化とその位置づけ
9 国際関係における個人の権利と「人民」の権利
一 はじめに
二 「人民」の用語の多様性と不明確さ
三 国際社会における「人民」および「個人」の系譜
四 人権保障の前提としての自決権から発展権論へ
五 おわりに
10 地球社会の人権論の構築――国民国家的人権論の克服――
一 はじめに
二 伝統的人権保障の前提
三 ナチズム・ファシズムからの教訓
四 植民地の独立・低開発からの問題提起
五 「国民国家」形成の不可能性の露呈と新しい課題――エスニシティの登場・普遍化――
六 おわりに
◇Ⅲ 国際連合と世界人権宣言◇
11 国連における人権問題の取扱い――世界人権宣言二〇周年テヘラン会議――
一 はじめに
二 現在における人権をめぐる問題―― 一九六八年国際人権会議の議題と決議
三 テヘラン会議と国連の機関・文書
四 いくつかの問題点
12 世界人権宣言採択の経緯と意義――世界人権宣言五〇周年の評価――
一 はじめに
二 前史:ダンバートン・オークス提案と国際機構に関する連合国会議
三 世界人権宣言起草の経緯、主要な争点および位置づけ
四 おわりに:世界人権宣言の与えた影響と二一世紀への役割
◇Ⅳ アジアの人権保障と日本の役割◇
13 日本による人権の受容と実施
一 はじめに
二 日本における人権の発展
三 人権の実施――緩やかな国際的枠組と国内的実施
四 人権の普遍性と特殊性
五 おわりに
14 東アジア人権委員会設立の提案――東アジアにおける国際人権保障制度設立の可能性――
一 はじめに
二 欧州人権保障制度
三 米州人権保障制度
四 アフリカ人権保障制度
五 東アジア人権保障機構設立の可能性
六 おわりに――東アジア人権委員会の機能と権限(案)
◇Ⅴ 国際人権と日本◇
15 国際人権規約の意義と日本の批准問題―― 一九七六年――〔講演録〕
一 国際人権規約の背景
二 国際人権規約の内容
三 日本と国際人権規約
16 (座談会)国際人権規約と弁護士実務
一 国際人権規約の国内法的効力―― 一般理論
二 社会権A・自由権B両規約に規定されている権利の保障方法
三 社会権A規約の国内法的効力
四 自由権B規約の国内法的効力
五 国際人権規約の国際法的効力
17 七千人を超える指紋押捺拒否者たち―― 一九八五年――
一 もう一人の私
二 よそ者への態度
三 相互主義の現実と平等主義の理想
四 外国人の一般的権利・義務
五 在日外国人の実態
六 在日外国人の人権
七 いわゆる国籍条項
八 外国人登録
九 人権と社会
18 大震災の経験からの提唱「弱者・少数者の幸福はすべての者の幸福」――「最大多数の最大幸福」からの脱却――
一 市民とNGOの「防災」国際フォーラム
二 「震災下」とは、いつまでか
三 内外人平等原則
四 「法と行政」のめざすところ――弱者保護――
補章 国際人権規約の意義と国内的効力
あとがき
「とき」と「ところ」を背景に「人」と「国」を見る、具体的人間観、具体的国家観を構築。歴史や先例から人間の知的営為を凝視し、超国家的な人類の共同意思によって支持される国際法・国際人権法を希求する。
第2巻は「国際人権」という言葉だけの一人歩きを脱すべく、「地球社会の人権論」として人権保障を考究し、誕生させ、定礎へと至る道のりを纏めた。論文、書評、講演記録等々収録。
【目 次】
著作集 はしがき
はしがき
◇Ⅰ 国際人権の意義◇
1 人権保障の国際義務の成立
一 国際的人権保障の意味
二 人権の一般法
三 人権諸条約による発展
四 おわりに
2 国際人権の意義について
一 はじめに
二 国際人権法学会の発足
三 国際人権規約発効後の研究状況
四 「国際人権」の登場
五 「国際人権」の意義
六 「国際人権」再論
3 国際人権保障――ヨーロッパの視点から――〔講演録〕
4 (書評)高野雄一著『国際社会における人権』
5 (書評)土井たか子編『「国籍」を考える』
6 (書評)久保田洋著『実践国際人権法』
7 (書評)大沼保昭著『人権、国家、文明』
◇Ⅱ 地球社会の人権◇
8 国家主権と人権
一 人権の国際的保障の必要性
二 戦後人権保障関係小史(一九四五 ― 一九八〇)
三 人権概念の多様化とその位置づけ
9 国際関係における個人の権利と「人民」の権利
一 はじめに
二 「人民」の用語の多様性と不明確さ
三 国際社会における「人民」および「個人」の系譜
四 人権保障の前提としての自決権から発展権論へ
五 おわりに
10 地球社会の人権論の構築――国民国家的人権論の克服――
一 はじめに
二 伝統的人権保障の前提
三 ナチズム・ファシズムからの教訓
四 植民地の独立・低開発からの問題提起
五 「国民国家」形成の不可能性の露呈と新しい課題――エスニシティの登場・普遍化――
六 おわりに
◇Ⅲ 国際連合と世界人権宣言◇
11 国連における人権問題の取扱い――世界人権宣言二〇周年テヘラン会議――
一 はじめに
二 現在における人権をめぐる問題―― 一九六八年国際人権会議の議題と決議
三 テヘラン会議と国連の機関・文書
四 いくつかの問題点
12 世界人権宣言採択の経緯と意義――世界人権宣言五〇周年の評価――
一 はじめに
二 前史:ダンバートン・オークス提案と国際機構に関する連合国会議
三 世界人権宣言起草の経緯、主要な争点および位置づけ
四 おわりに:世界人権宣言の与えた影響と二一世紀への役割
◇Ⅳ アジアの人権保障と日本の役割◇
13 日本による人権の受容と実施
一 はじめに
二 日本における人権の発展
三 人権の実施――緩やかな国際的枠組と国内的実施
四 人権の普遍性と特殊性
五 おわりに
14 東アジア人権委員会設立の提案――東アジアにおける国際人権保障制度設立の可能性――
一 はじめに
二 欧州人権保障制度
三 米州人権保障制度
四 アフリカ人権保障制度
五 東アジア人権保障機構設立の可能性
六 おわりに――東アジア人権委員会の機能と権限(案)
◇Ⅴ 国際人権と日本◇
15 国際人権規約の意義と日本の批准問題―― 一九七六年――〔講演録〕
一 国際人権規約の背景
二 国際人権規約の内容
三 日本と国際人権規約
16 (座談会)国際人権規約と弁護士実務
一 国際人権規約の国内法的効力―― 一般理論
二 社会権A・自由権B両規約に規定されている権利の保障方法
三 社会権A規約の国内法的効力
四 自由権B規約の国内法的効力
五 国際人権規約の国際法的効力
17 七千人を超える指紋押捺拒否者たち―― 一九八五年――
一 もう一人の私
二 よそ者への態度
三 相互主義の現実と平等主義の理想
四 外国人の一般的権利・義務
五 在日外国人の実態
六 在日外国人の人権
七 いわゆる国籍条項
八 外国人登録
九 人権と社会
18 大震災の経験からの提唱「弱者・少数者の幸福はすべての者の幸福」――「最大多数の最大幸福」からの脱却――
一 市民とNGOの「防災」国際フォーラム
二 「震災下」とは、いつまでか
三 内外人平等原則
四 「法と行政」のめざすところ――弱者保護――
補章 国際人権規約の意義と国内的効力
あとがき