10訂 民事判決起案の手引(補訂版)

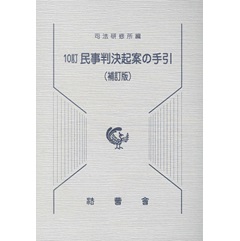
販売価格: 1,950円 税込
初めて民事判決の起案を試みる司法修習生のために、判決書の記載の形式、表現方法などをできる限り平易かつ具体的に説明した基礎的教材である。
初版は昭和33年の刊行であるが、その後も実務の動向に対応しつつ、体系的な整備や理論的な解明による内容の充実を図るべく、数次の改訂がなされてきた。
巻末に「事実摘示記載例集」及び「事実摘示記載例集―民法(債権関係)改正に伴う補訂版―」を合冊のうえ、補訂版とした。
目次
第1章 判決書作成の目的
第2章 在来様式による判決書
第1 事件の表示
1 表示の方法
2 事件番号
3 事件名
第2 口頭弁論の終結の日
第3 表題
第4 当事者,代理人等の表示
1 当事者
2 法定代理人及び法人の代表者
3 訴訟代理人
4 送達場所
第5 主文
1 主文の意義
2 訴え却下の主文
3 請求棄却の主文
4 請求認容の主文
(1) 給付判決の主文
ア 金員の支払を命ずる主文
イ 引換給付の主文
ウ 登記に関する主文
(2) 確認判決の主文
(3) 形成判決の主文
5 別紙目録,図面の利用
(1) 物件目録,図面の利用
(2) 登記目録の利用
6 訴訟費用に関する主文
(1) 記載の必要,内容,場所
(2) 記載の具体的方法
ア 一般の場合
イ 特殊な場合
(ア) 共同訴訟の場合
(イ) 反訴が提起されている場合
7 仮執行の宣言
(1) 仮執行の宣言の要否,判断基準
(2) 担保提供の要否,その額,判断基準
(3) 仮執行の宣言の許否が問題となる場合
ア 確認判決
イ 形成判決
ウ 意思表示を命ずる判決
エ 訴訟費用の負担の裁判
(4) 主文記載の必要,内容,場所
(5) 担保提供の方法
8 仮執行免脱の宣言
第6 事実
1 表題
2 事実摘示の構成
3 請求の趣旨
(1) 請求の趣旨の記載
(2) 訴訟費用の負担の申立て
(3) 仮執行の宣言の申立て
(4) 主文の引用
4 請求の趣旨に対する答弁
5 請求原因
(1) 請求原因の意義
(2) 請求原因の整理
(3) 請求原因を記載するに当たって注意すべき点
ア 口頭弁論において陳述された主張に限ること
イ 主張責任を考えること
ウ 主張を正確に記載すること
エ 主張は具体的に記述すること
オ 間接事実の主張
カ 他の書面の引用
キ 訴えの併合がされた場合
ク 攻撃方法としての請求原因が複数ある場合
ケ 分離前の当事者の呼称
コ 主張の要約(よって書き)
6 請求原因に対する認否
(1) 認否の記載方法
(2) 自白
(3) 否認
(4) 不知
(5) 沈黙
(6) 被告が複数の場合
(7) 法律上の主張
(8) 間接事実の主張
(9) 時機に後れた攻撃防御方法であるとの申立て
7 抗弁
(1) 抗弁の記載方法
(2) 抗弁記載の順序
8 抗弁に対する認否
9 再抗弁以下
第7 理由
1 理由の構成
(1) 理由の基本的構造
(2) 判断の記載順序
2 事実の確定
(1) 証拠を要しない場合
ア 自白した事実
イ 顕著な事実
(2) 証拠によるべき場合
ア 事実認定
イ 説示の方法
(ア) 原則
(イ) 証拠の挙示の仕方
a 書証
① 公文書
② 私文書
b 人証
① 証人
② 当事者本人,代表者
c 鑑定
d 検証
e 調査嘱託,鑑定嘱託
f 弁論の全趣旨
(ウ) 説示の要領
[事実を認定することができる場合]
a 直接証拠により主要事実を認定できる場合(直接認定型)
b 間接事実から主要事実を推認できる場合(間接推認型)
[事実を認定することができない場合]
c 主要事実又はそれを推認させる間接事実を認定するに足りる証拠がない場合(証拠不十分型)
d 間接事実は認定できるが,それから主要事実を推認することができない場合(推認不十分型)
3 法律の適用
4 訴訟費用の負担の裁判及び仮執行の宣言についての理由
5 結論
第8 裁判所の表示
第9 判決をした裁判官の署名押印
第3章 新様式による判決書
第1 事件の表示,口頭弁論の終結の日,表題,当事者,代理人等の表示
第2 主文
第3 事実及び理由
1 請求
2 事案の概要
3 争点に対する判断
第4 裁判所の表示及び判決をした裁判官の署名押印
第4章 請求原因自白,被告欠席の場合の判決書
第1 被告が請求原因事実を認め,抗弁を主張しない場合
第2 被告が公示送達以外の呼出しを受けて欠席した場合
第3 被告が公示送達による呼出しを受けて欠席した場合
第4 いわゆる調書判決
判決記載例(在来様式)
判決記載例(新様式)
(巻末)
事実摘示記載例集(平成18年8月)
事実摘示記載例集―民法(債権関係)改正に伴う補訂版―(令和元年10月)
初版は昭和33年の刊行であるが、その後も実務の動向に対応しつつ、体系的な整備や理論的な解明による内容の充実を図るべく、数次の改訂がなされてきた。
巻末に「事実摘示記載例集」及び「事実摘示記載例集―民法(債権関係)改正に伴う補訂版―」を合冊のうえ、補訂版とした。
目次
第1章 判決書作成の目的
第2章 在来様式による判決書
第1 事件の表示
1 表示の方法
2 事件番号
3 事件名
第2 口頭弁論の終結の日
第3 表題
第4 当事者,代理人等の表示
1 当事者
2 法定代理人及び法人の代表者
3 訴訟代理人
4 送達場所
第5 主文
1 主文の意義
2 訴え却下の主文
3 請求棄却の主文
4 請求認容の主文
(1) 給付判決の主文
ア 金員の支払を命ずる主文
イ 引換給付の主文
ウ 登記に関する主文
(2) 確認判決の主文
(3) 形成判決の主文
5 別紙目録,図面の利用
(1) 物件目録,図面の利用
(2) 登記目録の利用
6 訴訟費用に関する主文
(1) 記載の必要,内容,場所
(2) 記載の具体的方法
ア 一般の場合
イ 特殊な場合
(ア) 共同訴訟の場合
(イ) 反訴が提起されている場合
7 仮執行の宣言
(1) 仮執行の宣言の要否,判断基準
(2) 担保提供の要否,その額,判断基準
(3) 仮執行の宣言の許否が問題となる場合
ア 確認判決
イ 形成判決
ウ 意思表示を命ずる判決
エ 訴訟費用の負担の裁判
(4) 主文記載の必要,内容,場所
(5) 担保提供の方法
8 仮執行免脱の宣言
第6 事実
1 表題
2 事実摘示の構成
3 請求の趣旨
(1) 請求の趣旨の記載
(2) 訴訟費用の負担の申立て
(3) 仮執行の宣言の申立て
(4) 主文の引用
4 請求の趣旨に対する答弁
5 請求原因
(1) 請求原因の意義
(2) 請求原因の整理
(3) 請求原因を記載するに当たって注意すべき点
ア 口頭弁論において陳述された主張に限ること
イ 主張責任を考えること
ウ 主張を正確に記載すること
エ 主張は具体的に記述すること
オ 間接事実の主張
カ 他の書面の引用
キ 訴えの併合がされた場合
ク 攻撃方法としての請求原因が複数ある場合
ケ 分離前の当事者の呼称
コ 主張の要約(よって書き)
6 請求原因に対する認否
(1) 認否の記載方法
(2) 自白
(3) 否認
(4) 不知
(5) 沈黙
(6) 被告が複数の場合
(7) 法律上の主張
(8) 間接事実の主張
(9) 時機に後れた攻撃防御方法であるとの申立て
7 抗弁
(1) 抗弁の記載方法
(2) 抗弁記載の順序
8 抗弁に対する認否
9 再抗弁以下
第7 理由
1 理由の構成
(1) 理由の基本的構造
(2) 判断の記載順序
2 事実の確定
(1) 証拠を要しない場合
ア 自白した事実
イ 顕著な事実
(2) 証拠によるべき場合
ア 事実認定
イ 説示の方法
(ア) 原則
(イ) 証拠の挙示の仕方
a 書証
① 公文書
② 私文書
b 人証
① 証人
② 当事者本人,代表者
c 鑑定
d 検証
e 調査嘱託,鑑定嘱託
f 弁論の全趣旨
(ウ) 説示の要領
[事実を認定することができる場合]
a 直接証拠により主要事実を認定できる場合(直接認定型)
b 間接事実から主要事実を推認できる場合(間接推認型)
[事実を認定することができない場合]
c 主要事実又はそれを推認させる間接事実を認定するに足りる証拠がない場合(証拠不十分型)
d 間接事実は認定できるが,それから主要事実を推認することができない場合(推認不十分型)
3 法律の適用
4 訴訟費用の負担の裁判及び仮執行の宣言についての理由
5 結論
第8 裁判所の表示
第9 判決をした裁判官の署名押印
第3章 新様式による判決書
第1 事件の表示,口頭弁論の終結の日,表題,当事者,代理人等の表示
第2 主文
第3 事実及び理由
1 請求
2 事案の概要
3 争点に対する判断
第4 裁判所の表示及び判決をした裁判官の署名押印
第4章 請求原因自白,被告欠席の場合の判決書
第1 被告が請求原因事実を認め,抗弁を主張しない場合
第2 被告が公示送達以外の呼出しを受けて欠席した場合
第3 被告が公示送達による呼出しを受けて欠席した場合
第4 いわゆる調書判決
判決記載例(在来様式)
判決記載例(新様式)
(巻末)
事実摘示記載例集(平成18年8月)
事実摘示記載例集―民法(債権関係)改正に伴う補訂版―(令和元年10月)