Q&A 課税実務における有利・不利判定
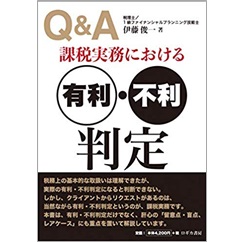
販売価格: 4,620円 税込
税務上の基本的な取扱いは理解できたが、実際の有利・不利判定になると判断できない。しかし、クライアントからリクエストがあるのは、当然ながら有利・不利判定というのが、課税実務です。
本書は、有利・不利判定だけでなく、肝心の「留意点・盲点、レアケースの」にも重点を置いて解説しています。
◎目次
Ⅰ 不動産関連税制
QⅠ-1 社長(オーナー)の自宅購入は、「個人購入」と「法人購入」どちらが有利?
QⅠ-2 「居住用財産3,000万円控除の特例適用」と「住宅ローン控除適用」どちらが有利?
QⅠ-3 土地売却時の取得費は、「概算取得費を用いる」と「市街地価格指数を用いる」どちらが有利?
QⅠ-4 借地権について、「事後に無償返還届出書を提出」と「自然発生借地権を算定し等価交換」どちらが有利?
QⅠ-5 不動産所有型法人スキーム策定において、「土地建物ともに売却」と「建物のみ売却」どちらが有利?
Ⅱ 複数税目関係
QⅡ-1 「役員報酬の増額」と「法人課税所得の増加」どちらが有利?
QⅡ-2 社長(オーナー)からの貸付金、「生前に精算する」と「精算しない」どちらが有利?
QⅡ-3 オーナーへの貸付金は、「解消する」と「解消しない」どちらが有利?
QⅡ-4 退職金を、「現金で支給する」と「現物で支給する」どちらが有利?
Ⅲ 資本戦略・組織再編成・M&A に係る税制
QⅢ-1 株主への資金還元方法として、「配当する」と「配当しない」どちらが有利?
補問A 完全支配関係(100%グループ内)の資産移転方法について、基本的な留意事項
補問B 保険積立金は譲渡損益調整資産か?また、適格現物分配できるか?
QⅢ-2 配当するなら、「資本剰余金を配当する」と「自己株式の取得(金庫株)にする」どちらが有利?
QⅢ-3 事業M&A における、「株式譲渡スキーム」と「事業譲渡スキーム」どちらが有利?
QⅢ-4 株式譲渡スキーム事業M&A において売主が個人・買手が法人の場合、「単純売却」と「売却前に種々の手法を重ねて使う」どちらが有利?
【実践例1 】株式譲渡スキームにおける個人株主、法人株主混在パターンの実例、違法配当の有効性
【実践例2 】医療法人M&A の実践事例/理事退職金の過大性の考え方
【実践例3 】同族法人間M&A において事業譲渡した場合の営業権の評価
【実践例4 】第三者M&A において欠損会社が事業譲渡する場合における営業権の評価
【実践例5 】得意先を含めた資産の譲渡の所得区分
【実践例6 】税理士事務所の事業承継 営業権譲渡に係る課税関係
補問C? M&A 関連費用の取扱い
QⅢ-5 少数株主からの買取請求があった時、「そのまま応じる」と「非訟事件にする」どちらが有利?
QⅢ-6 不要不動産を切り分けたい場合、「不動産をそのまま売却する」と「不動産会社株式を売却する」どちらが有利?
QⅢ-7 会社の期限切れ欠損金がたまっている場合、「そのまま切り捨てる」と「何らかの収益付けをして欠損金を解消する」どちらが有利?
Ⅳ 個人資産税・法人資産税(相続税・贈与税・所得税)に係る税制
QⅣ-1 「養子縁組をする」と「しない」どちらが有利?
補問D 再転相続の有利・不利判定
QⅣ-2 各事業体の比較について、パス・スルー課税の諸論点と、業種に合った事業体選択の有利・不利
QⅣ-3 「生前贈与する」と「相続税を支払う」どちらが有利?
QⅣ-4 「オーナー個人財産の法人への流入」と「事業承継税制をそのまま適用」どちらが有利?「持株会社にする」と「本体会社そのままに適用する」どちらが有利?
補問E 事業承継税制(特例)適用時のクライアント要請別の有利・不利判定
QⅣ-5 贈与税の納税猶予において「相続時精算課税併用(平成29年度改正)」と「暦年課税」どちらが有利?
QⅣ-6 個人確定申告における、「純損失の繰越控除」と「繰戻還付」どちらが有利?
補問F 個人事業の事業廃止の意義とは
Ⅴ 消費税・印紙税に係る税制
QⅤ-1 消費税、「本則課税」と「簡易課税」どちらが有利?
QⅤ-2 消費税、「一括比例配分方式採用」と「個別対応方式採用」どちらが有利?
QⅤ-3 契約書の記載事項による有利・不利
【資料1 】誤りやすい事例集(資産課税編)
【資料2 】資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係)
【資料3 】質疑応答事例 土壌汚染地の評価
【資料4 】3000万円特別控除制度創設までの居住用財産を譲渡した場合の特例の経緯
本書は、有利・不利判定だけでなく、肝心の「留意点・盲点、レアケースの」にも重点を置いて解説しています。
◎目次
Ⅰ 不動産関連税制
QⅠ-1 社長(オーナー)の自宅購入は、「個人購入」と「法人購入」どちらが有利?
QⅠ-2 「居住用財産3,000万円控除の特例適用」と「住宅ローン控除適用」どちらが有利?
QⅠ-3 土地売却時の取得費は、「概算取得費を用いる」と「市街地価格指数を用いる」どちらが有利?
QⅠ-4 借地権について、「事後に無償返還届出書を提出」と「自然発生借地権を算定し等価交換」どちらが有利?
QⅠ-5 不動産所有型法人スキーム策定において、「土地建物ともに売却」と「建物のみ売却」どちらが有利?
Ⅱ 複数税目関係
QⅡ-1 「役員報酬の増額」と「法人課税所得の増加」どちらが有利?
QⅡ-2 社長(オーナー)からの貸付金、「生前に精算する」と「精算しない」どちらが有利?
QⅡ-3 オーナーへの貸付金は、「解消する」と「解消しない」どちらが有利?
QⅡ-4 退職金を、「現金で支給する」と「現物で支給する」どちらが有利?
Ⅲ 資本戦略・組織再編成・M&A に係る税制
QⅢ-1 株主への資金還元方法として、「配当する」と「配当しない」どちらが有利?
補問A 完全支配関係(100%グループ内)の資産移転方法について、基本的な留意事項
補問B 保険積立金は譲渡損益調整資産か?また、適格現物分配できるか?
QⅢ-2 配当するなら、「資本剰余金を配当する」と「自己株式の取得(金庫株)にする」どちらが有利?
QⅢ-3 事業M&A における、「株式譲渡スキーム」と「事業譲渡スキーム」どちらが有利?
QⅢ-4 株式譲渡スキーム事業M&A において売主が個人・買手が法人の場合、「単純売却」と「売却前に種々の手法を重ねて使う」どちらが有利?
【実践例1 】株式譲渡スキームにおける個人株主、法人株主混在パターンの実例、違法配当の有効性
【実践例2 】医療法人M&A の実践事例/理事退職金の過大性の考え方
【実践例3 】同族法人間M&A において事業譲渡した場合の営業権の評価
【実践例4 】第三者M&A において欠損会社が事業譲渡する場合における営業権の評価
【実践例5 】得意先を含めた資産の譲渡の所得区分
【実践例6 】税理士事務所の事業承継 営業権譲渡に係る課税関係
補問C? M&A 関連費用の取扱い
QⅢ-5 少数株主からの買取請求があった時、「そのまま応じる」と「非訟事件にする」どちらが有利?
QⅢ-6 不要不動産を切り分けたい場合、「不動産をそのまま売却する」と「不動産会社株式を売却する」どちらが有利?
QⅢ-7 会社の期限切れ欠損金がたまっている場合、「そのまま切り捨てる」と「何らかの収益付けをして欠損金を解消する」どちらが有利?
Ⅳ 個人資産税・法人資産税(相続税・贈与税・所得税)に係る税制
QⅣ-1 「養子縁組をする」と「しない」どちらが有利?
補問D 再転相続の有利・不利判定
QⅣ-2 各事業体の比較について、パス・スルー課税の諸論点と、業種に合った事業体選択の有利・不利
QⅣ-3 「生前贈与する」と「相続税を支払う」どちらが有利?
QⅣ-4 「オーナー個人財産の法人への流入」と「事業承継税制をそのまま適用」どちらが有利?「持株会社にする」と「本体会社そのままに適用する」どちらが有利?
補問E 事業承継税制(特例)適用時のクライアント要請別の有利・不利判定
QⅣ-5 贈与税の納税猶予において「相続時精算課税併用(平成29年度改正)」と「暦年課税」どちらが有利?
QⅣ-6 個人確定申告における、「純損失の繰越控除」と「繰戻還付」どちらが有利?
補問F 個人事業の事業廃止の意義とは
Ⅴ 消費税・印紙税に係る税制
QⅤ-1 消費税、「本則課税」と「簡易課税」どちらが有利?
QⅤ-2 消費税、「一括比例配分方式採用」と「個別対応方式採用」どちらが有利?
QⅤ-3 契約書の記載事項による有利・不利
【資料1 】誤りやすい事例集(資産課税編)
【資料2 】資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得関係)
【資料3 】質疑応答事例 土壌汚染地の評価
【資料4 】3000万円特別控除制度創設までの居住用財産を譲渡した場合の特例の経緯