新版 残業代請求の理論と実務

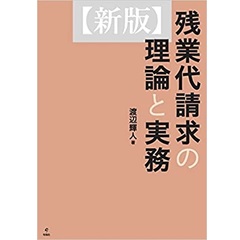
販売価格: 4,400円 税込
出版社・至誠堂品切れ中
好評だった前作を大幅に改定!
最新の判決と学説の理論状況を丁寧に分析した、残業代請求に関する理論書であり、最強の実務書!
・最新の最高裁判決(2020年)と学説動向を分析
・最先端の理論で、残業代請求実務がさらに確実に
・残業代計算ソフト「給与第一」「きょうとソフト」解説付き
〇目次
新版はしがき
初版はしがき
凡例
用語法・言葉の定義
第1部 割増賃金制度の理論
第1章 法定の計算方法と法定外の支払方法の許容性
第1 割増賃金制度の概略
1 労基法における労働時間規制の概略
2 割増賃金制度の趣旨
(1)最高裁判決
(2)労働行政の見解
(3)学説状況
(4)まとめ
3 法定の計算方法の概略
(1)根拠条文
(2)具体的計算方法
(3)賃金形態別の賃金単価の算出方法の概略
(4)賃金形態別の賃金単価の合算
第2 法定外の支払方法の許容性
1 労基法37条の強行的・直律的効力の範囲(法定外の支払方法の許容)
2 最高裁判決によりただちに違法ではないとされたこと
第3 通常の労働時間の賃金
1 概念整理の必要性
2 「通常の労働時間の賃金」という文言の特定
3 除外賃金との関係での通常の労働時間の賃金の定義
4 25%説の「通常の賃金」と通常の労働時間の賃金の関係
5 判別要件との関係での論点設定
第2章 判別要件(法定外の支払方法の有効要件)
第1 法定外の支払方法全般と全種の割増賃金を対象に
1 「固定残業代」の定義
2 当初の判別対象
3 康心会事件最高裁判決での対象の根本的拡大
4 従前の学説の問題点
5 小括:判別要件を法定外の支払方法全般へ拡大
6 すべての種類の割増賃金を判別要件の対象に
(1)深夜早朝割増賃金についての従前の労働行政、裁判例の状況
(2)ことぶき事件最高裁判決
(3)康心会事件最高裁判決で判別要件へ編入
(4)小括
第2 「判別」することの内容の深化
1 高知県観光事件最判の「判別」
2 テックジャパン事件での月給制への射程拡大
3 国際自動車事件第一次判決で賃金の計算過程まで射程を拡大
4 康心会事件最高裁判決の「すら」
5 国際自動車事件第二次最高裁判決での「置き換え」=判別不能の判示
第3 法37条の「趣旨による判別」
1 国際自動車事件第一次判決の投げかけた問題点
2 康心会事件最高裁判決以降の「趣旨による判別」
3 国際自動車事件第二次最高裁判決の「趣旨を踏まえた」対価性検討
4 小括
第4 対価性要件を判別要件の下に位置づけたこと
1 日本ケミカル事件の概要
2 対価性要件と判別要件の関係
3 担当調査官の見解
4 国際自動車事件第二次最高裁判決での対価性要件の位置付けの明確化
第5 判別要件は契約の定めにつきなされるものと位置付けられたこと
第6 まとめ:判別要件及び通常の労働時間の賃金の意義
1 判別要件の意義
(1)強行的・直律的効力のある「基準」としての判別要件の射程
(2)判別要件の目的
(3)誰にとっての「判別」可能性か
(4)判別可能性の立証責任
2 通常の労働時間の賃金の意義:客観説
3 まとめ
第3章 判別要件を基本とする対価性要件の具体的内容
第1 対価性要件の固有の意義
1 不定形性の指摘との関係での固有の意義
2 弁済との関係での対価性の範囲
(1)問題の所在
(2)固定残業代による対価性の時間的範囲
(3)同時に2種以上の割増賃金の支払対象となる労働時間を引き当てにする手当
(4)小括
第2 日本ケミカル事件の事案の詳細
1 入職2ヶ月前の雇用契約書で合意された週の各曜日の所定労働時間等
(1)週所定労働時間
(2)休日
(3)月平均所定労働時間数
2 賃金に関する契約書面の記載内容
(1)入職2ヶ月前の雇用契約書
(2)本件雇用契約に係る採用条件確認書
(3)賃金規定
3 業務手当について、会社と他の労働者の間で作成された確認書の記載
4 労働実態
(1)時間外労働時間
(2)残業代に関する給与明細書の記載
第3 対価性要件の具体的当てはめ内容
第4 対価性要件の考慮要素の検討
1 3つの要素の関係と意義
2 事例への当てはめの特徴
(1)労働契約上の所定労働時間の範囲と対価性の関係
(2)実際の残業時間と対価性の関係
(3)その他の事情の取り扱い
3 小括
第4章 固定残業代の具体的要件
第1 賃金算定期間と賃金締切期間
第2 時給制による支払の要件
1 時給制の賃金と通常の労働時間の賃金
2 時給制の賃金による割増賃金支払い
第3 日給制による支払いの要件
1 日給制の賃金の性質と通常の労働時間の賃金との関係
2 「休日手当」(労基則19条2項)
3 裁判例の状況
4 限界的事例の検討
第4 月給制(狭義の固定残業代)の要件
1 「通常の月給制」の原則
2 給与明細書による「明確区分」
3 就業規則で基準外賃金とされていること
4 賃金の性質が問題になる場面ごとの展開
(1)入職時
(2)賃金改定時
(3)昇給・昇進時
5 労働契約書(就業規則)に「残業代として支払う」と明記してある
(1)募集広告、求人票の記載やそれとの矛盾の追及
(2)労働契約に関する文書での記載の不備や文書同士の齟齬の追及
(3)労働契約における固定残業代の位置付けの不合理性
(4)労働時間と固定残業代の関係
(5)賃金増額を伴う場合
(6)通常の労働時間の賃金の減額を伴う場合
6 固定残業代を認めた裁判例の評価
(1)関西ソニー販売事件
(2)名鉄運輸事件
(3)ユニ・フレックス事件
(4)東和システム事件
(5)ワークフロンティア事件
(6)泉レストラン事件
(7)コロワイドMD(旧コロワイド東日本)事件
(8)結婚式場運営会社A事件
7 固定残業代の合意が無効になる場合
(1)時間外労働等に罰則付きの上限値の導入
(2)上限を超える固定残業代の契約の無効
(3)無効になる範囲
(4)無効の場合の具体的な計算方法
(5)制限値をどう考えるか
(6)三六協定未締結の場合
(7)公序良俗違反による無効
第5章 請負制(歩合給)による割増賃金の支払いの可否
第1 労基法24条との関係での請負制賃金の法的性質
1 請負制の意義
2 請負制賃金からの経費控除
第2 請負制の賃金の性質と通常の労働時間の賃金との関係
1 請負制の通常の労働時間の賃金
2 請負制の賃金該当性そのものが争点になった事例
第3 月決めの請負制の賃金全体を割増賃金とする場合
第4 月決めの出来高払制賃金の中に割合による仕切を設定する例(仕切説)
第5 通常の労働時間の賃金からの割増賃金相当額等の控除
1 割増賃金相当額の控除
(1)国際自動車事件第二次最高裁判決の要旨
(2)通常の労働時間の賃金の意義に言及がなかったことについて
(3)法37条の趣旨の実現の程度
(4)出来高制の定義がされたこととの関係での「置き換え」の意義
2 過去の平均割増賃金額の控除
3 定率・定額の控除
4 小括
第6 日決めの出来高払制等を用いて時間外労働等の時間帯のみの水揚げに対する歩合給
第7 時間決めの請負制賃金の場合
第8 まとめ
第6章 法定外の支払方法に関する学説
第1 時間賃率の未成熟
第2 固定残業代等の制度の由来
1 法定外の計算方法
2 深夜早朝割増賃金を含める所定賃金
3 日給制の手当による支払い
4 請負制の計算方法による支払い
5 狭義の固定残業代
6 狭義の固定残業代の幅広い普及経緯についての仮説
第3 必要性の乏しさ(固定残業代のメリット論批判)
1 メリットがないこと
2 使用者側から語られる社会的なメリットの検討
(1)使用者側が主張する社会的なメリット
最新の判決と学説の理論状況を丁寧に分析した、残業代請求に関する理論書であり、最強の実務書!
・最新の最高裁判決(2020年)と学説動向を分析
・最先端の理論で、残業代請求実務がさらに確実に
・残業代計算ソフト「給与第一」「きょうとソフト」解説付き
〇目次
新版はしがき
初版はしがき
凡例
用語法・言葉の定義
第1部 割増賃金制度の理論
第1章 法定の計算方法と法定外の支払方法の許容性
第1 割増賃金制度の概略
1 労基法における労働時間規制の概略
2 割増賃金制度の趣旨
(1)最高裁判決
(2)労働行政の見解
(3)学説状況
(4)まとめ
3 法定の計算方法の概略
(1)根拠条文
(2)具体的計算方法
(3)賃金形態別の賃金単価の算出方法の概略
(4)賃金形態別の賃金単価の合算
第2 法定外の支払方法の許容性
1 労基法37条の強行的・直律的効力の範囲(法定外の支払方法の許容)
2 最高裁判決によりただちに違法ではないとされたこと
第3 通常の労働時間の賃金
1 概念整理の必要性
2 「通常の労働時間の賃金」という文言の特定
3 除外賃金との関係での通常の労働時間の賃金の定義
4 25%説の「通常の賃金」と通常の労働時間の賃金の関係
5 判別要件との関係での論点設定
第2章 判別要件(法定外の支払方法の有効要件)
第1 法定外の支払方法全般と全種の割増賃金を対象に
1 「固定残業代」の定義
2 当初の判別対象
3 康心会事件最高裁判決での対象の根本的拡大
4 従前の学説の問題点
5 小括:判別要件を法定外の支払方法全般へ拡大
6 すべての種類の割増賃金を判別要件の対象に
(1)深夜早朝割増賃金についての従前の労働行政、裁判例の状況
(2)ことぶき事件最高裁判決
(3)康心会事件最高裁判決で判別要件へ編入
(4)小括
第2 「判別」することの内容の深化
1 高知県観光事件最判の「判別」
2 テックジャパン事件での月給制への射程拡大
3 国際自動車事件第一次判決で賃金の計算過程まで射程を拡大
4 康心会事件最高裁判決の「すら」
5 国際自動車事件第二次最高裁判決での「置き換え」=判別不能の判示
第3 法37条の「趣旨による判別」
1 国際自動車事件第一次判決の投げかけた問題点
2 康心会事件最高裁判決以降の「趣旨による判別」
3 国際自動車事件第二次最高裁判決の「趣旨を踏まえた」対価性検討
4 小括
第4 対価性要件を判別要件の下に位置づけたこと
1 日本ケミカル事件の概要
2 対価性要件と判別要件の関係
3 担当調査官の見解
4 国際自動車事件第二次最高裁判決での対価性要件の位置付けの明確化
第5 判別要件は契約の定めにつきなされるものと位置付けられたこと
第6 まとめ:判別要件及び通常の労働時間の賃金の意義
1 判別要件の意義
(1)強行的・直律的効力のある「基準」としての判別要件の射程
(2)判別要件の目的
(3)誰にとっての「判別」可能性か
(4)判別可能性の立証責任
2 通常の労働時間の賃金の意義:客観説
3 まとめ
第3章 判別要件を基本とする対価性要件の具体的内容
第1 対価性要件の固有の意義
1 不定形性の指摘との関係での固有の意義
2 弁済との関係での対価性の範囲
(1)問題の所在
(2)固定残業代による対価性の時間的範囲
(3)同時に2種以上の割増賃金の支払対象となる労働時間を引き当てにする手当
(4)小括
第2 日本ケミカル事件の事案の詳細
1 入職2ヶ月前の雇用契約書で合意された週の各曜日の所定労働時間等
(1)週所定労働時間
(2)休日
(3)月平均所定労働時間数
2 賃金に関する契約書面の記載内容
(1)入職2ヶ月前の雇用契約書
(2)本件雇用契約に係る採用条件確認書
(3)賃金規定
3 業務手当について、会社と他の労働者の間で作成された確認書の記載
4 労働実態
(1)時間外労働時間
(2)残業代に関する給与明細書の記載
第3 対価性要件の具体的当てはめ内容
第4 対価性要件の考慮要素の検討
1 3つの要素の関係と意義
2 事例への当てはめの特徴
(1)労働契約上の所定労働時間の範囲と対価性の関係
(2)実際の残業時間と対価性の関係
(3)その他の事情の取り扱い
3 小括
第4章 固定残業代の具体的要件
第1 賃金算定期間と賃金締切期間
第2 時給制による支払の要件
1 時給制の賃金と通常の労働時間の賃金
2 時給制の賃金による割増賃金支払い
第3 日給制による支払いの要件
1 日給制の賃金の性質と通常の労働時間の賃金との関係
2 「休日手当」(労基則19条2項)
3 裁判例の状況
4 限界的事例の検討
第4 月給制(狭義の固定残業代)の要件
1 「通常の月給制」の原則
2 給与明細書による「明確区分」
3 就業規則で基準外賃金とされていること
4 賃金の性質が問題になる場面ごとの展開
(1)入職時
(2)賃金改定時
(3)昇給・昇進時
5 労働契約書(就業規則)に「残業代として支払う」と明記してある
(1)募集広告、求人票の記載やそれとの矛盾の追及
(2)労働契約に関する文書での記載の不備や文書同士の齟齬の追及
(3)労働契約における固定残業代の位置付けの不合理性
(4)労働時間と固定残業代の関係
(5)賃金増額を伴う場合
(6)通常の労働時間の賃金の減額を伴う場合
6 固定残業代を認めた裁判例の評価
(1)関西ソニー販売事件
(2)名鉄運輸事件
(3)ユニ・フレックス事件
(4)東和システム事件
(5)ワークフロンティア事件
(6)泉レストラン事件
(7)コロワイドMD(旧コロワイド東日本)事件
(8)結婚式場運営会社A事件
7 固定残業代の合意が無効になる場合
(1)時間外労働等に罰則付きの上限値の導入
(2)上限を超える固定残業代の契約の無効
(3)無効になる範囲
(4)無効の場合の具体的な計算方法
(5)制限値をどう考えるか
(6)三六協定未締結の場合
(7)公序良俗違反による無効
第5章 請負制(歩合給)による割増賃金の支払いの可否
第1 労基法24条との関係での請負制賃金の法的性質
1 請負制の意義
2 請負制賃金からの経費控除
第2 請負制の賃金の性質と通常の労働時間の賃金との関係
1 請負制の通常の労働時間の賃金
2 請負制の賃金該当性そのものが争点になった事例
第3 月決めの請負制の賃金全体を割増賃金とする場合
第4 月決めの出来高払制賃金の中に割合による仕切を設定する例(仕切説)
第5 通常の労働時間の賃金からの割増賃金相当額等の控除
1 割増賃金相当額の控除
(1)国際自動車事件第二次最高裁判決の要旨
(2)通常の労働時間の賃金の意義に言及がなかったことについて
(3)法37条の趣旨の実現の程度
(4)出来高制の定義がされたこととの関係での「置き換え」の意義
2 過去の平均割増賃金額の控除
3 定率・定額の控除
4 小括
第6 日決めの出来高払制等を用いて時間外労働等の時間帯のみの水揚げに対する歩合給
第7 時間決めの請負制賃金の場合
第8 まとめ
第6章 法定外の支払方法に関する学説
第1 時間賃率の未成熟
第2 固定残業代等の制度の由来
1 法定外の計算方法
2 深夜早朝割増賃金を含める所定賃金
3 日給制の手当による支払い
4 請負制の計算方法による支払い
5 狭義の固定残業代
6 狭義の固定残業代の幅広い普及経緯についての仮説
第3 必要性の乏しさ(固定残業代のメリット論批判)
1 メリットがないこと
2 使用者側から語られる社会的なメリットの検討
(1)使用者側が主張する社会的なメリット