判例による離婚原因の実務

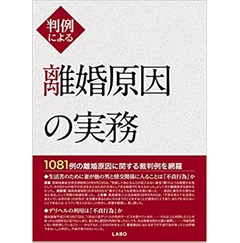
販売価格: 7,260円 税込
- 著者
- 中里和伸・著
- 発行元
- 弁護士会館ブックセンターLABO
- 発刊日
- 2021-12-20
- ISBN
- 978-4-904497-47-0
- CD-ROM
- 無し
- サイズ
- A5判 (656ページ)
1081の裁判例をもとに、民法770条1項1号から5号に規定する裁判上の離婚原因を分析。
特に有責配偶者からの離婚請求に関する最高裁昭和27年2月19日(いわゆる「踏んだり蹴ったり判決」)から、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決の分析を通じ、いわゆる苛酷状況に関する裁判例を網羅。
【目次】
第1章 我が国における離婚の方法と種類
1 総説
2 離婚手続の流れ
3 各類型についての説明
4 各類型の特色及びその整理
5 各類型の統計
6 協議離婚制度の問題点
(1) 総説
(2) 協議離婚制度の長所と短所
(3) 立法の際の議論
(4) 意思に反する離婚届の提出に対する対応
(5) 離婚無効確認請求訴訟等とその裁判例
(6) 不受理の申出
7 仮装離婚の有効性
8 離婚の効力発生時期
第2章 裁判所が示した婚姻観
1 総説
2 米倉教授の見解
3 婚姻観と離婚原因との関係
4 裁判例
第3章 離婚事由とその変遷
1 総説
2 離婚事由の意義
3 現行民法の定める離婚事由
4 明治民法における離婚事由
5 明治民法における夫と妻の離婚事由の違い
6 民法典論争
7 明治時代以前の離婚事由
(1) 総説
(2) 律令時代の離婚事由
(3) 江戸時代の庶民の離婚
第4章 離婚事由の分類-有責主義と破綻主義
1 意義
2 有責主義と破綻主義
3 具体的離婚事由(1~4号)と抽象的離婚事由(5号)
4 民法770条の適用順序
第5章 民法770条1項各号と裁判例
第1節 「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)
1 立法の経緯
2 国会における質疑
3 学者の問題意識
4 法制審議会における離婚事由の案とその当否
5 不貞行為と民法770条2項(裁量棄却)との関係
(1) 明礼議員と奥野委員との問答
(2) 榊原委員の意見
(3) 本項に関する裁判例
6 不貞行為の意味
(1) 立法の際の議論
(2) 狭義説と広義説
(3) 不貞行為の回数や期間
(4) 生活苦のために他の男と情交関係に入ることは「不貞行為」か
(5) 同性愛は「不貞行為」か
(6) デリへルの利用は「不貞行為」か
7 不貞行為の結果婚姻関係が破綻することまで必要か
8 不貞行為の行われた時期
9 宥恕
10 不貞行為の立証
11 不貞行為に基づく夫婦間の慰謝料
12 その他の裁判例
第2節 「悪意の遺棄」(2号)
1 総説
2 「悪意の遺棄」の意義
(1) 「悪意」の意義
(2) 「遺棄」の意義
(3) 「悪意の遺棄」を認めた裁判例
(4) 「悪意の遺棄」を否定した裁判例
(5) 他号との競合
第3節 「3年以上の生死不明」(3号)
1 総説
2 本号の問題点
3 本号の適否が問題となった裁判例
第4節 「回復の見込みのない強度の精神病」(4号)
1 総説
2 本号に関する国会における質疑
3 本号の問題点
4 本号の趣旨
5 「強度の精神病」の意義
6 「回復の見込みのない」の意義
7 「精神病」に限定したのはなぜか
8 本号に関する裁判例と「具体的方途論」
(1) 総説
(2) 離婚請求を肯定した裁判例
(3) 離婚請求を否定した裁判例
(4) 本号の適用関係
9 本号に基づく離婚請求訴訟の相手方
第5節 「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)
1 総説
2 立法の経緯
3 「婚姻を継続し難い重大な事由」の意義
4 「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断基準
5 「婚姻を継続し難い重大な事由」と有責性の要否
6 「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断要素
(1) 相手方も離婚を認めている場合
(2) 別居の事実
①総説、②法制審議会の法律案要綱、③離婚請求を認めた裁判例、④離婚請求を否定した裁判例
(3) 未成熟子の存在、当事者の年齢・社会的地位、離婚後の生活の不安などの事実の評価
(4) 「婚姻を継続し難い重大な事由」の原因となる行為類型等
①総説、②暴行(DV)・虐待、③暴言・精神的虐待、④嫌がらせ、⑤経済的破綻(浪費癖、勤労意欲の欠如、無為徒食)、⑥訴訟提起、強制執行、告訴・告発、⑦他方配偶者の親族との不和、⑧犯罪行為、⑨性格・価値観(人生観・生活感覚)の不一致、⑩宗教的活動、⑪性生活の不一致・異常性、⑫疾病・身体障害、⑬愛情の喪失、⑭その他、⑮まとめ
第6章 有責配偶者からの離婚請求の可否
第1節 問題の所在
第2節 裁判例の推移
1 総説
2 最高裁昭和27年2月19日(いわゆる「踏んだり蹴ったり判決」)
(1) 事案の概要
(2) 地裁・高裁の判断
(3) 最高裁の判断
(4) 最高裁の判断の問題点
(5) 読み物としても興味深い最高裁判例
3 「踏んだり蹴ったり判決」以降の裁判例
(1) 総説
(2) 6つの類型の裁判例とその内容
①Iの類型に属する裁判例、②IIの類型に属する裁判例、③IIIの類型に属する裁判例、④ IVの類型に属する裁判例、⑤ Vの類型に属する裁判例、⑥VIの類型に属する裁判例
(3) まとめ
4 最高裁大法廷昭和62年9月2日
(1) 事案の概要
(2) 下級審の判断
(3) 最高裁の判断とその要約
(4) 佐藤哲郎裁判官の「意見」とその要約
(5) 多数意見と佐藤哲郎裁判官の「意見」との対比
(6) 新聞記事
5 大法廷判決の判断の特徴と問題点
(1) 総説
(2) 有責配偶者について
(3) 長期間の別居
(4) 未成熟子の不存在
(5) いわゆる苛酷条項
(6) 苛酷条項と現実の離婚請求訴訟実務における原告及び被告にとっての悩み
(7) 角田禮次郎裁判官、林藤之輔裁判官の補足意見とその当否
①補足意見の内容、②補足意見の長所とその見解を採用する裁判例、3③義務者からの財産分与申立を認めないとする裁判例、④検討、⑤この論点と佐藤哲郎裁判官の「意見」との関係
6 その後の裁判例とその特徴
7 各裁判例における問題点
(1) 未成熟子の存在とその福祉という視点
(2) 妻が有責配偶者の場合
(3) 有責配偶者か否かが争われる場合 ①問題の所在、②原告側の3種類の主張(反論)、③各類型ごとの裁判例
(4) 異例と思われる裁判例
(5) 大法廷判決の規範(信義則)を類推適用した裁判例
(6) 有責配偶者からの離婚請求が認められるためには別居期間は何年必要か
①総説、②別居期間が約8年の最高裁判決の対比、③別居期間約6年の裁判例、④短期の別居期間で離婚請求が認められたその後の裁判例、⑤今後の裁判例について及び筆者の考え方について