任意後見の実務 フローチャートとポイント

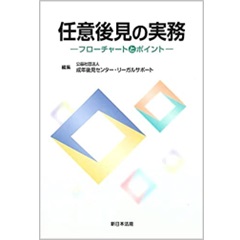
販売価格: 4,290円 税込
- 著者
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート・編
- 発行元
- 新日本法規
- 発刊日
- 2022-07-22
- ISBN
- 978-4-7882-9061-7
- CD-ROM
- 無し
- サイズ
- B5判 (270ページ)
本人の希望・状況への対応を手際よく実行するために!
◆相談・受任から契約の締結、就任後の事務手続、契約の終了まで、実務処理の手順に沿ってわかりやすく解説しています。
◆契約手続や任意後見事務の流れをフローチャートで示し、実務上の疑問点や留意点等を解説しています。
◆任意後見監督人の事務についても言及しています。
目次
第1編 制度の概要
第1章 成年後見制度の全体像
第1 制度の基本理念を理解する
第2 制度の守備範囲を確認する
第3 制度の仕組みを把握する
第4 成年後見制度の特徴を把握する
第5 制度に対する誤解を確認する
第6 能力概念の異同を理解する
第7 判断能力が不十分な状況での任意後見契約締結(即効型任意後見)の問題点に留意する
第2章 任意後見制度の位置付け
第1 成年後見制度利用促進基本計画における任意後見制度の位置付けを理解する
第2 権利擁護支援の地域連携ネットワークの本質を理解する
第3 代理意思決定と意思決定支援の異同を理解する
第4 任意後見優先の原則を確認する
第5 任意後見と任意代理との異同を理解する
第6 任意後見と法定後見の異同を理解する
第7 任意後見における同意権の設定と取消権の代理行使を理解する
第8 任意後見契約締結に際して事前指示書等を活用する
【参考書式1】事前指示書(ライフプラン)
第2編 契約手続
第1章 相談・受任
第1 相談・方針を決定する
<フローチャート~相談・方針の決定>
1 相談を受ける
(1) 本人からの相談~現在の生活環境と将来への不安や思いを聞き取る
(2) 本人以外からの相談~本人との関係を中心に聞き取る
2 成年後見制度に関する説明と検討
(1) 任意後見制度
(2) 法定後見制度
(3) その他の制度
3 本人からの詳細な情報の聞き取りと方針決定
(1) 本人から詳細な情報を聞き取る
(2) 任意後見制度の利用を決定する
第2 本人のニーズに合わせた任意後見契約を検討する
<フローチャート~本人のニーズの確認>
1 任意後見契約の三つの形態
(1) 「将来型」任意後見契約
(2) 「移行型」任意後見契約
(3) 「即効型」任意後見契約
(4) 問題点
2 任意後見契約を補完する契約
(1) 発効前のサポート(①継続的見守り契約、②財産管理等委任契約)
(2) 死後のサポート(死後事務委任契約)
(3) その他(死因贈与契約、遺言)
第3 受任者を検討する
<フローチャート~任意後見受任者の決定>
1 受任者の候補がいる場合
(1) 親族等が受任者となる
(2) 親族等と複数で受任者となる
2 受任者の候補がいない場合
(1) 受任者の候補を提案する
(2) 複数の受任者を検討する
第2章 任意後見契約の締結
第1 任意後見契約の締結を準備する
<フローチャート~任意後見契約の締結までの流れ>
1 任意後見契約の締結に向けた準備
(1) 任意後見契約と補完する契約の関係
(2) 重要事項の説明
(3) 契約締結における費用の説明
2 契約の方式に注意する
【参考書式2】重要事項説明書
第2 契約書を作成する
<フローチャート~任意後見契約と補完する契約の検討>
1 任意後見契約
2 代理権目録
(1) 単独代理
(2) 複数代理
(3) 予備的受任者の定め
3 ライフプラン
(1) ライフプランの目的
(2) ライフプランの内容
4 継続的見守り契約
5 財産管理等委任契約
6 死後事務委任契約
第3 公正証書の作成と契約締結を行う
<フローチャート~公正証書の作成と契約締結、登記事項証明書の取得>
1 公証役場との事前打合せと準備書類
(1) 公証役場との事前打合せ
(2) 契約書案の提示
(3) 準備書類
(4) 契約日に必要な書類等の準備・確認
2 任意後見契約の締結
(1) 契約日における注意
3 任意後見登記と登記事項証明書の取得
(1) 任意後見登記事項証明書の記載事項
(2) 登記事項証明書の取得
第3章 任意後見契約発効前の事務
第1 任意後見契約の発効前にすることを確認する
<フローチャート~任意後見契約の発効前にすること>
1 委任者との信頼関係の構築
(1) 連絡を途切れさせない
(2) 年1回は面会する
(3) 緊急時の連絡先になる
(4) ライフプランを更新する
(5) 臨時的に委任者から委任を受けて特定の法律行為を代理する
(6) 委任者が75歳になったら、見守り契約を勧める
(7) 継続的な財産管理を委任されている場合は契約どおりに行う
2 委任者の事理弁識能力の低下を把握する工夫
(1) 親 族
(2) 地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、市区町村、中核機関、社会福祉協議会等
(3) 介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、かかりつけ医療機関
(4) 民生委員、近隣住民、友人
(5) 金融機関
(6) 委任者について情報を共有する
第2 任意後見契約等のプラン変更の要否を検討する
<フローチャート~任意後見契約等のプランの変更・解除>
1 付随する契約の追加・変更
(1) 見守り契約の追加・変更
(2) 財産管理等委任契約の追加・変更
(3) 死後事務委任契約の追加・変更
2 任意後見契約の再契約・変更
(1) 代理権を行うべき事務の範囲又は行使方法(委任者、任意後見監督人又は第三者の同意の要否等)を変更する場合
(2) 受任者を追加する場合
(3) 受任者を減少させる場合
(4) 任意後見人の報酬の金額等を変更する場合
3 任意後見契約の解除
(1) 任意後見契約発効前の合意解除
(2) 任意後見契約発効前の一方からの解除及び相手方への通知による解除
第4章 任意後見契約の発効
第1 任意後見契約を発効させるべきか確認する
<フローチャート~任意後見契約の発効の要否の確認>
1 事理弁識能力の確認
(1) 本人情報シートの活用
(2) 医師による診断
(3) 本人の同意の有無
2 任意後見契約を発効させる
(1) 事理弁識能力が不十分である
(2) 本人の同意がある
3 任意後見契約の発効を見送る
(1) 事理弁識能力が不十分ではない
(2) 本人の同意がない
4 法定後見制度の利用を検討する
(1) 任意後見契約の内容では本人の支援が不十分の可能性があるとき
(2) 本人の同意は得られないが支援が必要なとき
(3) 受任者に不適切な事由があるとき
(4) 本人が既に法定後見を利用していて、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要であると認める可能性があるとき
5 法定後見制度を利用する
(1) 委任者又は受任者が未成年であるとき
第2 任意後見監督人選任の審判を申し立てる
<フローチャート~任意後見監督人選任の審判の申立て>
1 申立ての準備
(1) 申立ての時期
(2) 申立権者
(3) 申立書の作成と添付書類等の収集
2 管轄裁判所・申立書の提出
(1) 委任者が日本国籍の場合
(2) 委任者が在日外国人の場合
3 審理手続
(1) 委任者(本人)との面談
(2) 任意後見監督人となるべき者の意見聴取
(3) 受任者の意見聴取
(4) 鑑 定
(5) 親族への意向照会
(6) 申立ての取下げの制限
4 任意後見監督人選任の審判
(1) 任意後見監督人の欠格事由
(2) 任意後見契約の発効時期
(3) 受任者の関係者が任意後見監督人に選任されることの賛否
5 申立費用の負担
(1) 申立費用の内訳
(2) 申立費用を負担するのは誰か
第3編 任意後見事務
第1章 就任直後の事務
第1 任意後見登記事項証明書を取得する
<フローチャート~任意後見登記事項証明書の取得>
1 任意後見監督人選任審判の確定
2 管轄家庭裁判所から東京法務局への嘱託登記
3 法務局に対しての証明書の取得のための申請
(1) 郵便による方法で申請する場合
(2) 窓口で申請する場合
(3) オンラインで申請する場合
4 任意後見登記事項証明書の取得
5 代理権目録の確認
6 代理権を行使する相手方への提示・説明
【参考書式3】任意後見登記事項証明書
第2 任意後見監督人との打合せを行う
<フローチャート~任意後見監督
◆相談・受任から契約の締結、就任後の事務手続、契約の終了まで、実務処理の手順に沿ってわかりやすく解説しています。
◆契約手続や任意後見事務の流れをフローチャートで示し、実務上の疑問点や留意点等を解説しています。
◆任意後見監督人の事務についても言及しています。
目次
第1編 制度の概要
第1章 成年後見制度の全体像
第1 制度の基本理念を理解する
第2 制度の守備範囲を確認する
第3 制度の仕組みを把握する
第4 成年後見制度の特徴を把握する
第5 制度に対する誤解を確認する
第6 能力概念の異同を理解する
第7 判断能力が不十分な状況での任意後見契約締結(即効型任意後見)の問題点に留意する
第2章 任意後見制度の位置付け
第1 成年後見制度利用促進基本計画における任意後見制度の位置付けを理解する
第2 権利擁護支援の地域連携ネットワークの本質を理解する
第3 代理意思決定と意思決定支援の異同を理解する
第4 任意後見優先の原則を確認する
第5 任意後見と任意代理との異同を理解する
第6 任意後見と法定後見の異同を理解する
第7 任意後見における同意権の設定と取消権の代理行使を理解する
第8 任意後見契約締結に際して事前指示書等を活用する
【参考書式1】事前指示書(ライフプラン)
第2編 契約手続
第1章 相談・受任
第1 相談・方針を決定する
<フローチャート~相談・方針の決定>
1 相談を受ける
(1) 本人からの相談~現在の生活環境と将来への不安や思いを聞き取る
(2) 本人以外からの相談~本人との関係を中心に聞き取る
2 成年後見制度に関する説明と検討
(1) 任意後見制度
(2) 法定後見制度
(3) その他の制度
3 本人からの詳細な情報の聞き取りと方針決定
(1) 本人から詳細な情報を聞き取る
(2) 任意後見制度の利用を決定する
第2 本人のニーズに合わせた任意後見契約を検討する
<フローチャート~本人のニーズの確認>
1 任意後見契約の三つの形態
(1) 「将来型」任意後見契約
(2) 「移行型」任意後見契約
(3) 「即効型」任意後見契約
(4) 問題点
2 任意後見契約を補完する契約
(1) 発効前のサポート(①継続的見守り契約、②財産管理等委任契約)
(2) 死後のサポート(死後事務委任契約)
(3) その他(死因贈与契約、遺言)
第3 受任者を検討する
<フローチャート~任意後見受任者の決定>
1 受任者の候補がいる場合
(1) 親族等が受任者となる
(2) 親族等と複数で受任者となる
2 受任者の候補がいない場合
(1) 受任者の候補を提案する
(2) 複数の受任者を検討する
第2章 任意後見契約の締結
第1 任意後見契約の締結を準備する
<フローチャート~任意後見契約の締結までの流れ>
1 任意後見契約の締結に向けた準備
(1) 任意後見契約と補完する契約の関係
(2) 重要事項の説明
(3) 契約締結における費用の説明
2 契約の方式に注意する
【参考書式2】重要事項説明書
第2 契約書を作成する
<フローチャート~任意後見契約と補完する契約の検討>
1 任意後見契約
2 代理権目録
(1) 単独代理
(2) 複数代理
(3) 予備的受任者の定め
3 ライフプラン
(1) ライフプランの目的
(2) ライフプランの内容
4 継続的見守り契約
5 財産管理等委任契約
6 死後事務委任契約
第3 公正証書の作成と契約締結を行う
<フローチャート~公正証書の作成と契約締結、登記事項証明書の取得>
1 公証役場との事前打合せと準備書類
(1) 公証役場との事前打合せ
(2) 契約書案の提示
(3) 準備書類
(4) 契約日に必要な書類等の準備・確認
2 任意後見契約の締結
(1) 契約日における注意
3 任意後見登記と登記事項証明書の取得
(1) 任意後見登記事項証明書の記載事項
(2) 登記事項証明書の取得
第3章 任意後見契約発効前の事務
第1 任意後見契約の発効前にすることを確認する
<フローチャート~任意後見契約の発効前にすること>
1 委任者との信頼関係の構築
(1) 連絡を途切れさせない
(2) 年1回は面会する
(3) 緊急時の連絡先になる
(4) ライフプランを更新する
(5) 臨時的に委任者から委任を受けて特定の法律行為を代理する
(6) 委任者が75歳になったら、見守り契約を勧める
(7) 継続的な財産管理を委任されている場合は契約どおりに行う
2 委任者の事理弁識能力の低下を把握する工夫
(1) 親 族
(2) 地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、市区町村、中核機関、社会福祉協議会等
(3) 介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、かかりつけ医療機関
(4) 民生委員、近隣住民、友人
(5) 金融機関
(6) 委任者について情報を共有する
第2 任意後見契約等のプラン変更の要否を検討する
<フローチャート~任意後見契約等のプランの変更・解除>
1 付随する契約の追加・変更
(1) 見守り契約の追加・変更
(2) 財産管理等委任契約の追加・変更
(3) 死後事務委任契約の追加・変更
2 任意後見契約の再契約・変更
(1) 代理権を行うべき事務の範囲又は行使方法(委任者、任意後見監督人又は第三者の同意の要否等)を変更する場合
(2) 受任者を追加する場合
(3) 受任者を減少させる場合
(4) 任意後見人の報酬の金額等を変更する場合
3 任意後見契約の解除
(1) 任意後見契約発効前の合意解除
(2) 任意後見契約発効前の一方からの解除及び相手方への通知による解除
第4章 任意後見契約の発効
第1 任意後見契約を発効させるべきか確認する
<フローチャート~任意後見契約の発効の要否の確認>
1 事理弁識能力の確認
(1) 本人情報シートの活用
(2) 医師による診断
(3) 本人の同意の有無
2 任意後見契約を発効させる
(1) 事理弁識能力が不十分である
(2) 本人の同意がある
3 任意後見契約の発効を見送る
(1) 事理弁識能力が不十分ではない
(2) 本人の同意がない
4 法定後見制度の利用を検討する
(1) 任意後見契約の内容では本人の支援が不十分の可能性があるとき
(2) 本人の同意は得られないが支援が必要なとき
(3) 受任者に不適切な事由があるとき
(4) 本人が既に法定後見を利用していて、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要であると認める可能性があるとき
5 法定後見制度を利用する
(1) 委任者又は受任者が未成年であるとき
第2 任意後見監督人選任の審判を申し立てる
<フローチャート~任意後見監督人選任の審判の申立て>
1 申立ての準備
(1) 申立ての時期
(2) 申立権者
(3) 申立書の作成と添付書類等の収集
2 管轄裁判所・申立書の提出
(1) 委任者が日本国籍の場合
(2) 委任者が在日外国人の場合
3 審理手続
(1) 委任者(本人)との面談
(2) 任意後見監督人となるべき者の意見聴取
(3) 受任者の意見聴取
(4) 鑑 定
(5) 親族への意向照会
(6) 申立ての取下げの制限
4 任意後見監督人選任の審判
(1) 任意後見監督人の欠格事由
(2) 任意後見契約の発効時期
(3) 受任者の関係者が任意後見監督人に選任されることの賛否
5 申立費用の負担
(1) 申立費用の内訳
(2) 申立費用を負担するのは誰か
第3編 任意後見事務
第1章 就任直後の事務
第1 任意後見登記事項証明書を取得する
<フローチャート~任意後見登記事項証明書の取得>
1 任意後見監督人選任審判の確定
2 管轄家庭裁判所から東京法務局への嘱託登記
3 法務局に対しての証明書の取得のための申請
(1) 郵便による方法で申請する場合
(2) 窓口で申請する場合
(3) オンラインで申請する場合
4 任意後見登記事項証明書の取得
5 代理権目録の確認
6 代理権を行使する相手方への提示・説明
【参考書式3】任意後見登記事項証明書
第2 任意後見監督人との打合せを行う
<フローチャート~任意後見監督