交通事故事件の実務-裁判官の視点-(改訂版)

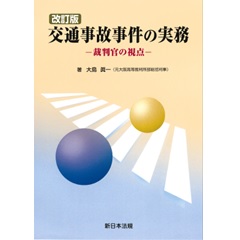
販売価格: 4,070円 税込
法曹関係者必携の決定版!
◆裁判官としての永年の経験から得た知見に基づき、実務上の論点や訴訟手続上の留意点をまとめ、余すことなく開示しています。
◆訴訟遂行の参考となる最高裁判例及び近時の下級審裁判例を取り上げ、最新の裁判事情を踏まえて解説しています。
目次
第1章 交通事故訴訟の特徴
1 立証責任の転換
2 保険制度の充実
3 過失相殺率と損害賠償額の基準化
第2章 責任(総論)
1 損害賠償請求の根拠規定
(1) 民法に基づく請求
(2) 自賠法3条に基づく請求
(3) 民法709条と自賠法3条の関係
2 請求する相手方
3 訴訟物
(1) 人的損害
(2) 物的損害
4 過 失
(1) 過失の意義
(2) 過失の主要事実
第3章 自賠法3条に関する問題
1 運行供用者
(1) 自動車の貸与者
ア レンタカー業者
イ リース会社
ウ 割賦販売における留保所有権者
エ 使用貸借における貸主
(2) 名義貸与者
(3) 泥棒運転
(4) 代行運転
(5) 運送業者
(6) 自動車修理業者
(7) 元請人
(8) 従業員による事故
ア 従業員による自己所有の自動車の事故
イ 従業員による使用者所有の自動車による事故
(9) 使用を容認されていた者の友人が起こした事故
2 運 行
(1) 牽引中の車両の事故
(2) クレーン車のクレーン作業中の事故
(3) 構内自動車による事故
(4) 駐停車中の車両による事故
(5) 非接触事故
3 運行起因性
(1) 荷積み・荷降ろし作業中の事故
(2) 近時の裁判例の動向
4 他人性
(1) 配偶者・好意(無償)同乗者
(2) 運転補助者
(3) 共同運行供用者
ア 非同乗型
イ 同乗型
ウ 混合型
5 免 責
第4章 責任能力
1 未成年者の責任能力
2 親権者の責任
3 監督義務者の責任
(1) 自賠法3条による責任
(2) 民法709条による責任
4 精神上の障害により責任弁識能力を欠く状態にある者の責任能力
(1) 運転者が疾患の影響で運転中に意識を失って人身事故を起こした場合
(2) 運転者が疾患の影響で運転中に意識を失って物損事故を起こした場合
5 認知症患者の介護者の監督義務者責任
第5章 共同不法行為
1 総 論
2 異時交通事故
3 交通事故と医療事故の競合
4 交通事故と道路の瑕疵
5 運転前に飲酒を勧めた者の責任
(1) 同乗型の飲酒運転関与者
(2) 非同乗型の飲酒運転関与者
6 被害者にも過失がある場合の過失相殺
7 共同不法行為者が損害額の一部を支払った場合の被害者の請求権
8 第三者又は被用者の使用者に対する求償
(1) 第三者の使用者に対する求償
(2) 被用者の使用者に対する求償
第6章 損害(一般)
1 損害額算定の基準
2 3庁共同提言
3 損害の内訳
4 人的損害
5 定期金賠償
(1) 全 般
(2) 後遺障害逸失利益
(3) 将来の介護費
第7章 積極損害
1 治療関係費
2 入院雑費
3 交通費
4 付添看護費
5 将来の介護費
6 装具・器具購入費等
7 家屋改造費等
8 葬儀関係費
9 その他の積極損害
第8章 消極損害
1 休業損害
(1) 基礎収入
ア 給与所得者
イ 事業所得者
ウ 会社役員
エ 家事従事者
オ 無職者(エの者を除く)
(2) 休業期間
2 後遺障害による逸失利益
(1) 基礎収入
ア 給与所得者
イ 事業所得者
ウ 家事従事者
エ 幼児、生徒、学生
オ 無職者(ウ及びエの者を除く)
カ 年少女子
キ 企業損害(間接損害)
(2) 労働能力喪失率
(3) 労働能力喪失期間
(4) 中間利息の控除
(5) 重度後遺障害(遷延性意識障害)
(6) 中間利息控除の基準時
(7) 後遺障害の類型
ア 外貌醜状
イ PTSD(心的外傷後ストレス障害)
ウ RSD、CRPS(反射性交感神経性ジストロフィー)
エ 高次脳機能障害
オ 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
3 死亡による逸失利益
(1) 生活費控除
(2) 年金の逸失利益性
ア 年金受給者の逸失利益性
イ 年金未受給者の逸失利益性
(3) 相続人以外の者の扶養利益の喪失
(4) 外国人
第9章 精神的損害(慰謝料)
1 死亡慰謝料
2 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
3 後遺障害慰謝料
4 一身専属性
5 近親者慰謝料
6 外国人
第10章 物的損害
1 車両修理費等
(1) 修理が可能な場合
(2) 修理が不可能な場合
2 代車使用料
3 休車損害
4 評価損
5 所有権留保、リース車両
(1) 所有権留保特約付の場合
(2) リース契約の場合
6 慰謝料
第11章 弁護士費用・遅延損害金
1 弁護士費用
2 遅延損害金
(1) 基 本
(2) 自賠法16条
(3) 労災保険等
(4) 求償金
(5) 遅延損害金の元本組入れ
第12章 過失相殺・素因減額
1 過失相殺
(1) 基 準
(2) 被害者の過失相殺能力
(3) 被害者側の過失
(4) 好意(無償)同乗
(5) シートベルト不装着
(6) 一部請求と過失相殺
2 素因減額
第13章 事故後の事情変更
1 逸失利益と事故と無関係な後発的事情による死亡
2 介護費用と口頭弁論終結前の死亡
3 交通事故後の被害者の自殺
4 後遺障害が口頭弁論終結後に発生した場合
第14章 損益相殺
1 控除の対象となる給付
(1) 自賠責保険金(自賠法16条)
(2) 政府の自動車損害賠償保障事業塡補金(自賠法72条)
(3) 任意保険金
(4) 各種社会保険給付
ア 労働者災害補償保険(労災保険)
イ 公的年金
ウ 健康保険法等における療養の給付
エ 介護保険金
オ 生活保護法による給付
カ 障害者総合支援法等
キ 独立行政法人自動車事故対策機構(旧自動車事故対策センター)による介護料
ク 後期高齢者医療給付
(5) 各種保険金
ア 損害保険金
イ 生命保険金・傷害保険金
ウ 搭乗者傷害保険金
エ 所得補償保険金
(6) その他
ア 香 典
イ 見舞金
ウ 租 税
エ 養育費
2 控除の時的範囲
(1) 被害者が加害者に対して請求する場合
(2) 政府の自動車損害賠償保障事業塡補金の場合
3 控除の主観的範囲
4 損益相殺と過失相殺との先後関係
(1) 自賠責保険金・政府の自動車損害賠償保障事業塡補金・任意保険金
(2) 労災保険金
(3) 健康保険法等による給付
(4) 国民年金・厚生年金
第15章 消滅時効・その他
1 消滅時効
(1) 後遺障害事案の時効の起算点
(2) 時効の完成猶予と更新
ア 完成猶予事由
イ 更新事由
(3) 協議を行う旨の合意による時効の
◆裁判官としての永年の経験から得た知見に基づき、実務上の論点や訴訟手続上の留意点をまとめ、余すことなく開示しています。
◆訴訟遂行の参考となる最高裁判例及び近時の下級審裁判例を取り上げ、最新の裁判事情を踏まえて解説しています。
目次
第1章 交通事故訴訟の特徴
1 立証責任の転換
2 保険制度の充実
3 過失相殺率と損害賠償額の基準化
第2章 責任(総論)
1 損害賠償請求の根拠規定
(1) 民法に基づく請求
(2) 自賠法3条に基づく請求
(3) 民法709条と自賠法3条の関係
2 請求する相手方
3 訴訟物
(1) 人的損害
(2) 物的損害
4 過 失
(1) 過失の意義
(2) 過失の主要事実
第3章 自賠法3条に関する問題
1 運行供用者
(1) 自動車の貸与者
ア レンタカー業者
イ リース会社
ウ 割賦販売における留保所有権者
エ 使用貸借における貸主
(2) 名義貸与者
(3) 泥棒運転
(4) 代行運転
(5) 運送業者
(6) 自動車修理業者
(7) 元請人
(8) 従業員による事故
ア 従業員による自己所有の自動車の事故
イ 従業員による使用者所有の自動車による事故
(9) 使用を容認されていた者の友人が起こした事故
2 運 行
(1) 牽引中の車両の事故
(2) クレーン車のクレーン作業中の事故
(3) 構内自動車による事故
(4) 駐停車中の車両による事故
(5) 非接触事故
3 運行起因性
(1) 荷積み・荷降ろし作業中の事故
(2) 近時の裁判例の動向
4 他人性
(1) 配偶者・好意(無償)同乗者
(2) 運転補助者
(3) 共同運行供用者
ア 非同乗型
イ 同乗型
ウ 混合型
5 免 責
第4章 責任能力
1 未成年者の責任能力
2 親権者の責任
3 監督義務者の責任
(1) 自賠法3条による責任
(2) 民法709条による責任
4 精神上の障害により責任弁識能力を欠く状態にある者の責任能力
(1) 運転者が疾患の影響で運転中に意識を失って人身事故を起こした場合
(2) 運転者が疾患の影響で運転中に意識を失って物損事故を起こした場合
5 認知症患者の介護者の監督義務者責任
第5章 共同不法行為
1 総 論
2 異時交通事故
3 交通事故と医療事故の競合
4 交通事故と道路の瑕疵
5 運転前に飲酒を勧めた者の責任
(1) 同乗型の飲酒運転関与者
(2) 非同乗型の飲酒運転関与者
6 被害者にも過失がある場合の過失相殺
7 共同不法行為者が損害額の一部を支払った場合の被害者の請求権
8 第三者又は被用者の使用者に対する求償
(1) 第三者の使用者に対する求償
(2) 被用者の使用者に対する求償
第6章 損害(一般)
1 損害額算定の基準
2 3庁共同提言
3 損害の内訳
4 人的損害
5 定期金賠償
(1) 全 般
(2) 後遺障害逸失利益
(3) 将来の介護費
第7章 積極損害
1 治療関係費
2 入院雑費
3 交通費
4 付添看護費
5 将来の介護費
6 装具・器具購入費等
7 家屋改造費等
8 葬儀関係費
9 その他の積極損害
第8章 消極損害
1 休業損害
(1) 基礎収入
ア 給与所得者
イ 事業所得者
ウ 会社役員
エ 家事従事者
オ 無職者(エの者を除く)
(2) 休業期間
2 後遺障害による逸失利益
(1) 基礎収入
ア 給与所得者
イ 事業所得者
ウ 家事従事者
エ 幼児、生徒、学生
オ 無職者(ウ及びエの者を除く)
カ 年少女子
キ 企業損害(間接損害)
(2) 労働能力喪失率
(3) 労働能力喪失期間
(4) 中間利息の控除
(5) 重度後遺障害(遷延性意識障害)
(6) 中間利息控除の基準時
(7) 後遺障害の類型
ア 外貌醜状
イ PTSD(心的外傷後ストレス障害)
ウ RSD、CRPS(反射性交感神経性ジストロフィー)
エ 高次脳機能障害
オ 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
3 死亡による逸失利益
(1) 生活費控除
(2) 年金の逸失利益性
ア 年金受給者の逸失利益性
イ 年金未受給者の逸失利益性
(3) 相続人以外の者の扶養利益の喪失
(4) 外国人
第9章 精神的損害(慰謝料)
1 死亡慰謝料
2 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
3 後遺障害慰謝料
4 一身専属性
5 近親者慰謝料
6 外国人
第10章 物的損害
1 車両修理費等
(1) 修理が可能な場合
(2) 修理が不可能な場合
2 代車使用料
3 休車損害
4 評価損
5 所有権留保、リース車両
(1) 所有権留保特約付の場合
(2) リース契約の場合
6 慰謝料
第11章 弁護士費用・遅延損害金
1 弁護士費用
2 遅延損害金
(1) 基 本
(2) 自賠法16条
(3) 労災保険等
(4) 求償金
(5) 遅延損害金の元本組入れ
第12章 過失相殺・素因減額
1 過失相殺
(1) 基 準
(2) 被害者の過失相殺能力
(3) 被害者側の過失
(4) 好意(無償)同乗
(5) シートベルト不装着
(6) 一部請求と過失相殺
2 素因減額
第13章 事故後の事情変更
1 逸失利益と事故と無関係な後発的事情による死亡
2 介護費用と口頭弁論終結前の死亡
3 交通事故後の被害者の自殺
4 後遺障害が口頭弁論終結後に発生した場合
第14章 損益相殺
1 控除の対象となる給付
(1) 自賠責保険金(自賠法16条)
(2) 政府の自動車損害賠償保障事業塡補金(自賠法72条)
(3) 任意保険金
(4) 各種社会保険給付
ア 労働者災害補償保険(労災保険)
イ 公的年金
ウ 健康保険法等における療養の給付
エ 介護保険金
オ 生活保護法による給付
カ 障害者総合支援法等
キ 独立行政法人自動車事故対策機構(旧自動車事故対策センター)による介護料
ク 後期高齢者医療給付
(5) 各種保険金
ア 損害保険金
イ 生命保険金・傷害保険金
ウ 搭乗者傷害保険金
エ 所得補償保険金
(6) その他
ア 香 典
イ 見舞金
ウ 租 税
エ 養育費
2 控除の時的範囲
(1) 被害者が加害者に対して請求する場合
(2) 政府の自動車損害賠償保障事業塡補金の場合
3 控除の主観的範囲
4 損益相殺と過失相殺との先後関係
(1) 自賠責保険金・政府の自動車損害賠償保障事業塡補金・任意保険金
(2) 労災保険金
(3) 健康保険法等による給付
(4) 国民年金・厚生年金
第15章 消滅時効・その他
1 消滅時効
(1) 後遺障害事案の時効の起算点
(2) 時効の完成猶予と更新
ア 完成猶予事由
イ 更新事由
(3) 協議を行う旨の合意による時効の