弁護士・臨床心理士の両視点にみる面会交流 当事者心理と実務のポイント

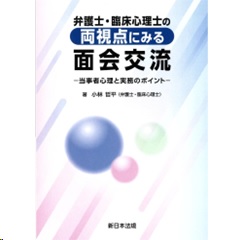
販売価格: 5,060円 税込
【法律×心理】で導く面会交流
⚫︎当事者にとって最良の面会交流が実現できるように、臨床心理士の資格を持つ弁護士が、「法律実務と心理学との融合」をコンセプトに執筆しています。
⚫︎本文の要所には「▶臨床心理士の視点」として、心理学的な視点が特に重要となるポイントを提示しています。
⚫︎実務ですぐに使える条項例及び近時の重要裁判例を数多く紹介しています。
掲載内容
第1章 面会交流に関する基本事項
1 面会交流の意義・目的〜面会交流のメリットは何か〜
(1)「メリット」という視点
(2)子どもにとっての面会交流の意義(メリット)
(3)親にとっての面会交流の意義(メリット)
2 面会交流の頻度〜面会交流の頻度はどの程度が一般的か〜
(1)全国ひとり親世帯の調査結果
(2)司法統計の結果
(3)頻度に関する実務上の考え方
3 面会交流の実施時間〜面会交流の実施時間はどの程度が一般的か〜
(1)子どもを対象にした全国調査の結果
(2)同居親(母親)を対象にした調査の結果
(3)実施時間に関する実務上の考え方
4 面会交流が問題となる子どもの年齢 〜面会交流が問題となるのは小学生までか〜
(1)司法統計の数値
(2)中学生以降の面会交流
第2章 禁止・制限事由
1 連れ去りのおそれ
(1)子どもの連れ去りのおそれがある場合の面会交流
(2)禁止・制限の判断基準
(3)連れ去りの具体的可能性がないのに、同居親の不安感が強い場合
(4)連れ去りのおそれを指摘された別居親にできること
2 子どもの虐待
(1)禁止・制限の判断基準
(2)虐待が子どもの心身に与える影響
(3)子どもが事実と異なる虐待の訴えをする可能性
3 同居親に対する暴力
(1)同居親に対する暴力の禁止・制限事由該当性
(2)禁止・制限の判断基準
(3)保護命令が発令されている場合
(4)子どもの面前での暴力が子どもの心身に与える影響
4 子どもの拒否
(1)禁止・制限の判断基準
(2)子どもの拒絶の背景に同居親の態度や行動がある場合
5 当事者間の高葛藤
(1)当然といえる感情対立
(2)高葛藤とは
(3)高葛藤事案の特徴 〜葛藤の程度の類型化〜
(4)弁護士の留意点 〜監護者指定等の申立てをすべきか〜
(5)禁止・制限の判断基準
6 当事者の再婚
(1)禁止・制限の判断基準
(2)親の再婚時の子どもの心理
(3)同居親の心理
(4)別居親の心理
7 婚姻費用・養育費の不払
(1)禁止・制限の判断基準
(2)本音と建前〜衡平理論による当事者心理の説明〜
(3)面会交流は婚姻費用・養育費の支払を促進するか
8 別居親の精神疾患・精神不安
(1)別居親が精神的に不安定な状態になる場合
(2)精神疾患になる割合
(3)禁止・制限の判断基準
(4)早期治療のすすめ
9 同居親の精神疾患・精神不安
(1)同居親が精神的に不安定な状態になる場合
(2)禁止・制限の判断基準
10 別居親の不貞行為
(1)不貞行為をされた同居親及び子どもの心理
(2)禁止・制限の判断基準
11 ルール不遵守
(1)面会交流に関する様々なルール
(2)時間や頻度を守らない場合
(3)子どもの引渡し時の同居親に対する非難等
(4)同居親や子どもの住所等を知ろうとする行為
第3章 協議・法的手続の重要ポイント
1 面会交流事件の解決までの期間
(1)面会交流事件は長期化しやすい事件類型
(2)解決期間に関する統計上の数値
(3)長期化する事案の傾向
2 手続選択の目安〜協議から始めるか、調停から始めるか〜
(1)協議スタートと調停スタート
(2)協議と調停のメリット、デメリット・リスク
(3)調停の方が、話がまとまりやすい場合
3 面会交流調停申立ての要否〜離婚調停が係属している場合でも別途面会交流調停を申し立てた方がよいか〜
(1)離婚調停における面会交流の取扱い
(2)面会交流調停の申立てを行う場合
4 当事者本人が調停に参加することの意義
(1)当事者欠席による調停の形骸化・長期化のおそれ
(2)当事者欠席によって相手方が不信感を抱くおそれ
(3)当事者が主体的に参加することによる納得感の向上
(4)依頼者と弁護士の関係性の向上
(5)弁護士から依頼者への説明の重要性
5 調査官調査
(1)調査官調査とは
(2)調査官調査で聞かれること
(3)調査官調査の際の注意点
6 子どもの調査
(1)子どもの調査が行われる場合
(2)子どもの調査の方法
(3)子どもの調査前後の注意点
7 試行的面会交流
(1)試行的面会交流とは
(2)試行的面会交流が実施される場合とその目的
(3)試行的面会交流の実施方法
(4)試行的面会交流前及び当日の注意点
(5)試行的面会交流後の注意点
8 面会交流調停の不成立〜調停を成立させるか、不成立にして審判手続に移行させるか〜
(1)面会交流調停が不成立になる場合
(2)調停を成立させるか審判手続に移行させるべきかの判断基準
9 審判手続
(1)調停不成立後の手続
(2)調停段階で出された書面などの取扱い
(3)審判手続の概要 〜審理の方法〜
(4)審判期日と審問期日の用語の異同
(5)審判期日(審問期日)の際の注意点
(6)審理終結及び審判
(7)審判の確定(審判の効力発生)
10 即時抗告
(1)即時抗告の期間制限
(2)抗告状の提出先
(3)抗告状の内容
【書式例】抗告状
(4)抗告理由書の提出期限
(5)即時抗告の効果
(6)不利益変更禁止の原則の有無 〜即時抗告のリスク〜
(7)附帯抗告という制度の有無
11 抗告審の流れ
(1)書面審理が中心
(2)家裁調査官の関与
(3)抗告審における調停
(4)抗告審の裁判の方式
(5)原審判が取消し・変更となる割合
(6)抗告審における弁護士の留意点
12 特別抗告・許可抗告
(1)特別抗告・許可抗告の要件
(2)期間制限
(3)特別抗告提起、許可抗告申立ての効果
(4)面会交流事件における特別抗告、許可抗告の実際
13 離婚訴訟における面会交流
(1)附帯処分の申立てを行う方法
(2)訴訟上の和解において面会交流を取り決める方法
14 審判前の保全処分
15 面会交流不履行の場合の法的手続
(1)面会交流が実施できなくなるのはどのような場合か
(2)履行勧告の申出
(3)間接強制
(4)損害賠償請求
(5)再調停
(6)親権者又は監護者の指定・変更
【書式例】間接強制申立書
16 同居親の不出頭〜同居親が法的手続に参加・協力しない場合〜
第4章 面会交流の内容
1 面会交流の内容を考える際のポイント
(1)五つの必須検討事項
(2)面会交流を考える上で重要なマインド
2 期日間の面会交流〜合意するまでの間に暫定的に面会交流を実施する際に押さえるべきポイント〜
(1)合意前に面会交流を実施するメリット
(2)合意前の面会交流の実施方法
(3)合意前の面会交流実施に当たっての注意点
3 子どもの年齢別・面会交流の注意点
(1)子どもの発達段階の特徴と両親の別居や紛争に対する反応
(2)乳幼児期の面会交流
(3)小学生の面会交流
(4)中学生(小学校高学年)以降の面会交流
4 当事者の葛藤の程度別・面会交流方法
5 面会交流条項の定め方の基本
(1)合意する場面別の基本条項の内容
(2)当事者が理解できる内容・平易な用語の使用
【書式例】面会交流実施要領
6 面会交流の頻度の定め方
(1)頻度の定め方の基本形
(2)基本形以外の定め方〜時期や月によって頻度を変える方法〜
7 面会