行政事件訴訟における調査検討・審理運営の在り方について

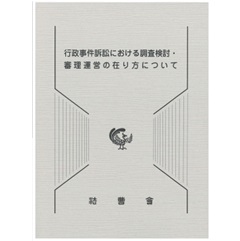
販売価格: 2,900円 税込
本書は、平成29年1月に行われた司法研修所の行政基礎研究会における東京地裁部総括判事(当時)岩井伸晃氏(現高松高裁長官)による講演(行政事件訴訟における調査検討・審理運営の在り方についての講演)の内容を基に、同氏がこれを取りまとめた講演録に行政事件訴訟の執務の参考に資する観点から補筆を加えたもので、行政事件訴訟の実務に携わる各位の好個の参考資料と思われるので、書籍として刊行することとなりました。
以上の経緯から、本書は、主に行政事件を初めて担当する裁判官を対象として、平成16年改正後の行政事件訴訟法の枠組みや主要な判例の概説及び一般的な実務の運用の紹介を中心に、行政事件訴訟における調査検討・審理運営に関する基本的な事項を実務家の視点から分かりやすく説明したものであり、これまで行政事件を担当する裁判官に実務の基本書として広く参照されてきた司法研修所編「改訂・行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究」(法曹会。通称「実務的研究」)を行政事件訴訟法の平成16年改正の内容の反映等の観点から補完する資料として、執務の参考になるものと思われます。
行政事件訴訟法の平成16年改正の当時、内閣法制局参事官として改正法案の審査を担当し、改正法の施行後は東京地裁行政部の部総括及び最高裁行政調査官室の上席調査官として行政事件を担当した著者の経験を踏まえ、改正法の精神・趣旨の実務への反映に資するよう、平成29年当時の講演の内容を基に、その後の判例や法改正等も踏まえ、これを敷えんして補筆が加えられ、今般の刊行に至ったものです。
<目 次>
第1 はじめに
第2 行政事件訴訟の特質と概況
1 行政事件訴訟の特質
2 行政事件訴訟の概況
⑴ 租税訴訟の複雑化・大型化
⑵ 住民訴訟の多様化・複雑化
⑶ 情報公開請求訴訟の増加・複雑化
⑷ 環境訴訟の増加・複雑化
⑸ 社会保障関係訴訟の増加・複雑化
⑹ 外国人事件の増加
⑺ 事件の多様化
3 平成16年の行訴法改正の実務への影響 ⑴ 原告適格(行訴法9条2項) ⑵ 義務付け訴訟・差止訴訟の創設(行訴法3条6項・7項、37条の2~37条の4) ⑶ 当事者訴訟の類型としての確認訴訟の明示(行訴法4条) ⑷ 処分性の概念の拡張 ⑸ 仮の救済手続の拡充(行訴法25条、37条の5) ⑹ 改正行訴法検証研究会 第3 調査の要点 1 法令等の調査・検討 2 判例・裁判例の調査・検討 ⑴ 最高裁判例(民集、集民、裁判所時報、裁判所ウェブサイト等) ⑵ 下級審裁判例(行裁集、裁判所ウェブサイト、訟務月報、判時、判タ、判例地方自治等) 3 実務上の有用な文献等 第4 訴状審査等 1 訴状審査の意義・方法 ⑴ 訴状審査の意義 ⑵ 訴状審査の方法 2 審査結果を踏まえた対応 ⑴ 口頭の事務連絡 ⑵ 書面による事務連絡 ⑶ 補正命令 ⑷ 第1回口頭弁論期日の指定 ⑸ 140条却下判決 3 審査事項等 ⑴ 基礎的な審査事項 ⑵ 訴訟要件 ア 抗告訴訟の基本的な訴訟要件(処分性、原告適格、訴えの利益) イ 抗告訴訟の被告適格 ウ 取消訴訟の審査請求前置 エ 取消訴訟の出訴期間 オ 取消訴訟以外の抗告訴訟に固有の訴訟要件 カ 当事者訴訟の訴訟要件 キ 抗告訴訟及び当事者訴訟に係る法律上の争訟性(裁判所法3条1項) ク 民衆訴訟及び機関訴訟の訴訟要件(行訴法5条、6条、42条等) ケ 住民訴訟の訴訟要件(地方自治法242条の2、242条1項・2項) ⑶ 請求の趣旨 第5 合議等の準備と審理・判決 1 合議等の準備 ⑴ 合議メモの活用 ⑵ 合議の充実 ア 合議体による期日前の合議・随時合議 イ 判決作成段階の書面合議(後記3⑵参照) ⑶ 判決を当初から視野に入れた審理・作業の工夫(後記3⑴参照) 2 審理上の留意点 ⑴ 審理の構造と理論上の問題 ⑵ 釈明の在り方 ⑶ 求釈明、釈明処分の申立て及び文書提出命令の申立てへの対応 ⑷ 請求の追加・変更の申立てへの対応 ⑸ 処分理由の差し替えの可否 ⑹ 意見陳述の申出への対応 ⑺ 証拠調べ ⑻ 訴訟要件の審理と本案要件の審理 ⑼ 訴訟参加 ⑽ 和解の可能性 ⑾ その他 3 判決作成上の工夫・留意点 ⑴ 判決を当初から視野に入れた審理・作業の工夫(前記1⑶参照) ⑵ 判決原案の提出時及びそれ以降の作業の工夫(前記1⑵イ参照) ⑶ 判決の作成に当たっての留意点 ⑷ 基本的な構成 第6 仮の救済 1 執行停止(行訴法25条) ⑴ 手続・日程の調整 ⑵ 要件の審査 ⑶ 平成16年改正後の認容例 2 仮の義務付け及び仮の差止め(行訴法37条の5) ⑴ 手続・日程の調整 ⑵ 要件の審査 ⑶ 平成16年改正による制度創設後の認容例 3 仮処分の排除(行訴法44条) ⑴ 行訴法44条の趣旨 ⑵ 行訴法44条の適用関係 第7 終わりに 1 行政事件の判決の重要性と社会的な影響等 ⑴ 行政・立法への影響・波及と社会的な影響等 ⑵ 行政・社会の規範の形成・基準の提示等(法令解釈の重要性) 2 通常民事事件の処理にも資する取組の姿勢等 ⑴ 判決を見据えた審理・釈明・和解等 ⑵ 合議の充実 ⑶ 判決の精度の向上(法的思考力・多角的視点・バランス感覚等の涵養) 3 最後に 巻末資料 参考資料1(レジュメ) 参考資料2(事務連絡の書式例) 参考資料3(行政事件訴訟における請求の趣旨の文例)