刑法総論 (法律学の森)
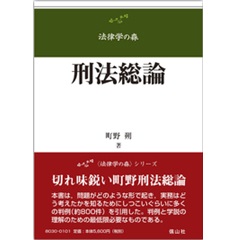
販売価格: 6,160円 税込
◆刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう対応したか ― 800件に及ぶ刑法総論関係判例を再検討した切れ味鋭い体系書◆
刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう考えたかを知るために、本書はかなり多くの判例を、しつこいくらい引用した。
法律学を学ぶ者は判例と学説を理解することが最低限必要であるが、さらにこれを武器として変革を求めなければならない。
動中に静を求める時代から静中に動を求めなければならない時代になっているという認識に立って本書を執筆した(「はしがき」より)。
【目 次】
はしがき
◇第1編 刑法理論と刑法◇
◆第1章 刑法理論
第1節 刑法と刑法学
第1款 刑法の意義
1 刑法の概念
2 現行刑法の制定
3 刑法改正と刑法の平易化
4 進行する刑法改正
第2款 刑法学の意義
第2節 刑法の役割
第1款 刑罰と犯罪の抑止
1 絶対的応報刑論と相対的応報刑論,規範防衛論と抑止刑論
2 刑罰論と犯罪概念―行為無価値論・結果無価値論
3 一般予防・特別予防および規範的予防
第2款 刑罰からの人権の保護
1 罪刑法定主義と罪刑専断主義
2 刑罰積極主義と刑罰消極主義
3 罪刑均衡の原則と刑罰の個別化
4 客観主義と主観主義,現実説と徴表説
◆第2章 罪刑法定主義と刑法の解釈
第1節 罪刑法定主義の実質化
1 罪刑法定主義の内容
2 刑法解釈の特色
第2節 法律主義
第1款 成文法主義
第2款 命 令
1 政令と命令
2 委任の特定性
第3款 条例
1 地方公共団体の刑事立法権
2 条例の法令との抵触
第3節 処罰の適正
第1款 遡及処罰の禁止
1 禁止範囲の拡張
2 「法」の遡及
3 「事後」の法
第2款 刑罰法規の明確性
1 刑罰法規の不明確性,過度の広範性
2 限定解釈による救済
3 法定刑の明確性
第3款 残虐な刑罰,不均衡な刑罰
1 残虐な刑罰
2 罪刑の均衡
3 差別的な法定刑
第4款 適正処罰の原則
1 「犯罪」とすることの合憲性
2 行為刑法,責任主義
3 被害者なき犯罪
第4節 刑法の解釈
第1款 刑法の解釈と罪刑法定主義
1 目的論的解釈
2 解釈の明確性
第2款 拡張解釈
1 類推解釈の禁止
2 拡張解釈の限界
第3款 限定解釈(縮小解釈)
1 限定解釈の必要性
2 合憲的限定解釈
3 限定解釈の限界
◆第3章 刑法の適用
第1節 刑法の適用と訴訟障害
第2節 刑法の時間的適用範囲
第1款 時際刑法の基本原則
第2款 刑罰法規の追及効
1 限時法理論
2 委任命令の改廃
3 補充法令の変更
第3節 刑法の場所的適用範囲
第1款 国際法と刑法
1 時際刑法と国際刑法
2 国際刑法の諸相
第2款 国内犯
1 属地主義・旗国主義
2 犯罪地の意義
3 結 果
4 行 為
第3款 国外犯
1 国外犯の処罰
2 国家自己保護
3 積極的属人主義
4 世界主義
第4款 外国刑事判決の効力
◇第2編 犯 罪◇
◆第1章 犯罪論の意義と役割
第1節 刑法総論と刑法各論
第2節 犯罪論体系の意義と機能
◆第2章 構成要件該当性
第1節 構成要件の機能と概念
第1款 罪刑法定主義機能
第2款 刑罰法規と構成要件
1 刑罰法規の解釈と構成要件
2 記述的構成要件要素と規範的構成要件要素
3 閉ざされた構成要件・開かれた構成要件,可罰的違法性の判断
第3款 不法責任類型としての構成要件
第2節 行 為
第1款 行為概念の機能
1 構成要件該当行為と正犯概念
2 行為責任の原則
3 身体性と有意性
4 行為論の体系的機能
第2款 法人の行為と犯罪
1 法人の犯罪能力と法人処罰
2 法人の行為
第3節 不作為犯
第1款 不作為の構成要件該当性
1 作為・不作為の構成要件該当性
2 真正不作為犯と不真正不作為犯
3 不作為の構成要件該当性
4 作為と不作為との関係
第2款 作為義務
1 不真正不作為犯における作為義務
2 作為の容易性
3 作為義務と保障人的地位
4 判例における作為義務
第4節 法益の侵害と危殆
第1款 侵害犯と危険犯
1 形式犯と実質犯
2 行為犯と結果犯
3 侵害犯と危険犯
第2款 構成要件的状況と処罰条件
第3款 犯罪の終了
1 即成犯,状態犯・継続犯
2 公訴時効の開始
3 犯罪の継続
4 犯罪の継続と罪数
第5節 因果関係
第1款 刑法における因果関係
第2款 条件関係
1 条件関係の意義
2 条件関係の存否
3 条件関係の証明
4 同時傷害の特例
第3款 相当因果関係
1 相当因果関係説の意義
2 相当因果関係論の基礎
3 事後の行為の介入
4 結果的加重犯の因果関係
5 早すぎた結果の発生
第6節 主観的構成要件要素
第1款 構成要件と主観的要素
第2款 主観的違法要素と責任要素
1 目的犯
2 表示犯
3 傾向犯
4 未遂犯
◆第3章 故 意
第1節 故意犯
第1款 意思責任の原則
1 責任主義
2 故意犯と過失犯
第2款 故意の概念
1 故意の現実性
2 故意の体系的地位
第2節 故意の態様
第1款 意思説・認識説・動機説
第2款 確定的故意と未必の故意
1 確定的故意
2 未必の故意
第3款 概括的故意と択一的故意
1 概括的故意
2 択一的故意
第4款 未確定的故意と条件付き故意
1 未確定的故意
2 条件付き故意
第3節 錯 誤
第1款 事実の認識と故意犯
1 故意と錯誤
2 処罰条件,結果的加重犯
3 犯罪阻却事由,刑罰減少事由の錯誤
4 違法阻却事由の過剰とその認識
5 意味の認識
第2款 抽象的事実の錯誤
1 事実の錯誤の種類
2 符合の限界
3 故意犯の成立
第3款 方法の錯誤
1 抽象的法定的符合説と具体的法定的符合説
2 客体の錯誤と方法の錯誤
第4款 因果関係の錯誤
1 因果関係の認識と故意
2 因果経過の錯誤
◆第4章 過 失
第1節 過失犯の処罰
第1款 刑事責任としての過失
第2款 過失犯の処罰規定
第2節 過失犯における違法と責任
第1款 過失犯の構造
1 新・旧過失犯論
2 過失行為
3 過失責任
第2款 重過失と業務上過失
1 過失の種類
2 重過失
3 業務上過失
第3節 予見可能性
第1款 予見可能性の意義
1 具体的予見可能性
2 予見可能性の対象
3 予見可能性の標準
第2款 信頼の原則
1 信頼の原則と予見可能性
2 行為者の交通法規違反
3 チーム医療
第3款 管理・監督過失
1 管理過失と監督過失
2 管理者の作為義務
3 結果の予見可能性
◆第5章 違法阻却事由
第1節 違法阻却事由の意義
第1款 犯罪阻却事由と違法阻却事由
1 犯罪の成立を阻却する消極的要件
2 構成要件該当性阻却と違法阻却
第2款 違法性と違法阻却
1 結果無価値論と違法阻却
刑法の問題がどのような形で起き、実務はどう考えたかを知るために、本書はかなり多くの判例を、しつこいくらい引用した。
法律学を学ぶ者は判例と学説を理解することが最低限必要であるが、さらにこれを武器として変革を求めなければならない。
動中に静を求める時代から静中に動を求めなければならない時代になっているという認識に立って本書を執筆した(「はしがき」より)。
【目 次】
はしがき
◇第1編 刑法理論と刑法◇
◆第1章 刑法理論
第1節 刑法と刑法学
第1款 刑法の意義
1 刑法の概念
2 現行刑法の制定
3 刑法改正と刑法の平易化
4 進行する刑法改正
第2款 刑法学の意義
第2節 刑法の役割
第1款 刑罰と犯罪の抑止
1 絶対的応報刑論と相対的応報刑論,規範防衛論と抑止刑論
2 刑罰論と犯罪概念―行為無価値論・結果無価値論
3 一般予防・特別予防および規範的予防
第2款 刑罰からの人権の保護
1 罪刑法定主義と罪刑専断主義
2 刑罰積極主義と刑罰消極主義
3 罪刑均衡の原則と刑罰の個別化
4 客観主義と主観主義,現実説と徴表説
◆第2章 罪刑法定主義と刑法の解釈
第1節 罪刑法定主義の実質化
1 罪刑法定主義の内容
2 刑法解釈の特色
第2節 法律主義
第1款 成文法主義
第2款 命 令
1 政令と命令
2 委任の特定性
第3款 条例
1 地方公共団体の刑事立法権
2 条例の法令との抵触
第3節 処罰の適正
第1款 遡及処罰の禁止
1 禁止範囲の拡張
2 「法」の遡及
3 「事後」の法
第2款 刑罰法規の明確性
1 刑罰法規の不明確性,過度の広範性
2 限定解釈による救済
3 法定刑の明確性
第3款 残虐な刑罰,不均衡な刑罰
1 残虐な刑罰
2 罪刑の均衡
3 差別的な法定刑
第4款 適正処罰の原則
1 「犯罪」とすることの合憲性
2 行為刑法,責任主義
3 被害者なき犯罪
第4節 刑法の解釈
第1款 刑法の解釈と罪刑法定主義
1 目的論的解釈
2 解釈の明確性
第2款 拡張解釈
1 類推解釈の禁止
2 拡張解釈の限界
第3款 限定解釈(縮小解釈)
1 限定解釈の必要性
2 合憲的限定解釈
3 限定解釈の限界
◆第3章 刑法の適用
第1節 刑法の適用と訴訟障害
第2節 刑法の時間的適用範囲
第1款 時際刑法の基本原則
第2款 刑罰法規の追及効
1 限時法理論
2 委任命令の改廃
3 補充法令の変更
第3節 刑法の場所的適用範囲
第1款 国際法と刑法
1 時際刑法と国際刑法
2 国際刑法の諸相
第2款 国内犯
1 属地主義・旗国主義
2 犯罪地の意義
3 結 果
4 行 為
第3款 国外犯
1 国外犯の処罰
2 国家自己保護
3 積極的属人主義
4 世界主義
第4款 外国刑事判決の効力
◇第2編 犯 罪◇
◆第1章 犯罪論の意義と役割
第1節 刑法総論と刑法各論
第2節 犯罪論体系の意義と機能
◆第2章 構成要件該当性
第1節 構成要件の機能と概念
第1款 罪刑法定主義機能
第2款 刑罰法規と構成要件
1 刑罰法規の解釈と構成要件
2 記述的構成要件要素と規範的構成要件要素
3 閉ざされた構成要件・開かれた構成要件,可罰的違法性の判断
第3款 不法責任類型としての構成要件
第2節 行 為
第1款 行為概念の機能
1 構成要件該当行為と正犯概念
2 行為責任の原則
3 身体性と有意性
4 行為論の体系的機能
第2款 法人の行為と犯罪
1 法人の犯罪能力と法人処罰
2 法人の行為
第3節 不作為犯
第1款 不作為の構成要件該当性
1 作為・不作為の構成要件該当性
2 真正不作為犯と不真正不作為犯
3 不作為の構成要件該当性
4 作為と不作為との関係
第2款 作為義務
1 不真正不作為犯における作為義務
2 作為の容易性
3 作為義務と保障人的地位
4 判例における作為義務
第4節 法益の侵害と危殆
第1款 侵害犯と危険犯
1 形式犯と実質犯
2 行為犯と結果犯
3 侵害犯と危険犯
第2款 構成要件的状況と処罰条件
第3款 犯罪の終了
1 即成犯,状態犯・継続犯
2 公訴時効の開始
3 犯罪の継続
4 犯罪の継続と罪数
第5節 因果関係
第1款 刑法における因果関係
第2款 条件関係
1 条件関係の意義
2 条件関係の存否
3 条件関係の証明
4 同時傷害の特例
第3款 相当因果関係
1 相当因果関係説の意義
2 相当因果関係論の基礎
3 事後の行為の介入
4 結果的加重犯の因果関係
5 早すぎた結果の発生
第6節 主観的構成要件要素
第1款 構成要件と主観的要素
第2款 主観的違法要素と責任要素
1 目的犯
2 表示犯
3 傾向犯
4 未遂犯
◆第3章 故 意
第1節 故意犯
第1款 意思責任の原則
1 責任主義
2 故意犯と過失犯
第2款 故意の概念
1 故意の現実性
2 故意の体系的地位
第2節 故意の態様
第1款 意思説・認識説・動機説
第2款 確定的故意と未必の故意
1 確定的故意
2 未必の故意
第3款 概括的故意と択一的故意
1 概括的故意
2 択一的故意
第4款 未確定的故意と条件付き故意
1 未確定的故意
2 条件付き故意
第3節 錯 誤
第1款 事実の認識と故意犯
1 故意と錯誤
2 処罰条件,結果的加重犯
3 犯罪阻却事由,刑罰減少事由の錯誤
4 違法阻却事由の過剰とその認識
5 意味の認識
第2款 抽象的事実の錯誤
1 事実の錯誤の種類
2 符合の限界
3 故意犯の成立
第3款 方法の錯誤
1 抽象的法定的符合説と具体的法定的符合説
2 客体の錯誤と方法の錯誤
第4款 因果関係の錯誤
1 因果関係の認識と故意
2 因果経過の錯誤
◆第4章 過 失
第1節 過失犯の処罰
第1款 刑事責任としての過失
第2款 過失犯の処罰規定
第2節 過失犯における違法と責任
第1款 過失犯の構造
1 新・旧過失犯論
2 過失行為
3 過失責任
第2款 重過失と業務上過失
1 過失の種類
2 重過失
3 業務上過失
第3節 予見可能性
第1款 予見可能性の意義
1 具体的予見可能性
2 予見可能性の対象
3 予見可能性の標準
第2款 信頼の原則
1 信頼の原則と予見可能性
2 行為者の交通法規違反
3 チーム医療
第3款 管理・監督過失
1 管理過失と監督過失
2 管理者の作為義務
3 結果の予見可能性
◆第5章 違法阻却事由
第1節 違法阻却事由の意義
第1款 犯罪阻却事由と違法阻却事由
1 犯罪の成立を阻却する消極的要件
2 構成要件該当性阻却と違法阻却
第2款 違法性と違法阻却
1 結果無価値論と違法阻却