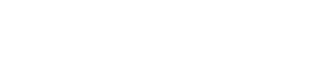法哲学はこんなに面白い

販売価格: 5,500円 税込
- 数量
研究生活40年の教授が説く,法哲学という学問の面白さと多様性。17編の論文・書評を収録。2019年1月の最終講義の記録も収載
【目 次】
・序 文
1 私の歩んできた法哲学研究の道
はじめに
① 思想史
② 規範的正義論、特にリバタリアニズム
③ 人格の同一性
④ 実定法学の基礎的問題
⑤ 法概念論
⑥ 幸福論
⑦ 翻 訳
終わりに
◇第一部 思想史◇
2 労働と私有財産
はじめに
一 先占から労働へ
1 ロック以前 2 ロックの所有論
二 現代の所有論
1 労働所有論の受容と批判 2 所有権論の原状と将来
む す び
3 ポリガミーと離婚に関する近世・近代ヨーロッパの思想――グロティウスからミルの批判者まで
一 序
二 近世自然法論
1 グロティウス 2 プーフェンドルフ
三 ミルトン
四 モンテスキューとスコットランド啓蒙
1 モンテスキュー 2 ハチスンとフォーダイス 3 ヒューム 4 スミス
五 ドイツ観念論
1 カント 2 ヘーゲル
六 ミルとその批判者たち
1 ミル 2 スティーヴンほか
七 結 語
◇第二部 規範的正義論、特にリバタリアニズム◇
4 マイケル・サンデルのコミュニタリアニズムを批判する
一 序
二 『民主政の不満』
三 『公共哲学』
四 サンデルのコミュニタリアン共和主義一般について
1 コミュニティへの帰属の価値 2 コミュニティとアソシエーション
3 「集団的アイデンティティ」批判の問題点 4 リベラル・コミュニタリアン論争は食い違っていたのか?
5 ロールズ 6 宗教と道徳 7 政治哲学は「善き生」について語るべきでない
五 『完全な人間を目指さなくてもよい理由』
六 『それをお金で買いますか』
七 サンデルの市場社会批判一般について
1 「市場化(商品化)」の二つの意味 2 売買は悪いが無償の贈与ならばよいのか?
3 自由の軽視と平等主義 4 理論的検討の薄弱さ
5 移民の規制は正当化できるか
一 序
1 この問題に関する議論はまだ多くない――特に日本では 2 出国と入国 3 本章で取り扱わない問題
二 自由権
1 移動の自由 2 経済的自由 3 結社の自由
三 民主主義
1 集団的自己統治 2 国民の意志 3 「足による投票」
四 社会の一体性
五 経済的豊かさ
六 分配的正義、特に平等
七 エコロジー
八 パターナリズム
九 結 語
6 移民規制に関するリバタリアンの議論
一 序
二 移民規制に反対するリバタリアン
三 移民規制に賛成するリバタリアン
1 晩年のロスバード 2 ホッペ 3 自由を尊重する社会と移民
四 実際的な結論
7 未来世代への道徳的義務の性質
一 序――いくつかの前提
二 未来世代は権利を持つか?
三 現在世代はなぜ未来世代に義務を負うのか、またどのような義務を負うのか?
1 功利主義 2 「間接的互恵性」の議論 3 ロールズの「貯蓄原理」 4 平等主義
5 改善主義あるいは非改悪主義 6 十分主義 7 優先主義 8 歴史を通じた大共同体としての人類
四 残された問題
◇第三部 人格の同一性◇
8 個人はいかにして存在するか
一 進化生物学と道徳
二 自己利益と人格の観念
三 人格に関する三次元主義と四次元主義
四 幸福(効用)評価の時間的単位
◇第四部 実定法学の基礎的問題◇
9 私的自治とは何か、また何のためか
序
一 「私的自治」の意味――それは実質上「契約の自由」と大差ない
二 私的自治は契約の法的強制を含む
三 契約が法的拘束力を認められるべき理由
補 論
1 和田仁孝「対話的私的自治の可能性へ向けて」へのコメント 2 浅野・山田コメントへの回答
10 親族法の私法化のために
一 民法典、特に親族法はいかなる点で公的か
二 リバタリアンな親族法(および刑法)の提案
三 リバタリアンな家族法解釈論
四 結 語
11 知的財産権に関するリバタリアンの議論
一 序
二 知的財産権を支持するリバタリアン
1 自然権としての知的財産権 2 インセンティヴ論
三 無体財産権に反対するリバタリアン
1 知的財産権はむしろ自由と財産権を制限する 2 インセンティヴ論への疑問
四 結 論
12 公用収用の法哲学的問題
◇第五部 書 評◇
13 規範的経済学の哲学的研究――塩野谷祐一『価値理念の構造ー効用対権利』(東洋経済新報社、一九八五年)
14 最後期ロールズの国際的正義論――ジョン・ロールズ『万民の法』(中山竜一訳、岩波書店、二〇〇六年)
一 内容の紹介
二 コメント
1 語られなかったこと、不明確なまま残されていること 2 「民衆(ピープル)」と「国家(ステイト)」の区別
3 援助義務と分配的正義との相違
15 ホッブズとケルゼンの解釈をめぐって――長尾龍一『ケルゼン研究Ⅲ』(慈学社、二〇一三年)
一 編集方針の問題点
二 ケルゼンの法学
三 ホッブズの自然状態論と社会契約論
追 記
16 法理論における立法の意義――『立法学のフロンティア』(全三巻)(ナカニシヤ出版、二〇一四年)
一 はじめに
二 規範的法実証主義と法の「正統性」
1 「規範的法実証主義」を取り上げる理由 2 名称と範囲の問題 3 記述的法実証主義との関係
4 法の正統性と正当性 5 正統性のない法には従う義務がないか?正統性のある法には必ず従うべきか?
6 特定の領域における法の正統性
三 その他の論文三篇
17 もしドゥオーキンが日本の憲法学者になったら――小泉良幸『個人として尊重 「われら国民」のゆくえ』(勁草書房、二〇一六年)
一 はじめに
二 立憲主義
三 自由よりも自律?
四 密教としての《リベラリズム》
五 ドゥオーキンは運の平等主義者でないのか?
・主要研究業績目録
・索引(人名・事項)
・序 文
1 私の歩んできた法哲学研究の道
はじめに
① 思想史
② 規範的正義論、特にリバタリアニズム
③ 人格の同一性
④ 実定法学の基礎的問題
⑤ 法概念論
⑥ 幸福論
⑦ 翻 訳
終わりに
◇第一部 思想史◇
2 労働と私有財産
はじめに
一 先占から労働へ
1 ロック以前 2 ロックの所有論
二 現代の所有論
1 労働所有論の受容と批判 2 所有権論の原状と将来
む す び
3 ポリガミーと離婚に関する近世・近代ヨーロッパの思想――グロティウスからミルの批判者まで
一 序
二 近世自然法論
1 グロティウス 2 プーフェンドルフ
三 ミルトン
四 モンテスキューとスコットランド啓蒙
1 モンテスキュー 2 ハチスンとフォーダイス 3 ヒューム 4 スミス
五 ドイツ観念論
1 カント 2 ヘーゲル
六 ミルとその批判者たち
1 ミル 2 スティーヴンほか
七 結 語
◇第二部 規範的正義論、特にリバタリアニズム◇
4 マイケル・サンデルのコミュニタリアニズムを批判する
一 序
二 『民主政の不満』
三 『公共哲学』
四 サンデルのコミュニタリアン共和主義一般について
1 コミュニティへの帰属の価値 2 コミュニティとアソシエーション
3 「集団的アイデンティティ」批判の問題点 4 リベラル・コミュニタリアン論争は食い違っていたのか?
5 ロールズ 6 宗教と道徳 7 政治哲学は「善き生」について語るべきでない
五 『完全な人間を目指さなくてもよい理由』
六 『それをお金で買いますか』
七 サンデルの市場社会批判一般について
1 「市場化(商品化)」の二つの意味 2 売買は悪いが無償の贈与ならばよいのか?
3 自由の軽視と平等主義 4 理論的検討の薄弱さ
5 移民の規制は正当化できるか
一 序
1 この問題に関する議論はまだ多くない――特に日本では 2 出国と入国 3 本章で取り扱わない問題
二 自由権
1 移動の自由 2 経済的自由 3 結社の自由
三 民主主義
1 集団的自己統治 2 国民の意志 3 「足による投票」
四 社会の一体性
五 経済的豊かさ
六 分配的正義、特に平等
七 エコロジー
八 パターナリズム
九 結 語
6 移民規制に関するリバタリアンの議論
一 序
二 移民規制に反対するリバタリアン
三 移民規制に賛成するリバタリアン
1 晩年のロスバード 2 ホッペ 3 自由を尊重する社会と移民
四 実際的な結論
7 未来世代への道徳的義務の性質
一 序――いくつかの前提
二 未来世代は権利を持つか?
三 現在世代はなぜ未来世代に義務を負うのか、またどのような義務を負うのか?
1 功利主義 2 「間接的互恵性」の議論 3 ロールズの「貯蓄原理」 4 平等主義
5 改善主義あるいは非改悪主義 6 十分主義 7 優先主義 8 歴史を通じた大共同体としての人類
四 残された問題
◇第三部 人格の同一性◇
8 個人はいかにして存在するか
一 進化生物学と道徳
二 自己利益と人格の観念
三 人格に関する三次元主義と四次元主義
四 幸福(効用)評価の時間的単位
◇第四部 実定法学の基礎的問題◇
9 私的自治とは何か、また何のためか
序
一 「私的自治」の意味――それは実質上「契約の自由」と大差ない
二 私的自治は契約の法的強制を含む
三 契約が法的拘束力を認められるべき理由
補 論
1 和田仁孝「対話的私的自治の可能性へ向けて」へのコメント 2 浅野・山田コメントへの回答
10 親族法の私法化のために
一 民法典、特に親族法はいかなる点で公的か
二 リバタリアンな親族法(および刑法)の提案
三 リバタリアンな家族法解釈論
四 結 語
11 知的財産権に関するリバタリアンの議論
一 序
二 知的財産権を支持するリバタリアン
1 自然権としての知的財産権 2 インセンティヴ論
三 無体財産権に反対するリバタリアン
1 知的財産権はむしろ自由と財産権を制限する 2 インセンティヴ論への疑問
四 結 論
12 公用収用の法哲学的問題
◇第五部 書 評◇
13 規範的経済学の哲学的研究――塩野谷祐一『価値理念の構造ー効用対権利』(東洋経済新報社、一九八五年)
14 最後期ロールズの国際的正義論――ジョン・ロールズ『万民の法』(中山竜一訳、岩波書店、二〇〇六年)
一 内容の紹介
二 コメント
1 語られなかったこと、不明確なまま残されていること 2 「民衆(ピープル)」と「国家(ステイト)」の区別
3 援助義務と分配的正義との相違
15 ホッブズとケルゼンの解釈をめぐって――長尾龍一『ケルゼン研究Ⅲ』(慈学社、二〇一三年)
一 編集方針の問題点
二 ケルゼンの法学
三 ホッブズの自然状態論と社会契約論
追 記
16 法理論における立法の意義――『立法学のフロンティア』(全三巻)(ナカニシヤ出版、二〇一四年)
一 はじめに
二 規範的法実証主義と法の「正統性」
1 「規範的法実証主義」を取り上げる理由 2 名称と範囲の問題 3 記述的法実証主義との関係
4 法の正統性と正当性 5 正統性のない法には従う義務がないか?正統性のある法には必ず従うべきか?
6 特定の領域における法の正統性
三 その他の論文三篇
17 もしドゥオーキンが日本の憲法学者になったら――小泉良幸『個人として尊重 「われら国民」のゆくえ』(勁草書房、二〇一六年)
一 はじめに
二 立憲主義
三 自由よりも自律?
四 密教としての《リベラリズム》
五 ドゥオーキンは運の平等主義者でないのか?
・主要研究業績目録
・索引(人名・事項)