広がる民法5 学説解読編
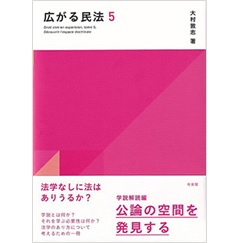
販売価格: 4,290円 税込
法と密接不可分の関係にある法学における「学説」の議論を追うことにより,法的な思考様式の諸側面を示していく。学説という議論空間を注意深くみることで,民法の理解をさらに豊かなものとする。法や法学のあり方について考える際の手がかりとしても最適。
目次
序 章 基本概念─行為と組織
1 民法と民法学──民法を学ぶのか,民法学を学ぶのか
2 ロースクール教育と法学部教育──何を目指すべきか
第1章 基本概念─行為と阻止区
3 法律行為と法秩序──何が規範を創りだすか
4 時効の存在理由──時効制度をいかに説明するか
5 法人とは何か──民法に規定は不要か
第2章 人と家族─主体と支援
6 嫡出推定──何のための制度か
7 内縁──婚姻はどうなるのか
8 成年後見・扶養──家族の限界はどこにあるのか
第3章 物権・不法行為─支配と救済
9 物権変動の法的構成──何が問題なのか
10 過失と違法──何のための議論か
11 損害──もうひとつの不法行為法へ
第4章 債権・契約─交換と実現
12 債務の構造──債権法学説は何を目指したのか
13 瑕疵担保──契約法学説は何を目指すか
14 不動産賃借権──時代の変遷とともに
15 債権譲渡──債権の財産化
16 債権者代位権・詐害行為取消権──変遷する制度趣旨
第5章 担保・相続─安定と継続
17 抵当権と利用権──近代的抵当権論をめぐって
18 遺言による相続──なぜ遺言は増えているのか
補 章 法学の方法─参与と観察
19 法解釈の意義と方法──法律家は何をしているのか
20 法律学の対象と方法──法学者は何をしているのか
目次
序 章 基本概念─行為と組織
1 民法と民法学──民法を学ぶのか,民法学を学ぶのか
2 ロースクール教育と法学部教育──何を目指すべきか
第1章 基本概念─行為と阻止区
3 法律行為と法秩序──何が規範を創りだすか
4 時効の存在理由──時効制度をいかに説明するか
5 法人とは何か──民法に規定は不要か
第2章 人と家族─主体と支援
6 嫡出推定──何のための制度か
7 内縁──婚姻はどうなるのか
8 成年後見・扶養──家族の限界はどこにあるのか
第3章 物権・不法行為─支配と救済
9 物権変動の法的構成──何が問題なのか
10 過失と違法──何のための議論か
11 損害──もうひとつの不法行為法へ
第4章 債権・契約─交換と実現
12 債務の構造──債権法学説は何を目指したのか
13 瑕疵担保──契約法学説は何を目指すか
14 不動産賃借権──時代の変遷とともに
15 債権譲渡──債権の財産化
16 債権者代位権・詐害行為取消権──変遷する制度趣旨
第5章 担保・相続─安定と継続
17 抵当権と利用権──近代的抵当権論をめぐって
18 遺言による相続──なぜ遺言は増えているのか
補 章 法学の方法─参与と観察
19 法解釈の意義と方法──法律家は何をしているのか
20 法律学の対象と方法──法学者は何をしているのか