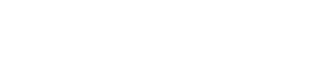令和2年版 社会福祉法人会計の実務 第2編 決算編

販売価格: 4,400円 税込
- 数量
◆概要◆
本書は、平成29年8月に発行された「平成29年4月施行 省令会計基準対応 社会福祉法人会計の実務」(第4編)の改訂版です。前回版の発行以降の平成30年3月及び令和元年5月に厚生労働省令改正、並びに関係局長通知及び課長通知の改正を踏まえた内容となっています。さらに平成31年4月から社会福祉法人の組織再編等の合併及び事業譲渡に関する制度的評価を行う「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」が設けられ、結果として同年9月11日に社会福祉法人会計基準省令及び運用上の取扱い局長通知が一部改正されました。当該改正はともに令和3年4月1日施行ですが、「第2編 決算編」はこれらを反映 した内容で作成しております。
これまでの4分冊を、「第1編月次編」と「第2編決算編」の2分冊としました(第1編は令和2年9月に発行いたしました)。
会計担当者の疑問や不安の解消にお役立ていただき、同時により適正な会計データの作成ができることで、社会福祉事業の円滑な経営に活用して下さい。
◆目次◆
1.社会福祉法における決算の主題
1?事業運営の公開
(1)計算書類等の備置き及び閲覧等
(2)情報の公開等に関する定め
①公表しなければならないもの
②公表の方法
(3)財務諸表等電子開示システム
2?会計監査人監査の導入
(1)特定社会福祉法人等の基準
(2)専門家による内部統制等の支援制度
(3)会計監査人監査等と行政監査との関係
①指導監査実施要綱
②「指導監査ガイドライン」の内容
③一般監査の実施の周期
2.法定の決算スケジュール
1?決算に係る監査及び承認の順序
2?決算原案の理事長承認から資産総額変更登記までのフロー
(1)決算原案の作成と監事監査の実施
(2)理事会の招集・開催・承認
(3)計算書類等の備置き・閲覧対応
(4)定時評議員会の招集・開催・承認等
①リモートによる理事会及び評議員会の開催
②決議の省略
③報告の省略
(5)所轄庁への届出等
①所轄庁への届出
②資産総額の変更登記
③財産目録等の備置き・閲覧対応
④情報の公開等
3?決算確定手続から情報公開等までの関係法令
(1)全般事項
(2)決算作業
(3)監事監査
(4)理事会の招集
(5)理事会の開催・承認
(6)計算書類等の備置き・閲覧等
(7)定時評議員会の招集
(8)定時評議員会の開催・承認・報告
(9)所轄庁への届出
(10)情報公開等
(11)資産総額の変更登記
(12)財産目録等の備置き・閲覧等
3.社会福祉充実計画の承認制度
1?内部留保問題と制度改革
(1)内部留保とは何か
(2)社会福祉法人の純資産の構成と未執行残高
(3)内部留保から社会福祉充実残額と社会福祉充実計画へ
2?財務規律の強化
(1)「社会福祉充実残額」に係る社会福祉法と省令の定め
①法第55条の2
②施行規則第6条の14
3?社会福祉充実残額の算定
(1)「社会福祉充実残額算定シート」の計算プロセス
1.「活用可能な財産の算定」
2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」
3.「再取得に必要な財産」
4.「必要な運転資金」=年間事業活動支出の3月分
5.「計算の特例」
6.「社会福祉充実残額」
7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」
(2)「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の財産目録における特定
4?社会福祉充実計画の策定と承認
(1)社会福祉充実計画の策定と流れ
(2)法第55条の2各項とH29.1.24局長通知の内容
(3)社会福祉充実計画の策定におけるポイント
5?社会福祉充実計画に位置づける事業の種類
6?地域における公益的な取組
7?社会福祉充実残額算定上の留意事項
(1)社会福祉充実残額の自動計算
(2)社会福祉充実計画の入力と承認申請
(3)社会福祉充実残額の現状と課題
(4)社会福祉充実残額の計算過程とその内容
(5)社会福祉充実残額のマイナスの意味
(6)算定された社会福祉充実残額のマイナス値について確認すべきこと
(7)資金在高について考慮すべきこと
(8)計算書類等の公開と社会福祉充実残額
8?建屋ごとの更新資金必要額の計算
4.決算手続の意義と決算の目的
1?決算手続とは
2?決算の目的
3?決算テーマの変容
5.決算書の体系
1?計算書類の体系と様式の定め
2?計算書類の作成単位
3?具体的計算書類体系(拠点区分・事業区分・法人単位)
4?作成を省略できる計算書類の様式
(1)事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合
(2)拠点区分が1つの法人の場合
(3)拠点区分が1つの事業区分の場合
(4)サービス区分が1つの拠点区分の場合
5?計算書類の様式と構成及び表示区分
(1)資金収支計算書
①資金収支計算書の様式
②資金収支計算書の表示区分と報告内容
③貸借対照表との関係
④拠点区分資金収支明細書との関係
(2)事業活動計算書
①事業活動計算書の様式
②事業活動計算書の表示区分と報告内容
③貸借対照表との関係
④拠点区分事業活動明細書との関係
⑤繰越活動増減差額の部
(3)貸借対照表
①貸借対照表の様式
②貸借対照表の表示区分
③資産及び負債の流動と固定の区分について
(運用上の取扱いについて局長通知の6)
④貸借対照表価額(会計基準第4条)
⑤貸借対照表と事業活動計算書の連動関係
⑥計算書類の相互の関係
6?注記の構成
7?財産目録の様式と構成
8?附属明細書の構成
6.決算実務の具体的な取組
1?決算の実務的流れ
2?決算実務のスケジュール表
3?活用上の注意
4?実際の完了予定日時決定のポイント
5?現況報告書提出のポイント
6?決算の所轄庁への届出と情報の公開等
7.決算手続
1?決算予備手続
(1)帳簿記録の検証
(2)決算棚卸表
(3)決算試算表の作成
2?決算本手続(決算整理)
(1)収益、費用の見越・繰延(未収金、未払金、前払金、前受金の計上)
①具体的な収益・費用の見越・繰延
②収益・費用の見越・繰延の期末整理仕訳
③前払費用に係る支払・決算整理・翌期首振替の仕訳処理
④「事業未収金」と「未収収益」の違い
⑤「前受金」と「前受収益」の違い
⑥「事業未払金」と「未払費用」の違い
⑦「前払金」と「前払費用」の違い
(2)棚卸資産(貯蔵品)の計上
(3)満期保有目的債券の償却原価法
(4)短期的運用有価証券の期末評価
(5)投資有価証券の期末評価
(6)外貨建て定期預金の期末評価
(7)資産評価損の計上
(8)固定資産の実査点検による修正
(9)月次減価償却費の概算計上と期末整理
(10)1年基準に係る期末整理
①1年基準が適用されるもの
②1年基準が適用されないもの
③支払資金残高と1年基準採用の関係
④固定資産の1年基準期末整理
⑤長期前払費用における1年基準の適用により生ずる前払費用
⑥固定負債の1年基準による期末整理
⑦長期預り金における1年基準の適用により生ずる「預り金」勘定への振替
⑧割賦購入に係る長期未払金における1年基準
(11)リース資産・リース債務に係る期末整理
(12)国庫補助金等特別積立金の積立と取崩
(13)基本金組入額の確認と処理
(14)その他の積立金の積立と取崩
(15)諸引当金の計上
①徴収不能引当金
②都道府県社協等退職共済に係る退職給付引当金繰入
③法人独自の退職給与規程に係る退職給付引当金繰入
④賞与引当金繰入
⑤役員退職慰労引当金繰入
(16)その他の修正
3?決算後手続
8.内部取引の消去
1?計算書類における内部取引の相殺消去場所
(1)資金収支計算及び事業活動計算における内部取引
(2)貸借対照表における法人内貸借勘定科目とその