実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集 相続編

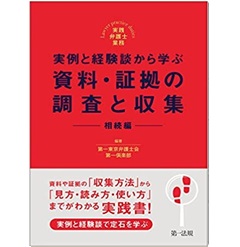
販売価格: 3,960円 税込
資料や証拠の「収集方法」から「見方・読み方・使い方」までがわかる実践書! 実例と経験談で定石を学べる!
弁護士が、相続事件において必要な『資料や証拠の調査』が理解できるだけでなく、『資料や証拠の見方・評価』がわかるようになり、さらに、陥りやすい失敗を避けるための勘所を先輩弁護士の失敗談からも学べる、相続事件に特化した“資料・証拠の調査や収集方法"がわかる実践書。
【目次】※抜粋※
はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例
序編
I はじめに
II 相続問題の手続概要
III 相続問題の具体的場面
事例1 相続人の範囲・遺産の調査・調停・相続分・分割方法・課税関係
(1) 相続人の範囲を確定するために必要な資料の調査方法
(2) 遺産の調査
(3) 遺産分割調停の申立て
(4) 各相続人の相続分の確定
(5) 遺産の分割方法
事例2 相続財産の範囲・評価・分割方法・課税関係
(1) 相続財産の範囲・課税関係
(2) 遺産の評価
(3) 特別受益・寄与分
事例3 相続放棄
(1) 法定代理人による相続放棄
(2) 相続放棄の申述期間
事例4 遺言(平成30年民法改正後)
遺言書作成・配偶者居住権・遺留分
(1) 遺言書の作成
(2) 遺言の調査・遺留分侵害額請求権
事例5 遺言(平成30年民法改正前) 遺言の有効性
事例6 国際相続
第1編 相続開始後における典型的な法的諸問題
第1章 相続人の範囲
I 相続人の調査
1 相続とは何か
2 死亡の概念
3 相続における「被相続人と相続人の同時存在の原則」
4 相続人の確定
5 相続人の法定相続分
6 相続人の確定上の具体的な問題が生じる場合
(1) 想定事案1(同時死亡・代襲相続等)
(2) 想定事案2(相続人の地位の重複の場合)
経験談1 相続人の特定あれこれ
7 相続人確定のための具体的な作業
経験談2 樺太の戸籍と外務省
8 法定相続情報証明制度
II 欠格・廃除
1 相続人の欠格事由(民法891条)
2 相続人の廃除(民法892条)
III 相続人の不存在~特別縁故者制度~
1 はじめに
2 実際の相続財産管理手続
3 特別縁故者の財産分与請求(民法958条の3)
(1) 請求期間
(2) 特別縁故者とは何か
(3) 清算後財産分与の内容
(4) 残余相続財産の国庫帰属(民法959条)
経験談3 民法255条と民法958条の3はどっちが優先?
経験談4 民法255条に基づく共有持分移転登記手続のための相続財産管理人選任申立て
経験談5 特別縁故者による相続財産管理人選任申立て
第2章 遺産の範囲の特定と評価
I 遺産の調査と範囲の適否、遺産の評価
1 不動産
(1) 不動産の調査
(2) 不動産の評価額
(3) 不動産の賃料
経験談6 税務調査が打開した遺産隠し
2 預貯金
(1) 預貯金の調査
(2) 無断引出し
(3) 預貯金払戻し制度
(4) 仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)
経験談7 被相続人名義の貸金庫を相続人の1人が確認する方法
3 有価証券
(1) 有価証券の調査
(2) 有価証券の評価
経験談8 被相続人の財産調査について
4 生命保険
(1) 調 査
(2) 保険契約のパターン
(3) 特別受益との関係
5 暗号資産
(1) 暗号資産とは
(2) 暗号資産は相続対象となるか
(3) 調査に当たっての留意点
6 債権(預貯金債権以外の可分債権)
(1) 預貯金債権以外の債権
(2) 遺産分割の対象か
(3) 債権の調査
7 債 務
(1) 相続財産であるが、遺産分割の対象ではない
(2) 連帯債務
(3) 保証債務
(4) 債務の調査方法
経験談9 社長が被相続人の場合の注意点
8 死亡退職金
(1) 死亡退職金は相続財産か
(2) 死亡退職金の根拠規定がある場合
(3) 死亡退職金の根拠規定がない場合
(4) 死亡退職金の調査
9 公的年金等
(1) 未支給年金について
(2) 遺族に給付される年金
10 祭祀財産・葬儀費用
(1) 祭祀財産
(2) 葬儀費用
(3) 香 典
経験談10 祭祀承継財産は遺産にあらず1相続財産管理人の事例
経験談11 祭祀承継財産は遺産にあらず2遺言執行者の事例
11 法定果実
(1) 問題の所在
(2) 実務上の取扱い
(3) 法定果実の調査方法について
12 使途不明金
(1) 被相続人の生前の使途不明金の場合
(2) 被相続人の死亡後の使途不明金の場合
(3) 改正民法906条の2の規定
(4) 改正民法909条の2との関係
(5) 遺産分割の調停における実務上の処理
経験談12 生前贈与等の持戻しが認められなかった事例
II 遺産の評価
第3章 遺産の分割方法
I 法定相続分
1 法定相続分の調査の意義と方法
2 相続分の譲渡と相続分の放棄
3 相続放棄
経験談13 海外に駆け落ちした相続人が突然帰国したので、公証役場で相続分譲渡証書にサイン証明を添付していただいた事案
II 特別受益
1 特別受益の対象
2 特別受益の効果
3 特別受益に関する問題点
III 寄与分と特別寄与料
1 寄与分と特別寄与料の対象
2 寄与分の算定
3 寄与分に関する問題点
経験談14 寄与と特別寄与料の関係
IV 具体的な分割方法
1 遺産分割の方法
2 現物分割
3 代償分割
4 換価分割
5 共有分割
経験談15 遺産分割と共有物分割
V 遺産分割協議書・調停条項案の作成
1 遺産分割協議
2 書面の作成
経験談16 「ないし」は使わない方がよい?!
経験談17 遺言書がなく、相続人(代襲相続人)が多数存在する事案
第4章 遺留分制度
I はじめに
II 相続法改正による抜本的な制度の見直し
III 遺留分、遺留分侵害額の算定方法
1 遺留分の算定方法について
2 「遺留分を算定するための財産の価額」について
3 「遺留分を算定するための財産の価額」に算入する「贈与」の価額について
4 負担付贈与について
5 遺留分侵害額の算定方法について
IV 遺留分侵害額請求権
1 遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ
2 遺留分侵害額請求権行使の効果について
3 受遺者又は受贈者の負担額について
4 期限の許与について
5 遺留分侵害額算定における債務について
V 具体的事例における計算
事例1
事例2
事例3
経験談18 遺留分減殺請求と認知無効訴訟とDNA鑑定
第5章 相続放棄・限定承認
I 相続放棄
1 相続放棄の概要
(1) 要件と効果
(2) 熟慮期間の起算点
(3) 相続人が数人いる場合の熟慮期間の起算点
(4) 再転相続の場合の熟慮期間の起算点
(5) 熟慮期間経過後の申述
(6) 法定単純承認事由(隠匿)の該当性(形見分け)
2 相続放棄の手続
3 相続放棄の申述
4 相続放棄の申述の受付
5 事実の調査・審理
6 審判と通知
(1) 審判の不服申立てと確定
(2) 審判確定の効力
(3) 審判の取下げ
7 相続放棄の受理証明と照会
(1) 相続放棄の受理証明
(2) 相続放棄の申述有無の照会
8 相続放棄後の相続財産の管理
(1) 相続放棄した者による管理
(2) 裁判所による必要な処分命令
(3) 相続人が明らかでない場合
9 申立期間の伸長
10 相続放棄の取消し
11 相続放棄の無効
12 その他の論点
(1) 共同相続している法定代理人による被後見人又は未成年者の相続放棄
(2) 再転相続と相続放棄
経験談19 相続放棄に関連する事案について
II 限定承認
1 限定承認の概要(要件と効力)
2 限定承認の手続
3 限定承認の申述
4 限定承認の申述の受付
5 事実の調査・審理
6 審判と通知
7 相続放棄の受理証明と照会
8 限定承認後の相続財産の管理
(1) 限定承認者等の職務
(2) 限定承認者等の管理
9 申立期間の伸長
10 限定承認の取消し
経験談20 死後認知で債務