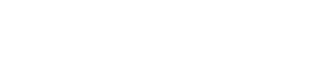所得保障法制成立史論 ― イギリスにおける「生活保障システム」の形成と法の役割

販売価格: 9,900円 税込
- 数量
◆現代的な所得保障法制成立に至る歴史を考察◆
【目次】
◆序 章
第一節 問題意識
第二節 検討の方法
第三節 先行研究の中での本研究の位置付け
第四節 各章の内容
◆第II章 封建制下における労働移動の規制
第一節 はじめに
第二節 封建制下における農民の就労形態とその変容
第三節 1349年労働者勅令・1351年労働者規制法の意義
第四節 1388年法の成立とその意義
第五節 小 括
◆第III章 浮浪者問題の変容と労働能力ある貧民に対する処遇の展開
第一節 本章の目的
第二節 労働移動に対する法規制
第三節 浮浪者規制法の展開と救貧法の生成
第四節 小 括
◆第IV章 旧救貧法体制の確立
第一節 本章の問題意識
第二節 労働能力のない貧民の救済機構の整備
第三節 セツルメント法に基づく「定住資格」の承認と救済を受け得る地位の保障
第四節 小括――旧救貧法体制の確立とその意義
◆第V章 労働移動の加速と旧救貧法体制の対応
第一節 旧救貧法の社会的役割と本章の課題
第二節 教区を基礎とした貧民救済行政の確保と旧救貧法の展開 第一項 「定住資格」の法的安定性の確保
第三節 労働移動の促進とセツルメント法の改正
第四節 小括――旧救貧法体制下における労働移動規制の変容
◆第VI章 19世紀救貧法改革における「問題」の構成
第一節 1834年救貧法改革の前提問題
第二節 教区の統制と治安判事の権限の強化
第三節 教区制度改革の本格化
第四節 救済費による賃金の補完とその問題の本質
第五節 小 括
◆第VII章 新救貧法体制の確立
第一節 はじめに
第二節 1834年救貧法王立委員会報告書
第三節 1834年制定法第76号の制定
第四節 セツルメント法の廃止を巡る制定法の展開
第五節 小括 ――19世紀救貧法改革の帰結
◆第VIII章 労働者の困窮問題の発生とその解決策の不在
第一節 はじめに
第二節 新救貧法体制の下での労働者救済の対応とその限界
第三節 労働組合による共済事業の意義と限界
第四節 小 括
◆第IX章 国営失業保険制度の創設とその意義
第一節 はじめに
第二節 「失業労働者」の救貧法からの分離
第三節 1905―9年救貧法王立委員会
第四節 1911年国民保険(第二部)法の成立
第五節 小括――1911年国営失業保険制度の歴史的位置付け
◆第X章 所得保障制度の確立――労働と所得保障給付の分離へ
第一節 はじめに
第二節 適用対象拡大の失敗
第三節 失業予防施策への転換
第四節 失業に対する所得保障と雇用政策の分離へ
第五節 小 括
◆終 章
第一節 これまでの内容の再整理
第二節 「生活保障システム」の歴史的変遷と法の役割
第三節 むすび
【目次】
◆序 章
第一節 問題意識
第二節 検討の方法
第三節 先行研究の中での本研究の位置付け
第四節 各章の内容
◆第II章 封建制下における労働移動の規制
第一節 はじめに
第二節 封建制下における農民の就労形態とその変容
第三節 1349年労働者勅令・1351年労働者規制法の意義
第四節 1388年法の成立とその意義
第五節 小 括
◆第III章 浮浪者問題の変容と労働能力ある貧民に対する処遇の展開
第一節 本章の目的
第二節 労働移動に対する法規制
第三節 浮浪者規制法の展開と救貧法の生成
第四節 小 括
◆第IV章 旧救貧法体制の確立
第一節 本章の問題意識
第二節 労働能力のない貧民の救済機構の整備
第三節 セツルメント法に基づく「定住資格」の承認と救済を受け得る地位の保障
第四節 小括――旧救貧法体制の確立とその意義
◆第V章 労働移動の加速と旧救貧法体制の対応
第一節 旧救貧法の社会的役割と本章の課題
第二節 教区を基礎とした貧民救済行政の確保と旧救貧法の展開 第一項 「定住資格」の法的安定性の確保
第三節 労働移動の促進とセツルメント法の改正
第四節 小括――旧救貧法体制下における労働移動規制の変容
◆第VI章 19世紀救貧法改革における「問題」の構成
第一節 1834年救貧法改革の前提問題
第二節 教区の統制と治安判事の権限の強化
第三節 教区制度改革の本格化
第四節 救済費による賃金の補完とその問題の本質
第五節 小 括
◆第VII章 新救貧法体制の確立
第一節 はじめに
第二節 1834年救貧法王立委員会報告書
第三節 1834年制定法第76号の制定
第四節 セツルメント法の廃止を巡る制定法の展開
第五節 小括 ――19世紀救貧法改革の帰結
◆第VIII章 労働者の困窮問題の発生とその解決策の不在
第一節 はじめに
第二節 新救貧法体制の下での労働者救済の対応とその限界
第三節 労働組合による共済事業の意義と限界
第四節 小 括
◆第IX章 国営失業保険制度の創設とその意義
第一節 はじめに
第二節 「失業労働者」の救貧法からの分離
第三節 1905―9年救貧法王立委員会
第四節 1911年国民保険(第二部)法の成立
第五節 小括――1911年国営失業保険制度の歴史的位置付け
◆第X章 所得保障制度の確立――労働と所得保障給付の分離へ
第一節 はじめに
第二節 適用対象拡大の失敗
第三節 失業予防施策への転換
第四節 失業に対する所得保障と雇用政策の分離へ
第五節 小 括
◆終 章
第一節 これまでの内容の再整理
第二節 「生活保障システム」の歴史的変遷と法の役割
第三節 むすび