教えて、くま先生! こんなときどうする?社会保障あんしん教室
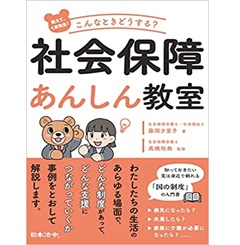
販売価格: 1,980円 税込
病気やケガ、失業、家族の介護などで、今までの生活ができなくなることがあります。
そんなとき、私たちのくらしを守るために日本の社会保障制度にはいろいろな支援があるのですが、非常にわかりづらく、どう使ったらいいのかわからない状態になっています。
本書は、誰にでも起こり得る思いがけないできごとを10の事例でストーリー展開して、こんなときにはこんな制度が使えるなど、立体的に理解できるようにわかりやすく説明しています。
目次
第1章 がんと就労と社会保障
事例2 がんと診断:今後の生活は?
1 がん相談支援センターで今後のことを相談しよう
2 仕事を長期間休むときには「傷病手当金」で所得保障?
3 傷病手当金を使うか使わないか、慎重に判断しよう
4 「傷病手当金」:実際に受給している人の状況は?
5 市区町村国民健康保険の加入者や被扶養者には傷病手当金はない
6 有給休暇はどう使う?
7 高額療養費の限度額適用認定証を取得、自己負担を最小限に。同時に民間の医療保険の補償内容を確認
8 仕事と治療の両立と言われても……
9 治療と仕事の両立支援
10 再発を告げられ、退職を考えた
11 退職の前に休職という選択:3日間の待期期間前に辞めると傷病手当金が受給できない
12 傷病手当金受給
13 障害者手帳交付申請。ストーマ装具等の購入費の給付
14 障害年金を請求
15 障害年金の請求を社会保険労務士に相談
16 求職活動ができるようになれば失業保険の受給ができるかも
17 障害年金受給
18 退職後の健康保険と年金
19 国民年金保険料「失業等による特例免除」がある
20 健康保険の扶養に入れる枠はけっこう広い
21 市区町村国民健康保険には保険料減免がある
22 再就職をめざし、基本手当を受給しながら就職活動
23 障害者など、就職困難者として認定されればより有利な基本手当が受給できるかも
24 雇用保険の基本手当を残して就労したら、再就職手当や就業促進定着手当が受給できるかも
25 65歳になれば、老齢厚生年金と障害年金をどう組み合わせて受給するのか
第2章 精神障害と社会保障
事例2 発達障害:退職
1 休職すると収入がなくなる? 解雇される? 心配なことばかり
2 自立支援医療を使うと医療費が安くなる
3 しっかりと休養するためにも周りの人ときちんと話してみて
4 復職はあせらずに 支援を受けながら
5 発達障害の特性に対する配慮とは
6 障害特性を活かした仕事ぶり
7 カウンセリングの効果
8 うつ病を発症するまで
9 再休職。傷病手当金受給開始
10 精神障害者保健福祉手帳の取得で福祉サービスの利用がスムーズに
11 初診日から1年6か月経過で障害年金の請求が可能
12 傷病手当金を退職後も受給
13 退職後の健康保険と年金
14 求職活動・職業訓練の前に
15 ハローワークで求職の申し込み。就職困難者として基本手当受給
16 基本手当の受給期間延長の申請。基本手当受給開始
17 公共職業訓練を受講
18 障害年金支給停止
19 両親の想い
20 就労の支援を受けながら、再就職
第3章 老齢年金とその他の社会保障制度
事例3 失明の危機:老齢年金との調整
1 いきなり退職、ではなく有給休暇などを活用
2 退職したらまずは年金事務所?
3 仕事ができない状態であれば基本手当は受給できない。傷病手当金や障害年金の活用を検討
4 退職後でも要件にあてはまれば傷病手当金を請求できる
5 まずは傷病手当金請求
6 傷病手当金と60 代前半の老齢厚生年金の支給調整
7 福祉サービスの利用
8 介護保険利用のために要介護認定。障害福祉サービス利用のために障害者手帳取得
9 障害者特例と障害年金
10 雇用保険の基本手当受給時には年金の選択も再検討
11 就職
12 65歳時に複数の年金受給権利があれば年金事務所で受給方法の再検討を
第4章 病気の後遺症による障害
事例4 脳出血が原因で半身不随
1 休職に向けて
2 ソーシャルワーカーと面談。困ったときにはいろいろな制度がある
3 医療費が高額になりそうなときには、まずは高額療養費・限度額適用認定証の申請
4 就労不能の病状が続くようなら傷病手当金受給の検討を
5 1年6か月までは傷病手当金。それ以降は障害年金?
6 年齢が若くても病気の種類によっては要介護認定が受けられる可能性も
7 退院に向けて、自宅の環境整備を
8 身体障害者手帳の取得のメリット
9 退院そして新しい生活へ
10 新しい生活は本人も家族も手探りに。うまくいかないことも多い
11 退職後の傷病手当金を受給する際の注意点
12 デイサービスの利用
13 介護保険の利用
14 障害年金の申請
15 雇用保険の基本手当は退職後1 年以内に受給終了しなければいけないの?
16 受給期間延長の申請と就職困難者
17 障害者雇用で再就職
第5章 家族の介護が必要な状態になったら
事例5 親が認知症で要介護状態
1 まずは相談
2 介護休業補償をまずは利用して介護の環境を整えよう
3 介護保険を利用するためには要介護認定を受けよう
4 介護計画書(ケアプラン)作成
5 清子さんの認知症状が悪化
6 悪化時には区分変更の申請、サービス量を増やして対応
7 家族が疲弊しているときにはショートステイの利用を検討
8 介護計画書(ケアプラン)の再検討。在宅か? 施設か?
9 本人と家族の想い
10 ぎりぎりの生活
11 経済的負担の軽減策はないか
12 清子さんが心筋梗塞発症、糖尿病悪化
13 医療措置が必要な人には、介護施設ではなく介護医療院がある
14 介護医療院
第6章 老後の生活と社会保障
事例6 定年退職
1 給料が減った場合には高年齢雇用継続給付が利用できる
2 年金事務所では将来の年金額の試算ができる
3 年金を早く受給できる繰上げ請求はデメリットがある
4 厚生年金に加入して働きながら年金を受給すると年金額が減る場合がある
5 60代前半の老齢厚生年金は繰下げできない
6 障害者特例の対象ではないか確認
7 障害年金の受給の可能性
8 社会保険労務士に相談
9 障害年金と老齢年金と雇用保険
10 障害状態の悪化。障害年金の額改定請求
11 65歳以降。老齢年金と障害年金
12 一定の障害がある場合、75歳前に後期高齢者医療制度に加入できる
13 基本手当と老齢年金の併給ができる場合
第7章 失業に対する社会保障
事例7 会社が倒産
1 雇用保険の基本手当(通称:失業保険)をすぐに受給するために
2 社会保険料の支払いができない
3 国民年金保険料の特例免除、市区町村国保の保険料減免
4 賃貸住宅の家賃は住宅確保給付金を利用
5 マイホームローンも相談しよう:弁護士や司法書士などに相談する場合は法テラスの利用
6 倒産前の給料をもらっていない場合、未払賃金立替払制度が利用できるかも
7 雇用保険の基本手当受給中に入院。そんなときは傷病手当と高額療養費
8 健康第一!
9 職業訓練を受けると基本手当の受給期間が延長される!
第8章 配偶者の死亡による母子・父子家庭への社会保障
事例8 夫が死亡 残された妻子
1 どんな制度があるのか役所で相談してみよう
2 仕事中の事故が原因の場合、労働者災害補償保険、遺族補償年金の受給ができる
3 公的年金から遺族年金の受給。遺族年金は遺族厚生年金と遺族基礎年金がある
4 公的なお金は同時受給できないことがある!?
5 死亡時に厚生年金に加入していなくても遺族厚生年金を受給できる場合がある(姉の夫の場合)
6 30歳未満の子のない妻は遺族厚生年金が受給できる期間が短い!?
7 障害厚生年金を受給している人がなくなった場合の遺族年金(いとこの場合)
8 子どもの障害の有無も遺族年金の受給期間などを左右することがある
9 母子家庭への支援制度
10 母子家庭には医療費助成や資金の貸し付けもある
11 子どもの学用品や給食費に対する支援:就学援助制度
12 母子家庭の就労相談はハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターでもできる
13 高等職業訓練促進給付金
14 一人親家庭等日常生活支援事業
第9章 障害のある子への社会保障