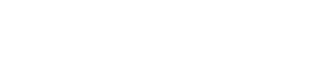法政策論への招待

販売価格: 2,200円 税込
- 数量
法学の組み換えにより、問題解決を図る
【目 次】
・はしがき
◆第1部 法による政策の決定◆
◆第1章 政策サイクルと法政策
〈問題が先か,政策が先か〉
1 人は政策サイクルをぐるぐる回す
2 立法/法改正をめぐる法と政策
3 政策サイクルの実際
4 政策科学での議論
5 政策アジェンダ
6 政策の窓
7 意図せざる結果
コラム 市民生活と法政策的思考 答えは42
◆第2章 社会的な意思決定
〈個々の合意か,集団的な決定か〉
1 人は決断から逃げられない
2 意思決定をめぐる法と政策
3 他の学問での扱い
4 法的な手順
5 法政策的思考の意義
6 連続的選択肢と政策決定
7 フットコストの最小化
コラム 市民生活と法政策的思考 ビュリダンのロバ
◆第3章 政策の決定方法(1) 多数決
〈多数の意見か,少数の人権か〉
1 人はとかく数に頼る
2 多数決をめぐる法と政策
3 メディアン・ボーター
4 ホテリング・モデル
5 実際の政治に即して
6 レファレンダム
7 人権をめぐる問題
コラム 市民生活と法政策的思考 日本の会議は全会一致
◆第4章 政策の決定方法(2) 討議
〈公共的討議か,利害の衝突か〉
1 人にはウラオモテがある
2 討議をめぐる法と政策
3 熟 議 論
4 共和主義と多元主義
5 代表の難しさ
6 本音と建て前
7 政党の役割
コラム 市民生活と法政策的思考 野球よりサッカー
◆第5章 政策の策定・評価基準
〈パレート基準か,カルドア・ヒックス基準か〉
1 人はより「まし」を目指す
2 権限をめぐる法と政策
3 パレート基準とは
4 パレート基準の実現性
5 パレート基準と公平性
6 カルドア・ヒックス基準とは
7 カルドア・ヒックス基準の難点
コラム 市民生活と法政策的思考 虎に食われる
◆第6章 公私の二区分
〈プライベートか,パブリックか〉
1 人は複素数の世界を生きる
2 公私をめぐる法と政策
3 公私の二分論の意義
4 複素数的なイメージ
5 ミクロの権力論
6 憲法の私人間効力の問題
7 市民社会に残存する倫理性
コラム 市民生活と法政策的思考 アイドルの恋愛禁止ルール
◆第7章 公共財の提供
〈市場の失敗か,政府の失敗か〉
1 人はいつだって「もっと欲しい」
2 公共財をめぐる法と政策
3 公共財をどこまで提供するか
4 社会的費用の最小化
5 価 値 財
6 分配問題への対応
7 モデルの一般的拡張
コラム 市民生活と法政策的思考 ビールは1杯目が一番うまい
◆第8章 政策要求の宛先・ルート
〈裁判の提起か,投票箱か〉
1 人は誰かに文句をぶつける
2 三権分立をめぐる法と政策
3 裁判に訴える方法
4 訴訟要件
5 政策志向型訴訟/紛争志向型訴訟
6 裁判当事者の責任
7 政策の担い手
コラム 市民生活と法政策的思考 東洋的な立憲主義は存在しない
◆第9章 改革と修正
〈抜本的改革か,部分的修正か〉
1 人は革命を夢見て戸惑う
2 改革をめぐる現行法と政策
3 対症療法の意義
4 本質還元主義
5 増分主義
6 根治療法の意義
7 戦略的な観点
コラム 市民生活と法政策的思考 世直しと立て直し
◆第10章 政策選択と不確実性
〈効用最大化か,リスク回避か〉
1 人の一寸先は闇
2 リスクをめぐる現行法と政策
3 マクシミン戦略
4 微小確率の問題
5 相手方の想定と戦略
6 ゲーム論的な駆け引き
7 危険効用基準
コラム 市民生活と法政策的思考 保険とのつき合い方
◆第2部 法による政策の実現◆
◆第11章 法政策と事前/事後
〈事前の予防か,事後の救済か〉
1 人は後講釈の名人
2 事前/事後をめぐる現行法と政策
3 社会的な位置づけと傾向
4 事前/事後の政策の比較
5 事前への拡張
6 事後への拡張
7 リスク・アプローチとポピュレーション・アプローチ
コラム 市民生活と法政策的思考 祭りの前と,あとの祭り
◆第12章 サンクションのタイポロジー
〈インセンティブか,サンクションか(その1)〉
1 人は賞罰で動く
2 賞罰をめぐる現行法と政策
3 刑 事 罰
4 オーバー・サンクション問題
5 行政刑罰
6 サンクションのバリエーション
7 民事責任の活用
コラム 市民生活と法政策的思考 サンクション中毒にご用心
◆第13章 インセンティブのタイポロジー
〈インセンティブか,サンクションか(その2)〉
1 人は賞罰に右往左往する
2 褒賞をめぐる現行法と政策
3 税制優遇
4 インセンティブのバリエーション
5 双方向的な効果を有する場合
6 法的効果を伴わない規範の意味
7 成功報酬・出来高払
コラム 市民生活と法政策的思考 罰金はお値段だ
◆第14章 選択のタイポロジー
〈集中させるか,分散させるか〉
1 人は法を横目で見る
2 契約自由をめぐる現行法と政策
3 任意規定の補充的な機能
4 秩序付け機能
5 情報流通・交渉促進的な機能
6 最安価費用回避者
7 自己選択
コラム 市民生活と法政策的思考 鉄の斧を選ぶ
◆第15章 強制のタイポロジー
〈制度か,強制か〉
1 人は制度の中で生きる
2 強制をめぐる現行法と政策
3 制度をめぐって
4 制度の画一的要件
5 画一性の意味合い
6 画一的取扱による公平性
7 作為と自然
コラム 市民生活と法政策的思考 自由の限界効用も逓減する
◆第16章 統一性のタイポロジー
〈一律か,個別の裁量か〉
1 人はわざとあいまいにできる
2 準則をめぐる現行法と政策
3 裁量とその統制
4 通達行政・行政指導
5 ストリートレベル官僚
6 地方公共団体の裁量
7 自治体の独自性
コラム 市民生活と法政策的思考 いい加減・良い加減
◆第17章 基準のタイポロジー
〈最低基準か,あるべき値か〉
1 人は〆切にあわせて動く
2 基準をめぐる現行法と政策
3 推奨される高い基準
4 最低以下のもう一つの基準
5 分離型均衡の可能性
6 例外規定,適用除外
7 直接の法的効果を伴わない基準
コラム 市民生活と法政策的思考 世界に線を引く
◆第18章 法政策と因果関係
〈因果関係か,相関関係か〉
1 人はいつも錯覚する
2 因果関係をめぐる現行法と政策
3 見せかけの因果関係
4 下支え効果
5 統計的な手法の活用
6 事後確率,偽陰性・偽陽性
7 アウトプットとアウトカム
コラム 市民生活と法政策的思考 今ここにいる不思議
◆第3部 学問としての法政策論◆
◆第19章 法政策論とは何か
〈立法論か,法政策論か〉
1 人は法と政策の間を生きる
2 法政策なるもの
3 政策論と法政策論
4 政策と法の間合い
5 法解釈の役割と限界
6 法学の目的と立法論
7 立法論と法政策論の違い
コラム 市民生活と法政策的思考 平和の王国
◆第20章 法政策論・余滴
〈法政策学か,法政策論か〉
1 人は未来に向かう
2 法政策学の構想
【目 次】
・はしがき
◆第1部 法による政策の決定◆
◆第1章 政策サイクルと法政策
〈問題が先か,政策が先か〉
1 人は政策サイクルをぐるぐる回す
2 立法/法改正をめぐる法と政策
3 政策サイクルの実際
4 政策科学での議論
5 政策アジェンダ
6 政策の窓
7 意図せざる結果
コラム 市民生活と法政策的思考 答えは42
◆第2章 社会的な意思決定
〈個々の合意か,集団的な決定か〉
1 人は決断から逃げられない
2 意思決定をめぐる法と政策
3 他の学問での扱い
4 法的な手順
5 法政策的思考の意義
6 連続的選択肢と政策決定
7 フットコストの最小化
コラム 市民生活と法政策的思考 ビュリダンのロバ
◆第3章 政策の決定方法(1) 多数決
〈多数の意見か,少数の人権か〉
1 人はとかく数に頼る
2 多数決をめぐる法と政策
3 メディアン・ボーター
4 ホテリング・モデル
5 実際の政治に即して
6 レファレンダム
7 人権をめぐる問題
コラム 市民生活と法政策的思考 日本の会議は全会一致
◆第4章 政策の決定方法(2) 討議
〈公共的討議か,利害の衝突か〉
1 人にはウラオモテがある
2 討議をめぐる法と政策
3 熟 議 論
4 共和主義と多元主義
5 代表の難しさ
6 本音と建て前
7 政党の役割
コラム 市民生活と法政策的思考 野球よりサッカー
◆第5章 政策の策定・評価基準
〈パレート基準か,カルドア・ヒックス基準か〉
1 人はより「まし」を目指す
2 権限をめぐる法と政策
3 パレート基準とは
4 パレート基準の実現性
5 パレート基準と公平性
6 カルドア・ヒックス基準とは
7 カルドア・ヒックス基準の難点
コラム 市民生活と法政策的思考 虎に食われる
◆第6章 公私の二区分
〈プライベートか,パブリックか〉
1 人は複素数の世界を生きる
2 公私をめぐる法と政策
3 公私の二分論の意義
4 複素数的なイメージ
5 ミクロの権力論
6 憲法の私人間効力の問題
7 市民社会に残存する倫理性
コラム 市民生活と法政策的思考 アイドルの恋愛禁止ルール
◆第7章 公共財の提供
〈市場の失敗か,政府の失敗か〉
1 人はいつだって「もっと欲しい」
2 公共財をめぐる法と政策
3 公共財をどこまで提供するか
4 社会的費用の最小化
5 価 値 財
6 分配問題への対応
7 モデルの一般的拡張
コラム 市民生活と法政策的思考 ビールは1杯目が一番うまい
◆第8章 政策要求の宛先・ルート
〈裁判の提起か,投票箱か〉
1 人は誰かに文句をぶつける
2 三権分立をめぐる法と政策
3 裁判に訴える方法
4 訴訟要件
5 政策志向型訴訟/紛争志向型訴訟
6 裁判当事者の責任
7 政策の担い手
コラム 市民生活と法政策的思考 東洋的な立憲主義は存在しない
◆第9章 改革と修正
〈抜本的改革か,部分的修正か〉
1 人は革命を夢見て戸惑う
2 改革をめぐる現行法と政策
3 対症療法の意義
4 本質還元主義
5 増分主義
6 根治療法の意義
7 戦略的な観点
コラム 市民生活と法政策的思考 世直しと立て直し
◆第10章 政策選択と不確実性
〈効用最大化か,リスク回避か〉
1 人の一寸先は闇
2 リスクをめぐる現行法と政策
3 マクシミン戦略
4 微小確率の問題
5 相手方の想定と戦略
6 ゲーム論的な駆け引き
7 危険効用基準
コラム 市民生活と法政策的思考 保険とのつき合い方
◆第2部 法による政策の実現◆
◆第11章 法政策と事前/事後
〈事前の予防か,事後の救済か〉
1 人は後講釈の名人
2 事前/事後をめぐる現行法と政策
3 社会的な位置づけと傾向
4 事前/事後の政策の比較
5 事前への拡張
6 事後への拡張
7 リスク・アプローチとポピュレーション・アプローチ
コラム 市民生活と法政策的思考 祭りの前と,あとの祭り
◆第12章 サンクションのタイポロジー
〈インセンティブか,サンクションか(その1)〉
1 人は賞罰で動く
2 賞罰をめぐる現行法と政策
3 刑 事 罰
4 オーバー・サンクション問題
5 行政刑罰
6 サンクションのバリエーション
7 民事責任の活用
コラム 市民生活と法政策的思考 サンクション中毒にご用心
◆第13章 インセンティブのタイポロジー
〈インセンティブか,サンクションか(その2)〉
1 人は賞罰に右往左往する
2 褒賞をめぐる現行法と政策
3 税制優遇
4 インセンティブのバリエーション
5 双方向的な効果を有する場合
6 法的効果を伴わない規範の意味
7 成功報酬・出来高払
コラム 市民生活と法政策的思考 罰金はお値段だ
◆第14章 選択のタイポロジー
〈集中させるか,分散させるか〉
1 人は法を横目で見る
2 契約自由をめぐる現行法と政策
3 任意規定の補充的な機能
4 秩序付け機能
5 情報流通・交渉促進的な機能
6 最安価費用回避者
7 自己選択
コラム 市民生活と法政策的思考 鉄の斧を選ぶ
◆第15章 強制のタイポロジー
〈制度か,強制か〉
1 人は制度の中で生きる
2 強制をめぐる現行法と政策
3 制度をめぐって
4 制度の画一的要件
5 画一性の意味合い
6 画一的取扱による公平性
7 作為と自然
コラム 市民生活と法政策的思考 自由の限界効用も逓減する
◆第16章 統一性のタイポロジー
〈一律か,個別の裁量か〉
1 人はわざとあいまいにできる
2 準則をめぐる現行法と政策
3 裁量とその統制
4 通達行政・行政指導
5 ストリートレベル官僚
6 地方公共団体の裁量
7 自治体の独自性
コラム 市民生活と法政策的思考 いい加減・良い加減
◆第17章 基準のタイポロジー
〈最低基準か,あるべき値か〉
1 人は〆切にあわせて動く
2 基準をめぐる現行法と政策
3 推奨される高い基準
4 最低以下のもう一つの基準
5 分離型均衡の可能性
6 例外規定,適用除外
7 直接の法的効果を伴わない基準
コラム 市民生活と法政策的思考 世界に線を引く
◆第18章 法政策と因果関係
〈因果関係か,相関関係か〉
1 人はいつも錯覚する
2 因果関係をめぐる現行法と政策
3 見せかけの因果関係
4 下支え効果
5 統計的な手法の活用
6 事後確率,偽陰性・偽陽性
7 アウトプットとアウトカム
コラム 市民生活と法政策的思考 今ここにいる不思議
◆第3部 学問としての法政策論◆
◆第19章 法政策論とは何か
〈立法論か,法政策論か〉
1 人は法と政策の間を生きる
2 法政策なるもの
3 政策論と法政策論
4 政策と法の間合い
5 法解釈の役割と限界
6 法学の目的と立法論
7 立法論と法政策論の違い
コラム 市民生活と法政策的思考 平和の王国
◆第20章 法政策論・余滴
〈法政策学か,法政策論か〉
1 人は未来に向かう
2 法政策学の構想