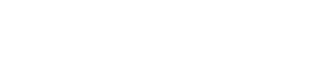メンタルヘルス不調による休職・復職の実務と規程 ~試し勤務を紛争予防策として活用するために

販売価格: 2,640円 税込
- 数量
- 著者
- 柊木野一紀・編著 佐々木規夫/染村宏法/山本 愛/盛 太輔/安藤源太/田中朋斉・著
- 発行元
- 日本法令
- 発刊日
- 2022-12-20
- ISBN
- 978-4-539-72939-7
- CD-ROM
- 無し
- サイズ
- A5判 (208ページ)
メンタル休職をした従業員の労務管理上の困難として、いったん復職した後に再び悪化し、休職・復職を繰り返してしまう問題がある。
特に休職期間満了が間近くなると、復職を焦る従業員との間で復職可否をめぐってトラブルになりやすく、コロナ禍でのリモートワークの普及により、一層判断が難しくなっている。
本書では、こうしたトラブルを予防するための試し勤務の設計、活用について、規程例や書式例を示しながら弁護士と産業医が解説。
目次
第1章 メンタルヘルス不調の従業員の労務管理が困難なのはなぜか
1-1 メンタルヘルス不調者に関する実態
1-2 メンタルヘルス不調の従業員の労務管理の難しさ
1-3 企業担当者と医療関係者(主治医・産業医)との意識の違い(治癒の多義性)
1-4 企業担当者・産業医と主治医との意識の違い
1-4-1 主治医の診断書の意味
1-4-2 認識の不一致が生じる背景
1-5 主治医と産業医の意識の違い(役割と従業員情報へのアクセスの違い)
1-6 復職判断に向けた医学的エビデンスの充実~試し勤務規程等の必要性
1-6-1 産業医に寄せられる期待
1-6-2 実際に産業医が実務で直面する課題
1-6-3 医学的エビデンス獲得に向けた措置
1-6-3-1 受診命令権を規定する
1-6-3-2 試し勤務及び通勤訓練に関する規程
1-6-3-3 その他
第2章 休職編
2-1 はじめに
2-2 メンタルヘルス不調者対応で必要となる基礎知識
2-2-1 精神疾患の治療経過
2-2-1-1 急性期
2-2-1-2 回復期
2-2-1-3 再発予防期
2-2-2 精神疾患とは
2-2-3 精神疾患の種類と症状
2-2-4 精神疾患はどのように診断される?
2-2-4-1 精神疾患を扱う医療機関
2-2-4-2 精神疾患の診断方法
2-2-5 精神疾患の治療
2-2-6 主な精神疾患の特徴と治療
2-2-6-1 うつ病
2-2-6-2 適応障害
2-2-6-3 双極性障害(躁うつ病)
2-2-6-4 不安障害(神経症性障害)
2-2-6-5 統合失調症
2-2-6-6 アルコール依存症
2-2-6-7 発達障害
2-2-6-8 心身症
2-2-6-9 自律神経失調症
2-3 欠勤・休職に関するモデル規定と解説
2-3-1 遅刻、早退及び欠勤に関する承認制を定めた規定例
2-3-2 遅刻、早退及び欠勤等に関して医師の診断書の提出を求める規定例
2-3-3 休職事由
2-3-4 休職期間
2-3-5 休職期間中の給与等の待遇
2-3-6 休職期間満了時の手続き
2-3-7 休職期間の通算
2-4 欠勤・休職に関する実務Q&A
2-4-1 受診指示に応じない場合の対応
2-4-2 自宅療養で療養環境を確保するための対応
2-4-2-1 安全配慮義務の意義・根拠・範囲(自宅療養に安全配慮義務が及ぶか)
2-4-2-2 自宅療養に対する実務対応
2-4-2-3 健康情報を同意なく家族に伝えてよいか(個人情報保護法、プライバシーとの関係)
2-4-3 休職する従業員の担当業務の処理・引継ぎの進め方
2-4-3-1 ポイント1 引継ぎは、短時間&短期間を原則とし、必要最小限にとどめる
2-4-3-2 ポイント2 引継ぎ場面には、引き継ぐ従業員だけでなく、業務を理解している人も同席するのがよい
2-4-3-3 ポイント3 引継ぎ後は、原則として業務の連絡は行わない。追加の引継ぎが必要な場合の連絡方法や関係者への連絡についても了承を得る
2-4-4 休職に入る従業員が在宅勤務の場合の貸与パソコンの取扱い
2-4-5 休職中の従業員への連絡方法
2-4-6 傷病手当金をめぐる対応
2-4-6-1 傷病手当金と給与の関係
2-4-6-2 傷病手当金と退職
2-4-6-3 傷病手当金と労災
2-4-7 休職期間中に主治医と接触する場合の対応
2-4-7-1 休職期間中の私傷病の診療関係書類作成費用、医療相談費用の負担関係
2-4-7-2 主治医との面談を秘密録音することの可否、証拠能力、実務対応
2-4-8 欠勤・休職に関する規定をめぐるQ&A
2-4-8-1 通算規定の設計(通算対象・通算期間)
2-4-8-2 回復可能性がない場合における休職の要否
2-4-9 メンタルヘルス不調に起因する問題行動が見られる従業員への対応
第3章 復職編
3-1 はじめに
3-2 休職期間満了時の規定を確認する
3-3 復職準備チェックシートを使って準備する
3-3-1 復職に向けた準備の必要性
3-3-1-1 職場復帰前の準備は、再発予防に重要である
3-3-1-2 復職準備チェックシートを活用して回復の程度をみる
3-3-2 復職の判断基準を踏まえた復職準備チェックシートの利用方法
3-3-3 復職準備チェックシートの質問からわかること
3-3-3-1 基本的生活リズムや症状は十分に回復しているか
3-3-3-2 日中の眠気が業務遂行に影響しないか
3-3-3-3 判断力や集中力、合理的思考が回復しているか
3-3-3-4 治療継続に関する環境が整っているか
3-3-3-5 不調のサインに気づき、対処できるか
3-3-4 職場復帰の成否の大半は復帰前に決まっている
3-4 復職判断に関する実務Q&A
3-4-1 復職可能との診断書が提出された場合の対応
3-4-2 職種や業務限定特約がある場合の復職の判断基準
3-4-3 主治医の診断書が提出された場合の対応
3-4-4 「 程なく治癒する見込み」との主治医の診断書が提出された場合の対応(エール・フランス事件、独立行政法人N事件)
3-4-5 休職事由消滅の立証責任は誰にあるか
3-4-6 障害者雇用促進法における合理的配慮義務と復職可否の判断
3-4-6-1 精神疾患により休職する従業員は合理的配慮の対象となる「障害者」に当たるか
3-4-6-2 精神疾患により休職していた従業員が復職するにあたり使用者に求められる合理的配慮の提供義務
第4章 試し勤務・通勤訓練編
4-1 試し勤務、通勤訓練とは
4-2 試し勤務制度に関するモデル規定と解説
4-2-1 目 的
4-2-2 対象者等
4-2-3 適用期間
4-2-4 試し勤務の計画
4-2-5 試し勤務時の待遇(指揮命令を受ける場合)
4-2-6 実施に関する手続き
4-2-7 試し勤務の内容
4-2-8 試し勤務の実施状況把握等
4-2-9 中 止
4-2-10 復職判断
4-3 通勤訓練に関するモデル規定と解説
4-3-1 目 的
4-3-2 対象者等
4-3-3 適用期間
4-3-4 実施に関する手続き
4-3-5 訓練内容
4-3-6 実施状況の報告
4-3-7 中 止
4-3-8 待遇・費用等の留意事項
4-3-9 復職判断
4-4 試し勤務実施に関する実務Q&A
4-4-1 試し勤務期間中に従事させる業務
4-4-2 試し勤務中の賃金、無給扱いの可否
第5章 テレワーク編(復職判断や試し勤務が受ける影響等を中心に)
5-1 テレワークをめぐる労働契約上の混乱
5-2 テレワークにおける労務管理・健康管理に関する実務Q&A
5-2-1 テレワークにおける部下のマネジメント
5-2-2 テレワーク勤務における健康問題
5-2-3 テレワーク勤務における労働環境整備
5-2-4 テレワーク勤務者が休職するときの会社貸与パソコンの取扱い
5-3 テレワークの制度設計に関する実務Q&A
5-3-1 テレワークの最適な制度設計の必要性と労働契約上の位置づけ
5-3-2 労働契約上の位置づけが明らかにされていない場合(図表15 ①)のテレワーク命令権・テレワーク就業請求権
5-3-3 戦略的なテレワークの制度設計
5-3-4 テレワーク命令権・テレワーク就労請求権を導入する際の手続き上の留意点
5-4 テレワークと私傷病休職からの復職に関する実務Q&A
5-5 私傷病休職とテレワークに関する実務Q&A
5-5-1 問題の所在
5-5-2 従業員の負担軽減やワーク・ライフ・バランスの向上目的をも有する制度として導入している場合
5-5-3 臨時的な就労形態としてテレワークを事実上実施した場合(図表15 ①)及び臨時的な就労形態として労働契約上位置づけて制度を導入した場合(図表15 ②)
5-6 テレワークでの復職判断・試し勤務のあり方に関する実務Q&A
5-6-1 テレワークでの復職判断
5-6-2 テレワーク下での回復の程度の評価
5-7 復職後等におけるテレワーク勤務