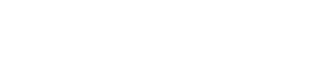学校法務 公教育を担う法務実務の視点と論理

販売価格: 2,420円 税込
- 数量
「学校法務」の在り方に迫るためには、その前提として、学校における教育問題、教員組織、教育行政の状況〈教育・学校等の特質〉、現代の学校の教育活動を支える制度システムの現状とその変容の状況〈制度システムの状況〉、法務実務の担い手である弁護士等の職務の状況とその動向〈法務実務の状況〉等について確認する必要がある。
学校教育問題における弁護士などの法律専門家の役割がクローズアップされるようになり、弁護士の学校問題への関わり方が重要な争点として浮上している。確かに、学校に関する紛争処理における法律専門家のニーズが高まっていると言えるが、その一方で、弁護士の関与によって、必ずしも、学校問題の真の解決、「子どもの最善の利益」の実現に結びついていないのではないかという疑問も呈されている。
本書は、「学校法務」という言葉を提起している。これは、学校教育や学校の抱える諸課題に関する法務実務という意味にとどまらず、公教育、学校教育に関わる上での法務実務はどうあればよいかという議論に応えようとするものである。本書では、「学校法務」を考える上での視点と論理、「学校法務」をめぐる法制の変化とそれを特徴づける法概念の検討、弁護士の活用が拡大するなかで、その活用上必要とされる基礎的な知識、近年整備されつつあるスクールロイヤーの制度の実態とスクールロイヤーが担うべき役割や機能、現代における多様な法的教育課題において弁護士に期待される役割について検討する。これらの検討を通じて、「学校法務」の概念の形成について示唆を得ようとするものである。
目 次
第1章 学校法務
第1節 学校教育における法務実務への注目
第2節 「学校法務」という考え方
第2章 学校法務をめぐる法制の変化と法概念の展開
第1節 学校教育をめぐる法制とアプローチの多様化 ―基盤としての教育基本法制と浸透する権利条約法制―
第2節 「子どもの最善の利益」の概念の法的、実践的な意義
第3節 紛争対応における「修復的正義」の萌芽とその可能性
第4節 社会的コミュニケーションの契機として「合理的配慮」の概念
第5節 参加に向けた法的整備と参加のための原理の適用
第3章 弁護士の活用に向けた基礎的理解
第1節 弁護士活用のメリット
第2節 弁護士の活用に向けて
第3節 弁護士の費用
第4節 訴訟保険
第5節 弁護士へのつながり方
第6節 弁護士倫理
第7節 弁護士の守秘義務
第8節 弁護士の誠実義務と真実義務
第9節 弁護士の活用と利益相反
第10節 組織内の法曹有資格者の活用
第11節 弁護士のチーム
第4章 スクールロイヤーの登場とその機能
第1節 教育委員会・学校における法務相談体制の状況
第2節 先行するスクールロイヤーの制度と職務の標準化
第3節 スクールロイヤーの公共性
第4節 チーム学校と弁護士
第5節 スクールロイヤーと臨床の視点 ―教育と福祉の連携―
第6節 「行政領域」「専門職種」の壁を超える機能
第7節 課題としてのアドボカシー、司法面接、メディエーション
第5章 現代における法的教育課題と弁護士の役割
第1節 いじめ問題と弁護士
第2節 第三者調査委員会の役割と弁護士
第3節 現代における学校事故対応と弁護士
第4節 少年事件と弁護士
第5節 ICT環境の変化と弁護士
第6節 保護者からの諸要求への対応
第7節 親権・監護権への対応と弁護士
第8節 教員個人を対象とした責任追及と弁護士
第9節 最新の裁判動向を踏まえた危機管理対応と弁護士
第10節 自治体・教育委員会の政策形成機能と弁護士
第11節 医療的ケア児支援法による医療的ケアの本格的な導入と弁護士
補論 「学校法務」の展開に向けて ~学校教育の制度システムの変動~