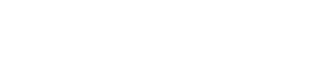よりよい相続のために!! 相続 手続・申告シンプルガイド(令和6年改訂版)
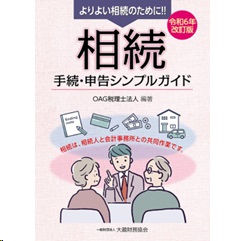
販売価格: 2,640円 税込
- 数量
相続税の申告は、所得税の確定申告のように毎年発生するものではないため、通常は馴染みの薄いものです。そのため、相続人には、ご自身が相続税の申告が必要なのかどうか、また、相続税はかかるのか、かかるとしたら手元の資金で払えるのか等々、心配されている方も多いと思います。本書は、相続が生じた場合の手続きから相続財産の評価、相続税の申告に至るまで、その手順について、相続人のみならず、相続人からご相談を受ける会計事務所・税理士事務所の皆様にも参考としていただけるよう構成したシンプルなガイドブックです。
主要目次
プロローグ
1 相続とは?
(1)相続人
(2)相続財産
2 相続があったら何をしなければならないか?
(1)遺言の確認4
公正証書遺言/自筆証書遺言(保管制度の利用あり)/自筆証書遺言(保管制度の利用なし)及び秘密証書遺言
(2)各種手続き
遺産分割/金融機関などの名義変更・解約・払戻し/不動産の相続登記
(3)相続税の申告
相続税の申告義務/相続税の申告期限
3 相続の専門家に相談するには?
相続の専門家とは?/専門家はどうやって探す?
第1編 申告書を作成する前に―相続人対応編―
1 相続人・相続分を調べよう
1-1 相続人の調査
(1)必要となる資料
基礎資料/兄弟姉妹が相続人となる場合に必要な資料/代襲相続が生じている場合
(2)具体的な戸籍の収集のしかた
(3)戸籍の種類
(4)相続人関係図を作成する
1-2 民法の規定をチェック
(1)法定相続人
相続人と相続順位
(2)法定相続分を理解しよう
法定相続分の計算
(3)代襲相続ってなに?
代襲相続の可否/孫が代襲相続人になるケース/甥、姪が代襲相続人になるケース
(4)相続人になれない人もいる!?
2 財産・債務を調べよう
2-1 財産を調べよう
(1)不動産の把握・所在確認
「固定資産税の納税通知書」を確認する/「名寄帳」を取得する/「固定資産評価証明書」も取得しておこう/権利証、売買契約書等の不動産関連資料の確認
【コラム 相続により取得した土地を国に帰属させることができる】
(2)登記事項証明書等の取得
登記所の窓口で取得する方法/郵送で取得する方法/インターネットを利用して取得する方法/登記情報提供サービスの活用
(3)「法定相続情報証明制度」の活用
「法定相続情報証明制度」を活用するメリット/「法定相続情報証明制度」を利用するための注意点/「法定相続情報証明制度」を利用する手続きの流れ
(4)金融資産を調べよう
預貯金の調査/残高証明書の発行手続き/預貯金口座の有無の確認/現存照会の手続き/インターネット銀行の調査/預貯金の取引履歴/株式・有価証券の調査/名義財産(名義預金、名義株等)/金融機関への相続発生後の手続きの流れ
【コラム 亡くなったことがわかると預金は凍結されてしまう】
(5)各種保険の調査
(6)退職金・弔慰金の調査
死亡退職金の取扱い/弔慰金の取扱い
2-2 債務を調べよう
(1)債務
銀行からの借入金の調査/銀行以外の借金の調査/未払金の調査/預り敷金の調査
(2)葬式費用
2-3 財産目録の作成
財産目録の意義
2-4 財産調査資料と相続税申告に必要な書類の関連性
3 申告の要否判定
3-1 判定の流れと基礎控除
基礎控除額の計算
3-2 法定相続人の数
相続税法上の法定相続人の数
【コラム 「法定相続人の数」を使う場面】
3-3 遺産総額の計算
(1)遺産総額の算式
遺贈とは/相続税のかかる財産/相続税のかからない財産/債務/葬式費用
【コラム 遺贈の種類】
(2)財産(遺産)の価額と評価
金融資産の価額/土地の評価額/家屋の評価額/その他の財産の価額
【コラム 土地は一物四価】
3-4 申告要否の判定シート
4 申告要否の目途がついたら(財産の評価と特例適用の可否判断)
遺産額が基礎控除額を大幅に下回っている場合/遺産額が基礎控除額を少し下回っている場合/遺産額が基礎控除額を少し上回っている場合、または大きく上回っている場合
第2編 財産評価、税制上の特例―専門家対応編―
1 財産の評価
1-1 はじめに
1-2 土地の評価(評価区分)
1-3 土地の評価(宅地の評価単位)
1筆の土地上でも2つの画地として評価する場合/2つの宅地を合わせて1画地として評価する場合
【コラム 使用貸借とは?】
1-4 土地の評価(宅地の評価方法の概要)
路線価方式/倍率方式
【コラム なぜ宅地の倍率は固定資産税評価額の1.1倍?】
1-5 土地の評価(専門家による宅地の評価)
資料収集/道路調査/道路種別とは?/現地調査
1-6 土地の評価(路線価を使った自用地の評価)
土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31年1月分以降用)
(1)1路線に面している宅地の評価
(2)角地(正面と側方に道路がある宅地)の評価
(3)正面と裏面に道路がある宅地の評価
(4)間口が狭小等な宅地、不整形地の評価
間口が狭小な宅地の評価/奥行が長大な宅地の評価/間口が狭小で奥行が長大な宅地の評価/不整形地の評価
(5)私道の評価
一般的な私道の評価/特定路線価を申請する場合の私道の評価
(6)マンションの敷地
従前の評価方法/令和6年1月1日以後に相続が発生した場合の評価方法
1-7 土地の評価(宅地の利用形態による評価)
自用地/借地権/貸宅地/貸家建付地
【コラム 借地契約書がなかったら?】
1-8 家屋等の評価
(1)家屋
自用家屋/区分所有建物/貸家・アパート
(2)附属設備等
家屋と構造上一体となっている設備/門、塀等の設備/庭園設備
(3)構築物
1-9 現金・預貯金の評価
(1)現金
(2)預貯金
普通預金、通常貯金等/定期預金、定期郵便貯金等/外貨預金
1-10 有価証券の評価
(1)上場株式
配当期待権
(2)公社債(個人向け国債)
(3)証券投資信託受益証券
日々決算型のもの(中期国債ファンド、MMF等)/金融商品取引所に上場している証券投資信託/上場していない証券投資信託
1-11 生命保険金等の評価
(1)死亡保険金
課税対象金額/剰余金等の取扱い/契約者貸付金等の取扱い/生命保険金の非課税制度
(2)生命保険契約に関する権利
1-12 退職金や弔慰金の評価
死亡退職金/弔慰金/死亡退職金の非課税制度
1-13 家庭用財産やその他の財産の評価
家財一式/書画・骨董・宝石類/貴金属類(金・プラチナなど換金できるもの)/車両/ゴルフ会員権/未収入金
【コラム 故人の確定申告と相続税の関係】
2 贈与税のあらまし
2-1 暦年課税と相続時精算課税
贈与とは/贈与税のしくみ
(1)暦年課税
暦年課税の計算方法
(2)相続時精算課税
相続時精算課税の適用を受けるための要件/相続時精算課税の計算方法
【コラム 贈与税の申告内容の開示請求手続き】
2-2 暦年課税の生前贈与加算
(1)生前贈与加算とは
相続が発生した年の贈与税・相続税の取扱い/孫への贈与
【コラム 孫(養子縁組をしている場合など)への相続は2割加算】
3 相続税が軽減できる税制上の特例
3-1 はじめに
3-2 配偶者の税額軽減
(1)制度の概要
(2)適用要件
(3)適用時の留意点
3-3 小規模宅地等の特例
(1)制度の概要
【コラム 生計一親族とは?】
主要目次
プロローグ
1 相続とは?
(1)相続人
(2)相続財産
2 相続があったら何をしなければならないか?
(1)遺言の確認4
公正証書遺言/自筆証書遺言(保管制度の利用あり)/自筆証書遺言(保管制度の利用なし)及び秘密証書遺言
(2)各種手続き
遺産分割/金融機関などの名義変更・解約・払戻し/不動産の相続登記
(3)相続税の申告
相続税の申告義務/相続税の申告期限
3 相続の専門家に相談するには?
相続の専門家とは?/専門家はどうやって探す?
第1編 申告書を作成する前に―相続人対応編―
1 相続人・相続分を調べよう
1-1 相続人の調査
(1)必要となる資料
基礎資料/兄弟姉妹が相続人となる場合に必要な資料/代襲相続が生じている場合
(2)具体的な戸籍の収集のしかた
(3)戸籍の種類
(4)相続人関係図を作成する
1-2 民法の規定をチェック
(1)法定相続人
相続人と相続順位
(2)法定相続分を理解しよう
法定相続分の計算
(3)代襲相続ってなに?
代襲相続の可否/孫が代襲相続人になるケース/甥、姪が代襲相続人になるケース
(4)相続人になれない人もいる!?
2 財産・債務を調べよう
2-1 財産を調べよう
(1)不動産の把握・所在確認
「固定資産税の納税通知書」を確認する/「名寄帳」を取得する/「固定資産評価証明書」も取得しておこう/権利証、売買契約書等の不動産関連資料の確認
【コラム 相続により取得した土地を国に帰属させることができる】
(2)登記事項証明書等の取得
登記所の窓口で取得する方法/郵送で取得する方法/インターネットを利用して取得する方法/登記情報提供サービスの活用
(3)「法定相続情報証明制度」の活用
「法定相続情報証明制度」を活用するメリット/「法定相続情報証明制度」を利用するための注意点/「法定相続情報証明制度」を利用する手続きの流れ
(4)金融資産を調べよう
預貯金の調査/残高証明書の発行手続き/預貯金口座の有無の確認/現存照会の手続き/インターネット銀行の調査/預貯金の取引履歴/株式・有価証券の調査/名義財産(名義預金、名義株等)/金融機関への相続発生後の手続きの流れ
【コラム 亡くなったことがわかると預金は凍結されてしまう】
(5)各種保険の調査
(6)退職金・弔慰金の調査
死亡退職金の取扱い/弔慰金の取扱い
2-2 債務を調べよう
(1)債務
銀行からの借入金の調査/銀行以外の借金の調査/未払金の調査/預り敷金の調査
(2)葬式費用
2-3 財産目録の作成
財産目録の意義
2-4 財産調査資料と相続税申告に必要な書類の関連性
3 申告の要否判定
3-1 判定の流れと基礎控除
基礎控除額の計算
3-2 法定相続人の数
相続税法上の法定相続人の数
【コラム 「法定相続人の数」を使う場面】
3-3 遺産総額の計算
(1)遺産総額の算式
遺贈とは/相続税のかかる財産/相続税のかからない財産/債務/葬式費用
【コラム 遺贈の種類】
(2)財産(遺産)の価額と評価
金融資産の価額/土地の評価額/家屋の評価額/その他の財産の価額
【コラム 土地は一物四価】
3-4 申告要否の判定シート
4 申告要否の目途がついたら(財産の評価と特例適用の可否判断)
遺産額が基礎控除額を大幅に下回っている場合/遺産額が基礎控除額を少し下回っている場合/遺産額が基礎控除額を少し上回っている場合、または大きく上回っている場合
第2編 財産評価、税制上の特例―専門家対応編―
1 財産の評価
1-1 はじめに
1-2 土地の評価(評価区分)
1-3 土地の評価(宅地の評価単位)
1筆の土地上でも2つの画地として評価する場合/2つの宅地を合わせて1画地として評価する場合
【コラム 使用貸借とは?】
1-4 土地の評価(宅地の評価方法の概要)
路線価方式/倍率方式
【コラム なぜ宅地の倍率は固定資産税評価額の1.1倍?】
1-5 土地の評価(専門家による宅地の評価)
資料収集/道路調査/道路種別とは?/現地調査
1-6 土地の評価(路線価を使った自用地の評価)
土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表(平成31年1月分以降用)
(1)1路線に面している宅地の評価
(2)角地(正面と側方に道路がある宅地)の評価
(3)正面と裏面に道路がある宅地の評価
(4)間口が狭小等な宅地、不整形地の評価
間口が狭小な宅地の評価/奥行が長大な宅地の評価/間口が狭小で奥行が長大な宅地の評価/不整形地の評価
(5)私道の評価
一般的な私道の評価/特定路線価を申請する場合の私道の評価
(6)マンションの敷地
従前の評価方法/令和6年1月1日以後に相続が発生した場合の評価方法
1-7 土地の評価(宅地の利用形態による評価)
自用地/借地権/貸宅地/貸家建付地
【コラム 借地契約書がなかったら?】
1-8 家屋等の評価
(1)家屋
自用家屋/区分所有建物/貸家・アパート
(2)附属設備等
家屋と構造上一体となっている設備/門、塀等の設備/庭園設備
(3)構築物
1-9 現金・預貯金の評価
(1)現金
(2)預貯金
普通預金、通常貯金等/定期預金、定期郵便貯金等/外貨預金
1-10 有価証券の評価
(1)上場株式
配当期待権
(2)公社債(個人向け国債)
(3)証券投資信託受益証券
日々決算型のもの(中期国債ファンド、MMF等)/金融商品取引所に上場している証券投資信託/上場していない証券投資信託
1-11 生命保険金等の評価
(1)死亡保険金
課税対象金額/剰余金等の取扱い/契約者貸付金等の取扱い/生命保険金の非課税制度
(2)生命保険契約に関する権利
1-12 退職金や弔慰金の評価
死亡退職金/弔慰金/死亡退職金の非課税制度
1-13 家庭用財産やその他の財産の評価
家財一式/書画・骨董・宝石類/貴金属類(金・プラチナなど換金できるもの)/車両/ゴルフ会員権/未収入金
【コラム 故人の確定申告と相続税の関係】
2 贈与税のあらまし
2-1 暦年課税と相続時精算課税
贈与とは/贈与税のしくみ
(1)暦年課税
暦年課税の計算方法
(2)相続時精算課税
相続時精算課税の適用を受けるための要件/相続時精算課税の計算方法
【コラム 贈与税の申告内容の開示請求手続き】
2-2 暦年課税の生前贈与加算
(1)生前贈与加算とは
相続が発生した年の贈与税・相続税の取扱い/孫への贈与
【コラム 孫(養子縁組をしている場合など)への相続は2割加算】
3 相続税が軽減できる税制上の特例
3-1 はじめに
3-2 配偶者の税額軽減
(1)制度の概要
(2)適用要件
(3)適用時の留意点
3-3 小規模宅地等の特例
(1)制度の概要
【コラム 生計一親族とは?】