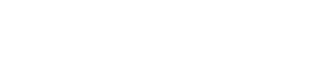ミスとリスクを徹底排除 消費税 簡易課税制度の実務(改訂版)

販売価格: 2,970円 税込
- 数量
インボイス制度の施行に伴う税額計算の特例(2割特例)終了後は、簡易課税適用事業者の一層の増加が見込まれます。2割特例及びその終了後の実務に関する解説、簡易課税制度の適用と事業区分判定に関するQ&Aを追加したほか、基本通達・経理通達の抜本改正、日本標準産業分類の改定に対応した大幅改訂版として、研修テキストにも最適。税額計算の手順や主要届出書の記載例を収録したほか、多様な業種名や取引が探しやすいよう索引も充実。
主要目次
第1編 消費税の概要
第1章 消費税の課税の対象
第1節 課税の対象となる国内取引
1 国内取引の課税の対象
2 事業者が事業として行う取引
3 対価を得て行う取引
4 資産の譲渡等
5 特定仕入れ
6 国内取引の判定基準
7 課税の対象にならない取引(不課税取引)
第2節 課税の対象となる輸入取引
1 課税の対象となる輸入取引
2 みなし引取り
第2章 非課税と免税
第1節 非課税
1 国内取引における非課税
2 輸入取引における非課税
第2節 免税
1 免税取引の範囲
2 非課税と免税の違い
第3章 納税義務者と納税義務の成立
第1節 納税義務者
1 国内取引の納税義務者
2 輸入取引の納税義務者
第2節 小規模事業者の納税義務の免除
1 小規模事業者の納税義務の免除とその特例
2 課税事業者の選択
3 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
4 相続等があった場合の納税義務の免除の特例
5 新設法人の納税義務の免除の特例
6 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
7 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
8 調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
第3節 納税義務の成立
1 国内取引
2 輸入取引
第4章 適格請求書発行事業者
第1節 適格請求書
1 適格請求書の記載事項
2 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理
第2節 適格請求書発行事業者の登録制度
1 登録手続
2 新規開業者の登録に関する特例
3 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の経過措置
4 適格請求書発行事業者の登録の取消し及び失効
〔参考〕特定非常災害とインボイス制度
第3節 適格請求書発行事業者の義務等
1 原則
2 適格請求書の交付義務が免除される場合
3 適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書を交付できる場合
4 適格請求書の写しの保存
第5章 課税標準と税率
第1節 課税標準と税率
1 国内取引の課税標準
2 輸入取引の課税標準
3 税率
第2節 課税標準額等の計算
1 課税標準額
2 課税標準額及び税額の計算(原則=総額割戻し方式)
3 インボイス制度開始後の適格請求書等積上げ方式(特例)
4 2割特例
第6章 税額控除等
第1節 仕入税額控除
1 課税仕入れ
2 課税仕入れの範囲
3 特定課税仕入れ
4 課税仕入れに係る消費税額の計算
5 特定課税仕入れに係る消費税額の計算
6 仕入税額控除の要件
第2節 仕入控除税額の計算方法
1 仕入控除税額の計算
2 課税売上割合とその計算
3 課税仕入れ等の税額の全額を控除できる場合
4 課税仕入れ等の税額の全額を控除できない場合
5 仕入対価の返還等を受けた場合の仕入控除税額の計算
6 調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整
第3節 簡易課税制度
1 簡易課税制度による場合の仕入控除税額の計算
2 簡易課税制度の適用要件
第4節 売上対価の返還等をした場合等の税額控除等
1 売上対価の返還等をした場合の税額控除
2 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の税額控除
3 貸倒れが生じた場合の税額控除等
第7章 課税期間、申告・納付、納税地
第1節 課税期間
1 個人事業者の課税期間
2 法人の課税期間
3 課税期間の特例
第2節 申告・納付
1 国内取引に係る申告と納付
2 輸入取引に係る申告と納付
第3節 納税地
1 国内取引の納税地
2 輸入取引の納税地
第8章 国等に対する特例
第1節 国等に対する特例の概要
1 事業単位の特例
2 資産の譲渡等の時期の特例
3 仕入税額控除の特例
4 一般会計の特例
5 申告期限の特例
第2節 仕入税額控除の特例
1 特定収入の意義
2 特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
3 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額の調整規定
第9章 雑則
1 届出書を提出しなければならない場合
2 承認・登録を受けなければならない場合
3 許可を受けなければならない場合
4 記帳義務
5 総額表示の義務
第2編 簡易課税制度
第1章 簡易課税制度の内容
第1節 簡易課税制度の特徴
1 一般課税との比較
2 インボイス制度と簡易課税制度
3 事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供を受けた場合
4 補助金等の収入がある場合
簡易課税制度の適用に関する事故事例
1 簡易課税制度を選択したことによる事故事例〔輸出免税の判断を誤ったケース〕
第2節 簡易課税制度を適用する場合、適用をやめる場合
1 簡易課税制度の適用
(1) 簡易課税制度の適用限度額
(2) 分割等の場合の適否判定
(3) 国外事業者に対する簡易課税制度の適用制限
(4) 簡易課税制度選択届出書の提出
(5) 事業を開始した日の属する課税期間等の特例
簡易課税制度選択届出書の効力発生時期としての「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」の意義
(6) 簡易課税制度選択届出書の効力の存続
イ 相続があった場合
ロ 合併等があった場合
簡易課税制度の適用に関する事故事例
2 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔新設法人を免税事業者と誤認したケース〕
3 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔特定期間の課税売上高による納税義務の判断を怠ったケ―ス〕
4 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔e-Tax運用停止中のケース〕
2 簡易課税制度の不適用
(1) 簡易課税制度選択不適用届出書の提出
(2) 不適用となる課税期間
(3) 不適用届出書の提出の制限(2年間の継続適用)
簡易課税制度の適用に関する事故事例
5 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔設備投資に係る税額の全額を控除できなくなったケース〕
6 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔吸収合併に係る合併法人のケース〕
7 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔休眠会社利用のケース〕
3 簡易課税制度選択届出書の提出制限
(1) 課税事業者となることを選択した事業者
(2) 新設法人又は特定新規設立法人
(3) 高額特定資産の仕入れ等を行った事業者
(4) 棚卸資産の調整措置の適用を受けた事業者
(5) 高額の金地金等を取得した事業者
4 簡易課税制度選択届出書等の提出に係る特例
(1) やむを得ない事情による場合の特例(届出特例)
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
(2) 災害等によりその課税期間から適用を受けようとする場合の特例(災害届出特例)
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
(3) 特定非常災害の場合の特例
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
ハ 被災事業者が調整対象固定資産の
主要目次
第1編 消費税の概要
第1章 消費税の課税の対象
第1節 課税の対象となる国内取引
1 国内取引の課税の対象
2 事業者が事業として行う取引
3 対価を得て行う取引
4 資産の譲渡等
5 特定仕入れ
6 国内取引の判定基準
7 課税の対象にならない取引(不課税取引)
第2節 課税の対象となる輸入取引
1 課税の対象となる輸入取引
2 みなし引取り
第2章 非課税と免税
第1節 非課税
1 国内取引における非課税
2 輸入取引における非課税
第2節 免税
1 免税取引の範囲
2 非課税と免税の違い
第3章 納税義務者と納税義務の成立
第1節 納税義務者
1 国内取引の納税義務者
2 輸入取引の納税義務者
第2節 小規模事業者の納税義務の免除
1 小規模事業者の納税義務の免除とその特例
2 課税事業者の選択
3 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例
4 相続等があった場合の納税義務の免除の特例
5 新設法人の納税義務の免除の特例
6 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
7 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
8 調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
第3節 納税義務の成立
1 国内取引
2 輸入取引
第4章 適格請求書発行事業者
第1節 適格請求書
1 適格請求書の記載事項
2 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理
第2節 適格請求書発行事業者の登録制度
1 登録手続
2 新規開業者の登録に関する特例
3 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の経過措置
4 適格請求書発行事業者の登録の取消し及び失効
〔参考〕特定非常災害とインボイス制度
第3節 適格請求書発行事業者の義務等
1 原則
2 適格請求書の交付義務が免除される場合
3 適格請求書発行事業者以外の者が適格請求書を交付できる場合
4 適格請求書の写しの保存
第5章 課税標準と税率
第1節 課税標準と税率
1 国内取引の課税標準
2 輸入取引の課税標準
3 税率
第2節 課税標準額等の計算
1 課税標準額
2 課税標準額及び税額の計算(原則=総額割戻し方式)
3 インボイス制度開始後の適格請求書等積上げ方式(特例)
4 2割特例
第6章 税額控除等
第1節 仕入税額控除
1 課税仕入れ
2 課税仕入れの範囲
3 特定課税仕入れ
4 課税仕入れに係る消費税額の計算
5 特定課税仕入れに係る消費税額の計算
6 仕入税額控除の要件
第2節 仕入控除税額の計算方法
1 仕入控除税額の計算
2 課税売上割合とその計算
3 課税仕入れ等の税額の全額を控除できる場合
4 課税仕入れ等の税額の全額を控除できない場合
5 仕入対価の返還等を受けた場合の仕入控除税額の計算
6 調整対象固定資産に係る仕入控除税額の調整
第3節 簡易課税制度
1 簡易課税制度による場合の仕入控除税額の計算
2 簡易課税制度の適用要件
第4節 売上対価の返還等をした場合等の税額控除等
1 売上対価の返還等をした場合の税額控除
2 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の税額控除
3 貸倒れが生じた場合の税額控除等
第7章 課税期間、申告・納付、納税地
第1節 課税期間
1 個人事業者の課税期間
2 法人の課税期間
3 課税期間の特例
第2節 申告・納付
1 国内取引に係る申告と納付
2 輸入取引に係る申告と納付
第3節 納税地
1 国内取引の納税地
2 輸入取引の納税地
第8章 国等に対する特例
第1節 国等に対する特例の概要
1 事業単位の特例
2 資産の譲渡等の時期の特例
3 仕入税額控除の特例
4 一般会計の特例
5 申告期限の特例
第2節 仕入税額控除の特例
1 特定収入の意義
2 特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
3 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額の調整規定
第9章 雑則
1 届出書を提出しなければならない場合
2 承認・登録を受けなければならない場合
3 許可を受けなければならない場合
4 記帳義務
5 総額表示の義務
第2編 簡易課税制度
第1章 簡易課税制度の内容
第1節 簡易課税制度の特徴
1 一般課税との比較
2 インボイス制度と簡易課税制度
3 事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供を受けた場合
4 補助金等の収入がある場合
簡易課税制度の適用に関する事故事例
1 簡易課税制度を選択したことによる事故事例〔輸出免税の判断を誤ったケース〕
第2節 簡易課税制度を適用する場合、適用をやめる場合
1 簡易課税制度の適用
(1) 簡易課税制度の適用限度額
(2) 分割等の場合の適否判定
(3) 国外事業者に対する簡易課税制度の適用制限
(4) 簡易課税制度選択届出書の提出
(5) 事業を開始した日の属する課税期間等の特例
簡易課税制度選択届出書の効力発生時期としての「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」の意義
(6) 簡易課税制度選択届出書の効力の存続
イ 相続があった場合
ロ 合併等があった場合
簡易課税制度の適用に関する事故事例
2 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔新設法人を免税事業者と誤認したケース〕
3 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔特定期間の課税売上高による納税義務の判断を怠ったケ―ス〕
4 簡易課税制度選択届出書の提出を失念した事故事例〔e-Tax運用停止中のケース〕
2 簡易課税制度の不適用
(1) 簡易課税制度選択不適用届出書の提出
(2) 不適用となる課税期間
(3) 不適用届出書の提出の制限(2年間の継続適用)
簡易課税制度の適用に関する事故事例
5 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔設備投資に係る税額の全額を控除できなくなったケース〕
6 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔吸収合併に係る合併法人のケース〕
7 簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念した事故事例〔休眠会社利用のケース〕
3 簡易課税制度選択届出書の提出制限
(1) 課税事業者となることを選択した事業者
(2) 新設法人又は特定新規設立法人
(3) 高額特定資産の仕入れ等を行った事業者
(4) 棚卸資産の調整措置の適用を受けた事業者
(5) 高額の金地金等を取得した事業者
4 簡易課税制度選択届出書等の提出に係る特例
(1) やむを得ない事情による場合の特例(届出特例)
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
(2) 災害等によりその課税期間から適用を受けようとする場合の特例(災害届出特例)
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
(3) 特定非常災害の場合の特例
イ 制度の内容
ロ 具体的な適用事例
ハ 被災事業者が調整対象固定資産の