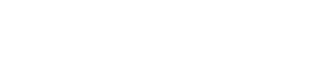労災認定の光と影 業務災害の公正な認定を目指して

販売価格: 2,200円 税込
- 数量
~業務災害の公正な認定を目指して~
元厚労省職業病認定対策室長の筆者が労災認定の基本的な原理を解き明かすだけでなく、歴史的経過を分析しかつての「災害主義」の考え方を排除することを提案しています。また、将来に向かっての労災認定のあるべき姿を示しています。
目次
はじめに
第1章 災害主義とその検証
第1節 戦前の労災認定の考え方
1 明治前期の国営工場労働者の災害補償
2 明治後期の鉱山労働者の保護
3 工場法の制定
4 労働者災害扶助法と労働者災害扶助責任保険法の制定
5 戦前における労災補償制度のポイント
第2節 労働基準法及び労働者災害補償保険法
1 労働基準法
2 労働者災害補償保険法
3 労働基準法と労働者災害補償保険法のポイント
第3節 「災害主義」の誤り
1 業務上疾病の限定とその誤り
〔1〕業務上疾病の限定の主張の背景
〔2〕業務上疾病の限定の理由
2 長谷川銕一郎著書の労災認定の理論とその誤り
〔1〕「災害」の定義等
〔2〕わが国の認定方式
3 「災害主義」とその誤り
〔1〕労働者性のない有害業務従事期間を含む事例(じん肺症の事例)
〔2〕過労死(脳・心臓疾患)の認定基準改正(2001年(平13)12月)
第4節 複数業務要因災害に関する保険給付の導入の誤り
1 問題点の認識
2 給付基礎日額(平均賃金)の算定方法の歴史的経過
〔1〕当初の解釈例規(通達による説明)
〔2〕裁判事例
〔3〕2004 年(平16)7月の「労災保険制度の在り方に関する研究会中間とりまとめ」
〔4〕副業・兼業の促進への政策転換
〔5〕副業・兼業促進の時代背景
3 複数業務要因災害に関する保険給付の創設とその考え方
〔1〕 労基法の災害補償責任と労災保険法による労災補償制度
〔2〕施行通達による説明の問題点
〔3〕従来の考え方-災害主義の残像-
〔4〕まとめ
〔5〕代替案
第2章 労災認定の在り方
第1節 労災補償制度の基本
1 労働者災害補償保険法の立法趣旨
2 労災補償の法的義務
3 無過失責任賠償
第2節 労災補償の対象となる事由
1 保険給付の対象
2 業務上疾病
〔1〕労働基準法施行規則別表第一の二(業務上疾病リスト)とその意義
〔2〕業務上疾病リストの内容
第3節 業務上の認定
1 「業務上」とは
〔1〕条件関係
〔2〕相当因果関係
〔3〕条件関係に加わって相当因果関係が肯定される要件
2 最高裁判決に基づく今後の認定方式
〔1〕東大ルンバール事件
〔2〕横浜南労基署長事件(東京海上横浜支店事件)
3 副業・兼業の場合の労災認定
4 立証責任
第4節 労災認定における留意事項
1 労働者性
〔1〕労働者の定義
〔2〕法令による適用除外
〔3〕会社の役員は原則として労働者に該当しない
〔4〕労働基準法研究会の「労働者」の判断基準
〔5〕在宅勤務者の労働者性
〔6〕労災保険の特別加入者
〔7〕その他判例等で労働者性の認められない者
〔8〕技能実習生の労働者性
〔9〕特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
〔10〕今後の労働者性
2 個別事例などにみる留意事項
〔1〕和歌山ベンジジン訴訟
〔2〕労災認定に対する事業主の不服申立て
〔3〕治療機会の喪失
〔4〕医療実践上の不利益に基づく補償
〔5〕出張中の傷病等
〔6〕企業スポーツ選手の傷病等
3 今後の課題となると考えられる事例
〔1〕宇宙線による健康障害
〔2〕傷病等に該当しない健康影響への対処
第3章 公正な労災認定
第1節 労災認定実務の基礎
1 医学への理解
〔1〕EBM(根拠に基づく医学・医療)
〔2〕量-影響関係
〔3〕医学情報と労災認定事例
2 不公正な考え方の排除
〔1〕政策論の介入の排除
〔2〕経済論の介入の排除
〔3〕認定しないのがよいとする同調圧力の排除
〔4〕不誠実な行政職員の対応
第2節 本省における実務
1 業務上疾病リストの改正
〔1〕定期的な検討の確保
〔2〕不適切な業務上疾病リストの改正(その1)
〔3〕不適切な業務上疾病リストの改正(その2)
2 認定基準の整備
〔1〕認定基準策定・改正の取組みの促進
〔2〕既存の認定基準の改正の必要性
3 調査実施要領の整備その他認定実務の支援等
〔1〕調査実施要領の整備
〔2〕労災認定のバイブル「労災保険 業務災害・通勤災害認定の理論と実際」の改訂
〔3〕厚生労働本省から労働局・労働基準監督署へのその他の支援
4 業務上疾病の労災補償状況の統計
〔1〕2つの業務上疾病統計
〔2〕労災認定数の統計の在り方
5 AI の導入による労災認定は不適切
第3節 労災認定の実務
1 概説
2 業務上疾病に関する認定の実務
3 労災認定に当たっての心構え
おわりに