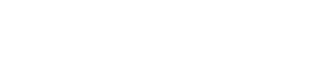実務直結シリーズ Vol. 4 行政書士のための 銀行の相続手続 実務家養成講座(第2版)

販売価格: 3,960円 税込
- 数量
凍結された口座の解除・払戻手続のすべて
株式・暗号資産・生命保険の手続について解説した新章を追加!
実際に作成・提出した「現物資料」162枚を完全再現して解説。
業務のイメージがつかめる! 業務完了までのロードマップが描ける!
口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されることになり、定められた手続で解除する必要があります。しかし、遺言の有無・遺産分割協議書の有無等、様々な条件によって必要書類が異なり、さらに各銀行で手続内容や必要書類が異なることがあるため、一般の人にとっては簡単ではありません。
相続人によっては、葬儀代などはもとより日々の生活費についても被相続人の預金に頼っており、早急に凍結を解除したいという方や、そもそも高齢で何度も銀行に足を運ぶことはできないといった方もいるため、相続手続の付随業務として一定のニーズがあります。
本書は、銀行手続業務に豊富な経験を持つ著者が、速やかに手続を済ませるために必要な知識とテクニックとともに、なぜそのような制度になっているかについても解説しています。
銀行の担当者によっては、本来必要ではない書類の提出を求めてくることがあり、十分な知識がない場合、徒に書類と手間が増えてしまいます。理論と技術の両面から解説した本書を活用することで、速やかで確実な手続が実現できます。
第2版では、新章「株式・暗号資産の相続手続と生命保険の手続」を追加しました。
実務においては、他の種類の金融資産が含まれていることもあります。ここでは、よくある「上場株式」の相続手続と、今後増加が見込まれる「暗号資産」の相続手続の流れについて解説しています。
また、相続財産には原則含まれませんが、生命保険についての手続をあわせて依頼されることも多いため、相続における生命保険の知識と行政書士が関与した死亡保険金請求手続の事例についても新たに解説を追加しています。
遺言作成・遺産分割などに加えて、銀行手続までワンストップでサービスを提供してもらえるのはありがたいと考えるクライアントは少ないはずです。行政書士に限らず、相続業務を行う専門家であれば是非ご一読ください。
【目次】
第1章 銀行の相続手続に求められる心得
1-1 「顧客価値」を知る~相続手続を行政書士に依頼する理由
1-2 「相続手続」業務に臨む3つの心得
1 「早期完遂」の意識で業務を遂行する
2 銀行の「助っ人」になる
3 法に基づいて論理的に対応する
1-3 「遺言作成」業務に臨む4つの心得
1 遺言の「目的」を考える
2 「ゴール」から考える
3 「万一」に備える
4 「速やか」に執行できるように納品する
第2章 銀行の相続手続に求められる法知識
2-1 遺言が「無い」場合に行う相続預貯金の払戻請求に必要な法知識
1 通常の場合~相続人全員による払戻請求
2 「遺産分割前における預貯金の払戻制度」を活用する場合(改正民909の2関係)
3 一部の相続人が「相続放棄」をした場合
4 一部の相続人が「相続分の放棄」や「相続分の譲渡」を行っている場合
5 相続人に「未成年の子」がいる場合
6 預金者が死亡した後,さらに相続人が死亡した場合(再転相続)
2-2 遺言が「有る」場合に行う相続預貯金の払戻請求に必要な法知識
1 「受益相続人」が行う場合
2 「受遺者」が行う場合
3 「遺言執行者」が行う場合
4 遺言で指定された受益相続人や受遺者が「既に死亡している」場合
5 「遺言と異なる」遺産分割協議書を提出する場合
2-3 遺言が「無い」「有る」に共通な相続預貯金の払戻請求に必要な法知識
1 「残高証明書」と「取引履歴」の開示請求
2 口座凍結~預金者が死亡した場合の銀行の対応
3 貸金庫~共同相続人の一部による貸金庫の内容物の確認・持出の可否
4 被相続人が外国籍の場合
5 相続預貯金の払戻手続を速やかにする遺言作成のポイント
6 自筆証書遺言の方式緩和と預貯金の目録作成に関する注意点
7 自筆証書遺言の保管制度
第3章 銀行の相続手続を俯瞰する
3-1 全ての業務に通底する「7つのプロセス」を知る
3-2 各プロセスの「役割」を知る
1 準備1(実務脳の習得)
2 アプローチ
3 引合い
4 準備2(面談に臨む準備)
5 面談
6 業務遂行
7 アフターフォロー
3-3 銀行の相続手続を俯瞰する
1 遺言が「無い」場合
2 遺言が「有る」場合
第4章 実務再現~「現物資料」で見る銀行の相続手続
4-1 遺言が「無い」場合
1 一般事例
2 相続人の中に「海外居住者」がいる事例
4-2 遺言が「有る」場合
1 「相続人の範囲」の調査
2 遺言の内容を相続人に通知する(改正民法1007条2項関係)
3 「相続財産の範囲と評価」の調査
4 払戻請求をする
5 相続財産の目録を作成して相続人に交付する(民法1011条1項関係)
6 業務完了
第5章 「7つのプロセス」で見る「銀行の相続手続」Q&A56
Q1 行政書士が銀行の相続手続を行う意義
Q2 銀行の相続手続に臨む心得
Q3 銀行に対する心得
Q4 銀行の相続手続の特徴と事務所経営の観点からみたメリット
Q5 銀行の相続手続の全体像
Q6 アプローチの方法
Q7 アプローチの決め台詞
Q8 銀行の相続手続の受任率をアップするために用意してもらう資料
Q9 引合い段階での注意点
Q10 受任率をアップするイメージトレーニング
Q11 銀行に連絡する前にすべきこと
Q12 銀行の相続手続の受任率をアップする技
Q13 受任を引き寄せる「5つ」の決め台詞
Q14 銀行の相続手続の委任状の技
Q15 銀行の相続手続の委任状をもらうタイミング
Q16 共同相続人の一部からの葬儀費用を支出するための預貯金払戻請求
Q17 受任当日に行う3つの事務
Q18 銀行の相続手続を要領よく行うための4つの知識
Q19 うっかり忘れがちなこと
Q20 銀行の相続手続の3つの型(銀行の相続手続の窓口)
Q21 原本還付と法定相続情報証明制度
Q22 銀行へのアポイント
Q23 アポイントでの伝達事項
Q24 銀行に提出する身分証明書
Q25 銀行の相続手続の所要時間
Q26 「相続届」の入手
Q27 担当者の指名
Q28 共同相続人の一部による預貯金口座の取引履歴及び残高証明書の請求の可否
Q29 残高証明書の届け先
Q30 残高証明書の請求に必要な戸籍謄本
Q31 残高証明書の発行に要する日数
Q32 口座凍結が実行される場面
Q33 口座凍結を行う理由
Q34 貸金庫の法的性質
Q35 貸金庫の内容物の取り出し
Q36 貸金庫内の「現金」の取り出し
Q37 貸金庫内の遺言書の取り出し
Q38 「遺産分割協議書」の作成の技
Q39 遺産分割協議成立前の葬儀費用の払戻請求
Q40 遺言執行者名義の口座開設の可否
Q41 遺言執行者として遺言執行者名義の口座を管理する際の留意点
Q42 遺言執行による払戻し完了後,新しい遺言書が発見された場合の当該払戻しの効力
Q43 受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合の代襲相続人への払戻しの可否
Q44 遺言があることを知らずに行った遺言内容と異なる払戻しの効力と行政書士の責任
Q45 遺言に不備がある場合の払戻請求の可否とその業務対応
Q46 相続届の作成の留意点
Q47 自書できない相続人がいる場合の対応
Q48 相続届の記載方法がわからない場合の対応
Q49 「相続届」を相続人の代理人のみの署名押印で作成する技
Q50 相続預貯金の振込方法
Q51 印鑑登録証明書の有効期限
Q52 ゆうちょ銀行の相続手続の留意点
Q53 投資信託等の払戻請求
Q54 残高が0円の口座の取扱い
Q55 被相続人が外国籍の相続預貯金の払戻し
Q56 依頼者をリピーターやキーマン(紹介者)にするフォローの技
第6章 株式・暗号資産の相続手続と生命保険の手続
6-1 上場株式の相続手続
1 上場株式の評価方法
2 場株式の相続手続
3 「現物資料」で見る上場株式の相続手続の流れ
6-2 暗号資産の相続手続
1 暗号資産の相続手続に必要な知識
2 暗号資産の相続手続の方法
6-3 生命保険の死亡保険金請求手続
1 死亡保険金請求手続に必要な知識
2 「現物資料」で見る死亡保険金請求手続の流れ