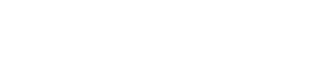判例と不動産鑑定 (第3版 ) 借地借家法理と鑑定実務
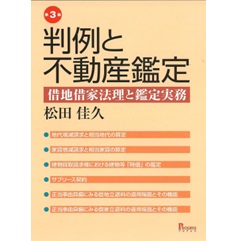
販売価格: 9,350円 税込
- 数量
新版発行以降の新たな判例・裁判例を100件以上追加し、その内容を分析・検討・解説している、借地借家法関連の判例レファレンスとして実務家必携の実務書の第3版。
不動産鑑定評価は、法律の規定と深い関わりを有している。特に借地借家では、借地権価額、借家権価額といった財産権譲渡にともなう価値評価のみではなく、地代・家賃等の法定果実、そして立退料、更新料、各種承諾料などといった一時金の算定など、いずれも調停や訴訟において鑑定評価がその算定の主役を担っているのである。
本書を著すにあたり、改めて裁判例をみると以前と同様に裁判において、原告依頼、被告依頼、裁判所依頼に基づく不動産鑑定士の鑑定評価がとても重要な役割を果たしていることがわかる。裁判官として不動産鑑定評価基準を理解しているものも多く、不動産鑑定士は、鑑定評価基準に則ってきちんとした鑑定評価を提出するので、裁判官が鑑定結果を修正して判決を下すという裁判例は少なくなったように思われる。
つまり、不動産鑑定は裁判に根付いており、その信頼は確固なものとなっているということである。
目次
第1章 地代増額請求と相当地代の算定
1 地代等増減請求権の要件
2 不動産鑑定評価基準における新規賃料および継続賃料の算出方法
(1) 新規賃料の算出方法
(2) 継続賃料の算出方法
3 判例・裁判例の分析・検討
(1) 宅地審議会第四次答申(昭和41年4月21日)前の判例・裁判例
(2) 宅地審議会第四次答申後の判例・裁判例
(3) 「不動産鑑定評価基準の設定に関する答申」建設省住宅地審発第15号
(昭和44年9月29日)後の判例・裁判例
(4) 平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用後から土地残余法採用(東京高判平12・7・18)前の判例・裁判例
(5) 土地残余法による方法を採用する裁判例
4 継続賃料肯定の是非
(1) 継続賃料・新規賃料の区分化
(2) 適正地代等と新規賃料の関係
(3) 不相当性判断の根拠となる事由
(4) 鑑定評価によって判断する個別性の判断
(5) 継続賃料肯定の是非
(6) 継続賃料算出方法と借地権価格
第2章 家賃増減請求と相当家賃の算定
1 問題の所在
2 地代等・家賃両者における増減請求権の条文比較
3 鑑定基準上の相違
4 判例・裁判例の分析
(1) 宅地審議会第四次答申後から「不動産鑑定評価基準の設立に関する答申」前
(2) 「不動産鑑定評価基準の設定に関する答申」後から平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用前
(3) 平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用後
5 家賃と地代等の算出上の差異
(1) 不相当性判断の根拠となる事由
(2) 鑑定評価で行う個別性の判断
(3) 家賃に関する判例と鑑定基準
(4) 差額配分法におけるマイナス差額の妥当性
6 本書旧版後の動向
(1) 不相当半産の根拠となる事由
(2) 鑑定評価に加える裁判官による個別性の判断
(3) 適用される鑑定評価手法とその関連づけについて
第3章 建物買取請求権における建物等「時価」の鑑定――場所的利益を中心として
1 対象不動産と価格時点
2 求めるべき価格と不動産鑑定評価基準
3 判例・裁判例にみる建物買取請求権における建物等「時価」の考え方―場所的利益が考慮された借地権価格を包含しない建物の積算価格
4 場所的利益の本質と算出方法
(1) 判例・裁判例の分析・検討
(2) 判例・裁判例における場所的利益の算出方法とその本質
5 判例・裁判例における建物買取請求権の建物等の「時価」の算出方法と鑑定基準の対比
6 建物買取請求権に関するその他の鑑定評価上の留意点
(1) 借地権譲渡後に増改築がなされた建物
(2) 所有者の異なる数筆の土地にまたがって存在する建物
(3) 借地権譲渡後に建物賃貸借がなされた場合
(4) 競落人からの買取請求の場合
第4章 サブリース契約(1)――サブリース法理と鑑定評価
1 最高裁平成15年10月判決前における下級審判決の分析・検討
2 平成15年10月以降の一連の最高裁判決の分析・検討
3 サブリース法理の借地への適用事案から判断されるサブリース法理の射程拡大
4 鑑定理論とサブリース契約等
(1) 拡大した射程に含まれるサブリース契約等
(2) 鑑定評価で求めるべき賃料として主張されている三説
(3) 若林氏が主張する正常実質賃料下限説とその評価
(4) 判例・裁判例における鑑定評価
(5) 鑑定によって求めるべき賃料
第5章 サブリース契約(2)――サブリース法理の他類型への射程拡大
1 借地事案と共同事業性
2 他類型事案への射程拡大
3 サブリース法理の一般化の検討
(1) 検討事項
(2) サブリースに関する一連の最高裁判決以降のサブリース法理適用時案における判断
4 おわりに
第6章 正当事由具備にみる借地立退料の適用場面とその機能
1 正当事由と根拠法
2 最三小判平6.10.25民集48.7.1303の判決内容
(1) 借地立退料の法的性質とその機能
(2) 正当事由の有無の判断基準時と立退料提供の申出可能期間
3 正当事由具備の段階的判断とその仮定
4 類型設定
5 判例・裁判例の分析・検討
(1) 新法施行前における判例
(2) 新法施行後における判例
6 総合考察
(1) 立退料と類型との関係
(2) 正当事由の段階的判断と立退料との関係
(3) 算定基準
(4) 申出額の増減
7 鑑定基準と立退料との関係
(1) 鑑定基準に基づく基準立退料額
(2) 立退料の価格時点と立退料算出の時間的限界
第7章 正当事由具備にみる借家立退料の適用場面とその機能
1 はじめに
2 正当事由の存在すべき時期と最高裁判所
3 正当事由具備の段階的判断とその仮定
4 類型設定
5 判例・裁判例の分析・検討
(1) 新法施行前における判例・裁判例
(2) 新法施行後における判例・裁判例
6 総合考察
(1) 立退料と類型との関係
(2) 正当事由の段階的判断と立退料との関係
(3) 算定基準
(4) 申出額の増減
7 新法適用時案の分析
(1) 類型ごとのまとめ
(2) 立退料と類型との関係(全類型)
(3) 正当事由の段階的判断と立退料との関係(全類型)
(4) 算定基準(全類型)
(5) 申出額の増減(全類型)
8 鑑定基準と立退料との関係
(1) 鑑定基準に基づく基準立退料額
(2) 立退料の価格時点と立退料算出の時間的限界
9 借地と借家の立退料理論の交錯
(1) 借地立退料と借家立退料との異同
(2) 法的諸問題
不動産鑑定評価は、法律の規定と深い関わりを有している。特に借地借家では、借地権価額、借家権価額といった財産権譲渡にともなう価値評価のみではなく、地代・家賃等の法定果実、そして立退料、更新料、各種承諾料などといった一時金の算定など、いずれも調停や訴訟において鑑定評価がその算定の主役を担っているのである。
本書を著すにあたり、改めて裁判例をみると以前と同様に裁判において、原告依頼、被告依頼、裁判所依頼に基づく不動産鑑定士の鑑定評価がとても重要な役割を果たしていることがわかる。裁判官として不動産鑑定評価基準を理解しているものも多く、不動産鑑定士は、鑑定評価基準に則ってきちんとした鑑定評価を提出するので、裁判官が鑑定結果を修正して判決を下すという裁判例は少なくなったように思われる。
つまり、不動産鑑定は裁判に根付いており、その信頼は確固なものとなっているということである。
目次
第1章 地代増額請求と相当地代の算定
1 地代等増減請求権の要件
2 不動産鑑定評価基準における新規賃料および継続賃料の算出方法
(1) 新規賃料の算出方法
(2) 継続賃料の算出方法
3 判例・裁判例の分析・検討
(1) 宅地審議会第四次答申(昭和41年4月21日)前の判例・裁判例
(2) 宅地審議会第四次答申後の判例・裁判例
(3) 「不動産鑑定評価基準の設定に関する答申」建設省住宅地審発第15号
(昭和44年9月29日)後の判例・裁判例
(4) 平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用後から土地残余法採用(東京高判平12・7・18)前の判例・裁判例
(5) 土地残余法による方法を採用する裁判例
4 継続賃料肯定の是非
(1) 継続賃料・新規賃料の区分化
(2) 適正地代等と新規賃料の関係
(3) 不相当性判断の根拠となる事由
(4) 鑑定評価によって判断する個別性の判断
(5) 継続賃料肯定の是非
(6) 継続賃料算出方法と借地権価格
第2章 家賃増減請求と相当家賃の算定
1 問題の所在
2 地代等・家賃両者における増減請求権の条文比較
3 鑑定基準上の相違
4 判例・裁判例の分析
(1) 宅地審議会第四次答申後から「不動産鑑定評価基準の設立に関する答申」前
(2) 「不動産鑑定評価基準の設定に関する答申」後から平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用前
(3) 平成3年4月1日不動産鑑定評価基準適用後
5 家賃と地代等の算出上の差異
(1) 不相当性判断の根拠となる事由
(2) 鑑定評価で行う個別性の判断
(3) 家賃に関する判例と鑑定基準
(4) 差額配分法におけるマイナス差額の妥当性
6 本書旧版後の動向
(1) 不相当半産の根拠となる事由
(2) 鑑定評価に加える裁判官による個別性の判断
(3) 適用される鑑定評価手法とその関連づけについて
第3章 建物買取請求権における建物等「時価」の鑑定――場所的利益を中心として
1 対象不動産と価格時点
2 求めるべき価格と不動産鑑定評価基準
3 判例・裁判例にみる建物買取請求権における建物等「時価」の考え方―場所的利益が考慮された借地権価格を包含しない建物の積算価格
4 場所的利益の本質と算出方法
(1) 判例・裁判例の分析・検討
(2) 判例・裁判例における場所的利益の算出方法とその本質
5 判例・裁判例における建物買取請求権の建物等の「時価」の算出方法と鑑定基準の対比
6 建物買取請求権に関するその他の鑑定評価上の留意点
(1) 借地権譲渡後に増改築がなされた建物
(2) 所有者の異なる数筆の土地にまたがって存在する建物
(3) 借地権譲渡後に建物賃貸借がなされた場合
(4) 競落人からの買取請求の場合
第4章 サブリース契約(1)――サブリース法理と鑑定評価
1 最高裁平成15年10月判決前における下級審判決の分析・検討
2 平成15年10月以降の一連の最高裁判決の分析・検討
3 サブリース法理の借地への適用事案から判断されるサブリース法理の射程拡大
4 鑑定理論とサブリース契約等
(1) 拡大した射程に含まれるサブリース契約等
(2) 鑑定評価で求めるべき賃料として主張されている三説
(3) 若林氏が主張する正常実質賃料下限説とその評価
(4) 判例・裁判例における鑑定評価
(5) 鑑定によって求めるべき賃料
第5章 サブリース契約(2)――サブリース法理の他類型への射程拡大
1 借地事案と共同事業性
2 他類型事案への射程拡大
3 サブリース法理の一般化の検討
(1) 検討事項
(2) サブリースに関する一連の最高裁判決以降のサブリース法理適用時案における判断
4 おわりに
第6章 正当事由具備にみる借地立退料の適用場面とその機能
1 正当事由と根拠法
2 最三小判平6.10.25民集48.7.1303の判決内容
(1) 借地立退料の法的性質とその機能
(2) 正当事由の有無の判断基準時と立退料提供の申出可能期間
3 正当事由具備の段階的判断とその仮定
4 類型設定
5 判例・裁判例の分析・検討
(1) 新法施行前における判例
(2) 新法施行後における判例
6 総合考察
(1) 立退料と類型との関係
(2) 正当事由の段階的判断と立退料との関係
(3) 算定基準
(4) 申出額の増減
7 鑑定基準と立退料との関係
(1) 鑑定基準に基づく基準立退料額
(2) 立退料の価格時点と立退料算出の時間的限界
第7章 正当事由具備にみる借家立退料の適用場面とその機能
1 はじめに
2 正当事由の存在すべき時期と最高裁判所
3 正当事由具備の段階的判断とその仮定
4 類型設定
5 判例・裁判例の分析・検討
(1) 新法施行前における判例・裁判例
(2) 新法施行後における判例・裁判例
6 総合考察
(1) 立退料と類型との関係
(2) 正当事由の段階的判断と立退料との関係
(3) 算定基準
(4) 申出額の増減
7 新法適用時案の分析
(1) 類型ごとのまとめ
(2) 立退料と類型との関係(全類型)
(3) 正当事由の段階的判断と立退料との関係(全類型)
(4) 算定基準(全類型)
(5) 申出額の増減(全類型)
8 鑑定基準と立退料との関係
(1) 鑑定基準に基づく基準立退料額
(2) 立退料の価格時点と立退料算出の時間的限界
9 借地と借家の立退料理論の交錯
(1) 借地立退料と借家立退料との異同
(2) 法的諸問題