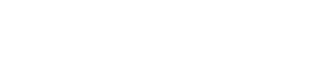よくわかる日本法制史
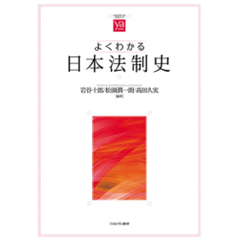
販売価格: 3,080円 税込
- 数量
国家生活、社会生活を営む私たちにとって所与のシステムである法律や法制度。その成立過程、存在意義、目的とはいかなるものか。本書は、日本法の歴史を、「古代」・「中世」・「近世」・「近現代」の各時代に区分して解説する。法の歴史をひもとくことで、現在では自明となっている様々な事柄の意味を、その成り立ちと起源から問い直す思考へと誘う。法律も歴史も幅広く学びたい人のためのテキスト。
[ここがポイント]
◎ 縦軸として、「古代」・「中世」・「近世」・「近現代」の各時代ごとに、通史的に日本法の成立・展開過程を解説
◎ 横軸として、「法源」・「法律学」・「法律家」・「裁判制度」の4つのテーマを設けることで、テーマ別に読み、学ぶことも可能
目次
はじめに
Ⅰ 古代
概 観
1 ヤマト政権と氏姓制度
2 大王と天皇号
3 中国律令法体系の継受と律令国家
4 律令官司制の構造
5 律令の罪刑
6 律令における親族規定
7 律令税制
8 古代の荘園
9 貴族政治の展開と令外官
10 格と式の編纂:弘仁・貞観・延喜三代の格式
11 律令学の生成と展開
12 律令体制下の法曹
13 律令の裁判機構と手続の流れ
14 刑部省と検非違使
15 軍制と検断
コラム1 平安時代の国司と地方支配
Ⅱ 中世——平安時代(院政期)〜戦国時代
概 観
1 院政の成立と中世公家政権
2 鎌倉幕府の権力構造
3 室町幕府・守護の支配体制
4 戦国大名の支配と正当性
5 身分と「家」の形成
コラム1 知行論争:日本法制史学の論争⑴
6 中世荘園制と本所法
7 村落と村法
8 取引社会と法
9 諸集団の法:寺社法と座法
コラム2 災害と法
10 鎌倉幕府法
11 室町幕府法
12 戦国大名の法
13 在地領主法
14 法と慣習
15 幕府法の運用と奉行人
コラム3 御成敗式目の注釈学:“今”を読み解くための過去の法令
16 朝廷・本所の裁判制度
17 鎌倉幕府の裁判制度
コラム4 神判
18 室町幕府の裁判制度
19 戦国大名の裁判制度
Ⅲ 近世——安土桃山時代・江戸時代
概 観
1 織豊政権の法
2 幕藩体制の統治構造
3 身分と家
4 対外関係と法
5 村落と土地制度
コラム1 現代とは異なる近世の土地慣行
6 幕藩制国家の領主財政と市場
7 都市生活と法
8 取引社会と法
コラム2 家父長制論争:日本法制史学の論争⑵
9 幕藩法の制定・編纂
コラム3 近世琉球の法と裁判
10 近世的法観念
11 裁判実務と方法
12 民衆と訴訟
13 法運用の担い手たち
14 江戸幕府の裁判制度の構成
15 訴願とその手続
16 江戸幕府の吟味筋
17 江戸幕府の出入筋
コラム4 評定所の出入筋裁判と判決方式の特質
18 幕府の裁判と藩の裁判
Ⅳ 近現代
概 観
1 明治前期
1 復古王政と近代化
2 太政官制から内閣制へ
3 元老院
4 不平等条約体制の成立と改正交渉
5 地租改正と地券
6 戸籍と身分制度
7 ヨーロッパ法の導入:民事法を中心に
8 刑事法典の編纂:律と西洋近代法
9 旧商法から明治商法へ
10 明治期の日本法学:法術と法学
11 法律学校(官立・私立)
12 法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)の歴史
13 法曹資格制度の歴史
14 お雇い外国人法律家
コラム1 明治日本における外国人法律家の学術活動
15 裁判制度(前期)
16 司法権の独立の近代史
17 刑事手続の近代化
18 勧解から調停制度へ
コラム2 法令の公知・公布
2 明治後期
1 大日本帝国憲法(制定過程と内容)
2 帝国議会
3 軍政と統帥
4 法典論争
5 法典調査会
6 明治民法
7 明治家族法制の成立
8 明治刑法
9 産業財産権法制
10 法例と国際私法
11 地方制度
12 法典継受と学説継受
13 学位制度の確立と大学令
14 裁判所構成法から裁判所法へ
15 民事訴訟制度
16 行政裁判所制度
17 監獄法の成立と展開(刑事処遇の近代化)
3 大正期,昭和戦前・戦間期
1 植民地統治(法制・含満洲国)
2 国際公法の展開
3 大正少年法
4 労働法・社会保障法の整備
5 公益事業法制と経済統制法令
6 臨時法制審議会
7 総動員体制/ファシズム体制
8 大正期の日本法学
9 概念法学と法律社会学
10 日本主義と「固有法」思想
11 天皇機関説事件
12 総動員体制下の法学者・法律家
13 大正刑事訴訟法(予審・陪審制度)
14 思想犯処罰/特高警察と検察
4 戦後
1 ポツダム宣言とGHQ占領
2 日本国憲法の制定
3 戦後の議会と選挙制度
4 民事法改正
5 刑事法改正
6 東京裁判
コラム1 日米安保
7 55年体制と憲法改正論議
8 戦後の地方自治
9 戦後日本と領土
10 戦後の日本法学
11 法整備支援
人名・事項索引
[ここがポイント]
◎ 縦軸として、「古代」・「中世」・「近世」・「近現代」の各時代ごとに、通史的に日本法の成立・展開過程を解説
◎ 横軸として、「法源」・「法律学」・「法律家」・「裁判制度」の4つのテーマを設けることで、テーマ別に読み、学ぶことも可能
目次
はじめに
Ⅰ 古代
概 観
1 ヤマト政権と氏姓制度
2 大王と天皇号
3 中国律令法体系の継受と律令国家
4 律令官司制の構造
5 律令の罪刑
6 律令における親族規定
7 律令税制
8 古代の荘園
9 貴族政治の展開と令外官
10 格と式の編纂:弘仁・貞観・延喜三代の格式
11 律令学の生成と展開
12 律令体制下の法曹
13 律令の裁判機構と手続の流れ
14 刑部省と検非違使
15 軍制と検断
コラム1 平安時代の国司と地方支配
Ⅱ 中世——平安時代(院政期)〜戦国時代
概 観
1 院政の成立と中世公家政権
2 鎌倉幕府の権力構造
3 室町幕府・守護の支配体制
4 戦国大名の支配と正当性
5 身分と「家」の形成
コラム1 知行論争:日本法制史学の論争⑴
6 中世荘園制と本所法
7 村落と村法
8 取引社会と法
9 諸集団の法:寺社法と座法
コラム2 災害と法
10 鎌倉幕府法
11 室町幕府法
12 戦国大名の法
13 在地領主法
14 法と慣習
15 幕府法の運用と奉行人
コラム3 御成敗式目の注釈学:“今”を読み解くための過去の法令
16 朝廷・本所の裁判制度
17 鎌倉幕府の裁判制度
コラム4 神判
18 室町幕府の裁判制度
19 戦国大名の裁判制度
Ⅲ 近世——安土桃山時代・江戸時代
概 観
1 織豊政権の法
2 幕藩体制の統治構造
3 身分と家
4 対外関係と法
5 村落と土地制度
コラム1 現代とは異なる近世の土地慣行
6 幕藩制国家の領主財政と市場
7 都市生活と法
8 取引社会と法
コラム2 家父長制論争:日本法制史学の論争⑵
9 幕藩法の制定・編纂
コラム3 近世琉球の法と裁判
10 近世的法観念
11 裁判実務と方法
12 民衆と訴訟
13 法運用の担い手たち
14 江戸幕府の裁判制度の構成
15 訴願とその手続
16 江戸幕府の吟味筋
17 江戸幕府の出入筋
コラム4 評定所の出入筋裁判と判決方式の特質
18 幕府の裁判と藩の裁判
Ⅳ 近現代
概 観
1 明治前期
1 復古王政と近代化
2 太政官制から内閣制へ
3 元老院
4 不平等条約体制の成立と改正交渉
5 地租改正と地券
6 戸籍と身分制度
7 ヨーロッパ法の導入:民事法を中心に
8 刑事法典の編纂:律と西洋近代法
9 旧商法から明治商法へ
10 明治期の日本法学:法術と法学
11 法律学校(官立・私立)
12 法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)の歴史
13 法曹資格制度の歴史
14 お雇い外国人法律家
コラム1 明治日本における外国人法律家の学術活動
15 裁判制度(前期)
16 司法権の独立の近代史
17 刑事手続の近代化
18 勧解から調停制度へ
コラム2 法令の公知・公布
2 明治後期
1 大日本帝国憲法(制定過程と内容)
2 帝国議会
3 軍政と統帥
4 法典論争
5 法典調査会
6 明治民法
7 明治家族法制の成立
8 明治刑法
9 産業財産権法制
10 法例と国際私法
11 地方制度
12 法典継受と学説継受
13 学位制度の確立と大学令
14 裁判所構成法から裁判所法へ
15 民事訴訟制度
16 行政裁判所制度
17 監獄法の成立と展開(刑事処遇の近代化)
3 大正期,昭和戦前・戦間期
1 植民地統治(法制・含満洲国)
2 国際公法の展開
3 大正少年法
4 労働法・社会保障法の整備
5 公益事業法制と経済統制法令
6 臨時法制審議会
7 総動員体制/ファシズム体制
8 大正期の日本法学
9 概念法学と法律社会学
10 日本主義と「固有法」思想
11 天皇機関説事件
12 総動員体制下の法学者・法律家
13 大正刑事訴訟法(予審・陪審制度)
14 思想犯処罰/特高警察と検察
4 戦後
1 ポツダム宣言とGHQ占領
2 日本国憲法の制定
3 戦後の議会と選挙制度
4 民事法改正
5 刑事法改正
6 東京裁判
コラム1 日米安保
7 55年体制と憲法改正論議
8 戦後の地方自治
9 戦後日本と領土
10 戦後の日本法学
11 法整備支援
人名・事項索引