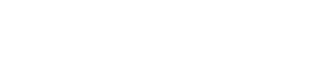Q&Aで学ぶ相続法 最新の法改正を踏まえた相続の基礎
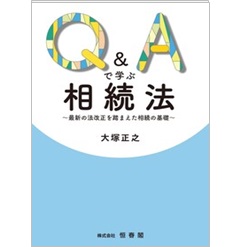
販売価格: 1,760円 税込
- 数量
◆相続法を初めて学ぶ方や、実際に相続の問題に関わることになったが、どのようにしたらよいか分からないという方に向け、Q&A形式により効果的に学んでいただくための相続法の講座です。
◆相続の全体像が理解できるよう、図を入れたり、実例を取り上げることでイメージ化しやすくし、自分が相続に関わることになったときに役立てることができます。
◆最近になって改正された相続法及び相続に関係する法律について、まとめて整理をしました。
目次
はじめに
第1部 相続とは?
Q01 相続とは何ですか
Q1 相続の原因は何ですか。
Q2 所在不明の人が生きているかどうか分からない場合、その財産はどうなるのでしょうか。
Q3 失踪宣告後、本人が生きていた場合、どうなるのでしょうか。
Q4 失踪宣告が取消された場合、その間に行われた遺産分割の効力はどうなるのでしょうか。
Q5 人が死亡した場合、相続人に承継されない権利や義務というのはあるのでしょうか。
Q02 相続人になるのは誰ですか
Q1 相続人になるのは誰ですか。
Q2 相続人である子、親、兄弟姉妹が複数いる場合、どうなるのですか。
Q3 被相続人に子がいない場合は、誰が相続しますか。
Q4 被相続人に子も親もいない場合は、誰が相続しますか。
Q5 兄弟姉妹が相続する場合、その相続分は平等ですか。
Q03 被相続人に多額の借金がある場合などはどうしたらよいですか
Q1 被相続人に多額の借金がある場合、どうすればよいでしょうか。
Q2 相続放棄をしないで、3か月が経過し、その後に債務があることが発覚した場合、相続放棄はできないのでしょうか。
Q3 相続の放棄をした方がよいかどうか分からない場合、どうすればよいでしょうか。
Q4 被相続人の債務の存在について争いがあり、その決着がつかないと放棄してよいかどうか判断できない場合はどうすればよいのでしょうか。
Q5 相続人全員が相続を放棄した場合、どうなるのですか。
Q6 相続の承認も放棄もしない場合、どうなるのですか。
Q04 相続の放棄や承認をした後に、これを撤回することはできますか
Q1 相続放棄をした後に、撤回して承認することはできますか。
Q2 どんな場合でも相続の承認や放棄の撤回ができないのでしょうか。
Q3 相続の承認や放棄の取消をしたい場合、どうすればよいのでしょうか。
Q05 相続を承認したことになるのは、猶予期間の3か月が経過した場合だけでしょうか
Q1 相続を承認したことになるのは、3か月が経過した場合以外にありますか。
Q2 相続の承認にはならない「短期間の賃貸借」というのは、どの程度の期間でしょうか。
Q3 相続放棄の申述をした後は、単純承認になることはありませんか。
Q06 相続人になることができない事由とは何でしょうか
Q1 どのような場合に、相続人になることができないのですか。
Q2 相続人の1人がすべての財産を当該相続人に相続させる旨の遺言書を発見しましたが、そうなると家族間で紛争になるので、これを隠匿した場合、相続欠格事由に該当するのですか。
Q3 長男が自分に対して虐待などの行為をしているので、相続させたくありません。このような場合、どうすればよいですか。
Q07 財産分離というのは何ですか
Q1 民法にある財産分離とは何でしょうか。
Q2 被相続人に財産がなく、相続人に資産と負債がある場合はどうなるのでしょうか。
Q08 相続人がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか
Q1 相続人が見つからない場合、どうすればよいのでしょうか。
Q2 死亡者に相続人がいない場合、その債権者はどうすればよいのでしょうか。
Q3 清算中に相続人だと主張する人が現われたら、どうするのでしょうか。
Q4 相続人が現れなかった場合、どうなるのでしょうか。
Q5 相続人が現れなかった場合、相続財産はどうなるのでしょうか。
Q6 特別縁故者がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか。
第2部 遺言とは何か?
Q09 遺言とは何でしょうか
Q1 遺言とは、どのようなものですか。
Q2 遺言にはどのような方式のものがありますか。
Q3 未成年者や成年被後見人も遺言をすることはできるのでしょうか。
Q4 遺言能力とは何ですか。
Q5 遺言書を夫婦が一緒にすることはできますか。
Q6 普通方式の遺言には、どのようなものがありますか。
Q7 自筆証書による遺言とはどのような遺言ですか。
Q8 相続財産がたくさんある場合、それを全部手で書くのは大変ではないですか。
Q9 遺言書に変更・訂正がある場合、有効なのでしょうか。
Q10 遺言書の署名の下に押印がなく、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目に押印がある場合はどうなるのでしょうか。
Q11 カーボン複写の場合はどうでしょうか。
Q10 公正証書遺言とは、どのような遺言なのでしょうか
Q1 公正証書遺言はどのようにして作りますか。
Q2 公正証書遺言の要件はどのようなものですか。
Q3 遺言者の口述を筆記するとされていますが、口がきけない者は口述ができないので、公正証書遺言は作成できないことになるのでしょうか。
Q11 秘密証書遺言とは、どのような遺言書なのでしょうか
Q1 秘密証書遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 秘密証書遺言の要件はどのようなものですか。
Q3 秘密証書遺言の方式を具備していない場合は無効になりますか。
Q4 秘密証書遺言でも、口がきけない人は口授できないという問題がありませんか。
Q12 特別方式の遺言には、どのようなものがありますか
Q1 特別方式の遺言として、どのようなものが認められていますか。
Q2 死亡の危急の迫った者の遺言というのは、どのようにして作成するのでしょうか。
Q3 遺言者において、口がきけなかったり、耳が聞こえなかったりする場合、どうすればよいのでしょうか。
Q13 伝染病隔離者の遺言とは何でしょうか
Q1 伝染病隔離者の遺言の要件とは何ですか。
Q2 その場合、警察官や証人はどうすればよいのでしょうか。
Q14 在船者の遺言とは、どのようなものですか
Q1 在船者の遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 その場合、船長又は事務員や証人は何をすればよいのでしょうか。
Q15 船舶遭難者の遺言とは何でしょうか
Q1 船舶遭難者の遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 口がきけない者の場合はどうすればよいのでしょうか。
Q16 遺言にはどのような効力があるのでしょうか
Q1 遺言が有効にされた場合、その遺言書にはどのような効力があるのでしょうか。
Q2 遺贈とは何ですか。
Q3 遺贈は拒絶されない限り、その効力が生じるのはなぜでしょうか。
Q4 遺贈の承認又は放棄を撤回することができますか。
Q5 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしない間に死亡した場合はどうなりますか。
Q6 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合はどうなりますか。
Q7 遺贈の効力が生じない場合、その受遺者が受けるべき遺産はどうなりますか。
Q8 相続財産に属さない財産を遺贈の目的とした場合、その遺贈は効力を生じますか。
Q9 遺贈の目的物にキズ(瑕疵)があった場合、遺贈義務者はキズのないものに代えないといけないのでしょうか。
Q17 遺言書が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか
Q1 遺言者が死亡した後、机の引き出しに自筆による遺言書(自筆証書遺言)がありました。そのまま保管をしていればよいのでしょうか。
Q2 遺言書の検認を受けない場合、どうなりますか。
Q3 その場合、遺言書は無効になるのでしょうか。
Q18 遺言の執行はどのようにして実施すればよいのでしょうか
Q1 遺言の内容を実現するにあたり、遺言執行者は必要なのでしょうか。
Q2 遺言執行者に指定された人が遺言執行者になることを拒んだ場合、どうすればよいでしょうか。
Q3 遺言執行者が「就職を辞退する」と、言ってきたときはどうすればよいでしょうか。
Q4 誰でも遺言執行者になれるのでしょうか。
Q5 遺言執行者は何をする人ですか。
Q6 遺言執行者がある場合、相続人は遺贈を受けた者に遺贈された物又は権利を渡すことはできますか。
Q7 もし、相続人が遺言執行者の意思に反して受遺者に目的物を引き渡すなどしたら、その効力はどうなるのでしょうか。
Q8 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合、その不動産の取得者は、相続登記をすることができないのでしょうか。
Q9 遺言執行者がきちんと遺言の執行をしてくれない場合、相続人又は受遺者はどうすればよいでしょうか。
第3部 遺産分割について
Q19 遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか
Q1 遺産分割は、どのようにすればよいのでしょうか。
Q2 遺産の評価はどうすればよいのでしょうか。
Q3 相続時から20年が経過しており、相続時の評価額と現在の評価額とでは全く違っています。そのような場合も相続時の評価が基準となりますか。
Q4 先祖代々のお墓や祭具なども遺産分割の対象になるのでしょうか。
Q5 相続財産が放置されている場合、保存に必要な処分は誰が行うのでしょうか。
Q6 相続人が相続を放棄した場合は誰が遺産を管理するのでしょうか。
Q7 相続人が複数いる場合、相続財産は誰に帰属しているのでしょうか。
Q8 預貯金等の解約ができないと葬儀費用を支払えないというような場合、どうすればよいのでしょうか。
Q9 遺産分割が終了した後に死後認知により相続人となった者が現われた場合、どうすればよいでしょうか。
Q20 遺産分割の具体的な方法について教えてください
Q1 遺産分割の基準はどうなっていますか。
Q2 長男が親と一緒に農業を営んできて、父が亡くなった後も農業を続けたいという場合、すべての遺産を長男に相続させることはできますか。
Q3 長男は親と一緒に農業を営み、遺産を増やすのに貢献してきたのに法定相続分が同じだというのは不公平ではありませんか。
Q4 相続人の中に生前被相続人から多額の生計の資本としての贈与を受けていた者がある場合、相続分は同じなのでしょうか。
Q5 特別受益が多額の場合、どうなるのですか。
Q6 特別受益や寄与分を考慮するというのは、どの時点で遺産分割をする場合でも適用されるのですか。
Q7 特別受益、寄与分というのは、どの時点で評価されますか。相続時でしょうか。分割時でしょうか。
Q8 遺産が不動産しかない場合、どのような分割方法が考えられますか。
Q9 被相続人の妻と先妻の子が相続したが、遺産としては自宅の土地建物しかない場合、どのように分割すればよいでしょうか。
Q10 夫が生前、妻に自宅を贈与した場合、特別受益として、遺産分割では考慮されることになり、妻は自宅以外の遺産を取得できなくなりませんか。
Q11 20年に満たない夫婦関係の場合、持ち戻しをしないという推定は働きませんし、突然死亡したような場合には贈与や遺贈の余地がなく、この規定は適用できません。そのような場合、どうすればよいのでしょうか。
Q12 相続人は、相続が開始して遺産分割が終了するまで遺産である建物に引き続き居住することができますか。
Q21 遺産分割において、遺産の評価はどのようにしたらよいでしょうか
Q1 遺産分割では遺産の評価が必要になりますが、どのように評価をすればよいのでしょうか。
Q2 不動産の評価はどの時点を基準にすればよいのでしょうか。
Q3 株式などは相続時の評価額でよいのでしょうか。
Q4 書画・骨董品などの評価はどうすればよいのでしょうか。
Q5 自動車の場合、評価はどうなるのでしょうか。
Q6 相続開始後に相続人の1人が遺産についての固定資産税を負担したり、建物の修復工事をしたりするなどの費用を投下してきている場合、これらの費用を他の相続人に請求することはできますか。
Q7 遺産分割前に遺産である自動車を相続人の1人が処分をした場合、どうすればよいのでしょうか。
Q8 遺産の一部に争いがある場合、その争いのある部分を除いて遺産分割をすることはできますか。
Q9 しばらく遺産分割をしたくないという場合、遺産分割を禁止することはできないでしょうか。
Q10 遺産分割の結果、不動産を取得した者は、相続開始から分割協議成立までの賃貸不動産の賃料(法定果実)を取得できますか。
Q11 被相続人の負担していた債務は、遺産分割ではどのように扱われるのでしょうか。
Q12 遺産相続や遺産分割があった場合、不動産については、その旨の登記をしなくてもよいのでしょうか。
Q22 遺留分とは何ですか
Q1 全財産を長男に遺贈する旨の遺言があっても遺留分を侵害することはできないというのは、どういう意味なのでしょうか。
Q2 遺産総額に遺留分割合を乗じたものが遺留分侵害額になるのでしょうか。
Q3 遺留分算定の基礎財産に加算すべき贈与というのは、すべての贈与を含むのですか。
Q23 長男の妻が被相続人の自宅での介護を長期間にわたり行っていたのですが、その労苦は相続において評価されないのでしょうか
Q1 被相続人の療養介護に専念した相続人の親族は、相続を受けることができないのでしょうか。
Q2 特別寄与者というのは、被相続人の親族に限られるのですか。
Q3 特別寄与者が相続人に対し、特別寄与料の請求をしても応じてもらえない場合、どうすればよいのでしょうか。
Q4 相続人が複数いる場合、どの相続人にどのような金額の特別寄与料を請求したらよいのでしょうか。
第4部 最近の相続法改正について
Q24 最近の相続法の改正について教えてください
Q1 相続法については、まず平成30年に大きく民法の相続編が改正されていますが、どの点について変更がされたのでしょうか。
Q2 同じく平成30年に自筆証書遺言を法務局で保管をする制度ができましたが、これはどのような内容でしょうか。
Q3 所有者不明土地問題の解決のため、相続法に影響を与える法改正として国庫帰属法がありますが、これはどのようなものでしょうか。
Q4 令和3年改正法により、民法の共有に関する規定の改正が行われました。相続に影響を与える改正内容を教えてください。
Q5 所有者不明土地の解消を目的とする法改正に伴い、相続法に影響を与えたのはどのような点でしょうか。
Q6 令和5年改正法による相続法の改正がありますか。
おわりに
付録(参照条文)
◆相続の全体像が理解できるよう、図を入れたり、実例を取り上げることでイメージ化しやすくし、自分が相続に関わることになったときに役立てることができます。
◆最近になって改正された相続法及び相続に関係する法律について、まとめて整理をしました。
目次
はじめに
第1部 相続とは?
Q01 相続とは何ですか
Q1 相続の原因は何ですか。
Q2 所在不明の人が生きているかどうか分からない場合、その財産はどうなるのでしょうか。
Q3 失踪宣告後、本人が生きていた場合、どうなるのでしょうか。
Q4 失踪宣告が取消された場合、その間に行われた遺産分割の効力はどうなるのでしょうか。
Q5 人が死亡した場合、相続人に承継されない権利や義務というのはあるのでしょうか。
Q02 相続人になるのは誰ですか
Q1 相続人になるのは誰ですか。
Q2 相続人である子、親、兄弟姉妹が複数いる場合、どうなるのですか。
Q3 被相続人に子がいない場合は、誰が相続しますか。
Q4 被相続人に子も親もいない場合は、誰が相続しますか。
Q5 兄弟姉妹が相続する場合、その相続分は平等ですか。
Q03 被相続人に多額の借金がある場合などはどうしたらよいですか
Q1 被相続人に多額の借金がある場合、どうすればよいでしょうか。
Q2 相続放棄をしないで、3か月が経過し、その後に債務があることが発覚した場合、相続放棄はできないのでしょうか。
Q3 相続の放棄をした方がよいかどうか分からない場合、どうすればよいでしょうか。
Q4 被相続人の債務の存在について争いがあり、その決着がつかないと放棄してよいかどうか判断できない場合はどうすればよいのでしょうか。
Q5 相続人全員が相続を放棄した場合、どうなるのですか。
Q6 相続の承認も放棄もしない場合、どうなるのですか。
Q04 相続の放棄や承認をした後に、これを撤回することはできますか
Q1 相続放棄をした後に、撤回して承認することはできますか。
Q2 どんな場合でも相続の承認や放棄の撤回ができないのでしょうか。
Q3 相続の承認や放棄の取消をしたい場合、どうすればよいのでしょうか。
Q05 相続を承認したことになるのは、猶予期間の3か月が経過した場合だけでしょうか
Q1 相続を承認したことになるのは、3か月が経過した場合以外にありますか。
Q2 相続の承認にはならない「短期間の賃貸借」というのは、どの程度の期間でしょうか。
Q3 相続放棄の申述をした後は、単純承認になることはありませんか。
Q06 相続人になることができない事由とは何でしょうか
Q1 どのような場合に、相続人になることができないのですか。
Q2 相続人の1人がすべての財産を当該相続人に相続させる旨の遺言書を発見しましたが、そうなると家族間で紛争になるので、これを隠匿した場合、相続欠格事由に該当するのですか。
Q3 長男が自分に対して虐待などの行為をしているので、相続させたくありません。このような場合、どうすればよいですか。
Q07 財産分離というのは何ですか
Q1 民法にある財産分離とは何でしょうか。
Q2 被相続人に財産がなく、相続人に資産と負債がある場合はどうなるのでしょうか。
Q08 相続人がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか
Q1 相続人が見つからない場合、どうすればよいのでしょうか。
Q2 死亡者に相続人がいない場合、その債権者はどうすればよいのでしょうか。
Q3 清算中に相続人だと主張する人が現われたら、どうするのでしょうか。
Q4 相続人が現れなかった場合、どうなるのでしょうか。
Q5 相続人が現れなかった場合、相続財産はどうなるのでしょうか。
Q6 特別縁故者がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか。
第2部 遺言とは何か?
Q09 遺言とは何でしょうか
Q1 遺言とは、どのようなものですか。
Q2 遺言にはどのような方式のものがありますか。
Q3 未成年者や成年被後見人も遺言をすることはできるのでしょうか。
Q4 遺言能力とは何ですか。
Q5 遺言書を夫婦が一緒にすることはできますか。
Q6 普通方式の遺言には、どのようなものがありますか。
Q7 自筆証書による遺言とはどのような遺言ですか。
Q8 相続財産がたくさんある場合、それを全部手で書くのは大変ではないですか。
Q9 遺言書に変更・訂正がある場合、有効なのでしょうか。
Q10 遺言書の署名の下に押印がなく、遺言書本文の入れられた封筒の封じ目に押印がある場合はどうなるのでしょうか。
Q11 カーボン複写の場合はどうでしょうか。
Q10 公正証書遺言とは、どのような遺言なのでしょうか
Q1 公正証書遺言はどのようにして作りますか。
Q2 公正証書遺言の要件はどのようなものですか。
Q3 遺言者の口述を筆記するとされていますが、口がきけない者は口述ができないので、公正証書遺言は作成できないことになるのでしょうか。
Q11 秘密証書遺言とは、どのような遺言書なのでしょうか
Q1 秘密証書遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 秘密証書遺言の要件はどのようなものですか。
Q3 秘密証書遺言の方式を具備していない場合は無効になりますか。
Q4 秘密証書遺言でも、口がきけない人は口授できないという問題がありませんか。
Q12 特別方式の遺言には、どのようなものがありますか
Q1 特別方式の遺言として、どのようなものが認められていますか。
Q2 死亡の危急の迫った者の遺言というのは、どのようにして作成するのでしょうか。
Q3 遺言者において、口がきけなかったり、耳が聞こえなかったりする場合、どうすればよいのでしょうか。
Q13 伝染病隔離者の遺言とは何でしょうか
Q1 伝染病隔離者の遺言の要件とは何ですか。
Q2 その場合、警察官や証人はどうすればよいのでしょうか。
Q14 在船者の遺言とは、どのようなものですか
Q1 在船者の遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 その場合、船長又は事務員や証人は何をすればよいのでしょうか。
Q15 船舶遭難者の遺言とは何でしょうか
Q1 船舶遭難者の遺言は、どのような場合に利用されますか。
Q2 口がきけない者の場合はどうすればよいのでしょうか。
Q16 遺言にはどのような効力があるのでしょうか
Q1 遺言が有効にされた場合、その遺言書にはどのような効力があるのでしょうか。
Q2 遺贈とは何ですか。
Q3 遺贈は拒絶されない限り、その効力が生じるのはなぜでしょうか。
Q4 遺贈の承認又は放棄を撤回することができますか。
Q5 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしない間に死亡した場合はどうなりますか。
Q6 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合はどうなりますか。
Q7 遺贈の効力が生じない場合、その受遺者が受けるべき遺産はどうなりますか。
Q8 相続財産に属さない財産を遺贈の目的とした場合、その遺贈は効力を生じますか。
Q9 遺贈の目的物にキズ(瑕疵)があった場合、遺贈義務者はキズのないものに代えないといけないのでしょうか。
Q17 遺言書が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか
Q1 遺言者が死亡した後、机の引き出しに自筆による遺言書(自筆証書遺言)がありました。そのまま保管をしていればよいのでしょうか。
Q2 遺言書の検認を受けない場合、どうなりますか。
Q3 その場合、遺言書は無効になるのでしょうか。
Q18 遺言の執行はどのようにして実施すればよいのでしょうか
Q1 遺言の内容を実現するにあたり、遺言執行者は必要なのでしょうか。
Q2 遺言執行者に指定された人が遺言執行者になることを拒んだ場合、どうすればよいでしょうか。
Q3 遺言執行者が「就職を辞退する」と、言ってきたときはどうすればよいでしょうか。
Q4 誰でも遺言執行者になれるのでしょうか。
Q5 遺言執行者は何をする人ですか。
Q6 遺言執行者がある場合、相続人は遺贈を受けた者に遺贈された物又は権利を渡すことはできますか。
Q7 もし、相続人が遺言執行者の意思に反して受遺者に目的物を引き渡すなどしたら、その効力はどうなるのでしょうか。
Q8 特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合、その不動産の取得者は、相続登記をすることができないのでしょうか。
Q9 遺言執行者がきちんと遺言の執行をしてくれない場合、相続人又は受遺者はどうすればよいでしょうか。
第3部 遺産分割について
Q19 遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか
Q1 遺産分割は、どのようにすればよいのでしょうか。
Q2 遺産の評価はどうすればよいのでしょうか。
Q3 相続時から20年が経過しており、相続時の評価額と現在の評価額とでは全く違っています。そのような場合も相続時の評価が基準となりますか。
Q4 先祖代々のお墓や祭具なども遺産分割の対象になるのでしょうか。
Q5 相続財産が放置されている場合、保存に必要な処分は誰が行うのでしょうか。
Q6 相続人が相続を放棄した場合は誰が遺産を管理するのでしょうか。
Q7 相続人が複数いる場合、相続財産は誰に帰属しているのでしょうか。
Q8 預貯金等の解約ができないと葬儀費用を支払えないというような場合、どうすればよいのでしょうか。
Q9 遺産分割が終了した後に死後認知により相続人となった者が現われた場合、どうすればよいでしょうか。
Q20 遺産分割の具体的な方法について教えてください
Q1 遺産分割の基準はどうなっていますか。
Q2 長男が親と一緒に農業を営んできて、父が亡くなった後も農業を続けたいという場合、すべての遺産を長男に相続させることはできますか。
Q3 長男は親と一緒に農業を営み、遺産を増やすのに貢献してきたのに法定相続分が同じだというのは不公平ではありませんか。
Q4 相続人の中に生前被相続人から多額の生計の資本としての贈与を受けていた者がある場合、相続分は同じなのでしょうか。
Q5 特別受益が多額の場合、どうなるのですか。
Q6 特別受益や寄与分を考慮するというのは、どの時点で遺産分割をする場合でも適用されるのですか。
Q7 特別受益、寄与分というのは、どの時点で評価されますか。相続時でしょうか。分割時でしょうか。
Q8 遺産が不動産しかない場合、どのような分割方法が考えられますか。
Q9 被相続人の妻と先妻の子が相続したが、遺産としては自宅の土地建物しかない場合、どのように分割すればよいでしょうか。
Q10 夫が生前、妻に自宅を贈与した場合、特別受益として、遺産分割では考慮されることになり、妻は自宅以外の遺産を取得できなくなりませんか。
Q11 20年に満たない夫婦関係の場合、持ち戻しをしないという推定は働きませんし、突然死亡したような場合には贈与や遺贈の余地がなく、この規定は適用できません。そのような場合、どうすればよいのでしょうか。
Q12 相続人は、相続が開始して遺産分割が終了するまで遺産である建物に引き続き居住することができますか。
Q21 遺産分割において、遺産の評価はどのようにしたらよいでしょうか
Q1 遺産分割では遺産の評価が必要になりますが、どのように評価をすればよいのでしょうか。
Q2 不動産の評価はどの時点を基準にすればよいのでしょうか。
Q3 株式などは相続時の評価額でよいのでしょうか。
Q4 書画・骨董品などの評価はどうすればよいのでしょうか。
Q5 自動車の場合、評価はどうなるのでしょうか。
Q6 相続開始後に相続人の1人が遺産についての固定資産税を負担したり、建物の修復工事をしたりするなどの費用を投下してきている場合、これらの費用を他の相続人に請求することはできますか。
Q7 遺産分割前に遺産である自動車を相続人の1人が処分をした場合、どうすればよいのでしょうか。
Q8 遺産の一部に争いがある場合、その争いのある部分を除いて遺産分割をすることはできますか。
Q9 しばらく遺産分割をしたくないという場合、遺産分割を禁止することはできないでしょうか。
Q10 遺産分割の結果、不動産を取得した者は、相続開始から分割協議成立までの賃貸不動産の賃料(法定果実)を取得できますか。
Q11 被相続人の負担していた債務は、遺産分割ではどのように扱われるのでしょうか。
Q12 遺産相続や遺産分割があった場合、不動産については、その旨の登記をしなくてもよいのでしょうか。
Q22 遺留分とは何ですか
Q1 全財産を長男に遺贈する旨の遺言があっても遺留分を侵害することはできないというのは、どういう意味なのでしょうか。
Q2 遺産総額に遺留分割合を乗じたものが遺留分侵害額になるのでしょうか。
Q3 遺留分算定の基礎財産に加算すべき贈与というのは、すべての贈与を含むのですか。
Q23 長男の妻が被相続人の自宅での介護を長期間にわたり行っていたのですが、その労苦は相続において評価されないのでしょうか
Q1 被相続人の療養介護に専念した相続人の親族は、相続を受けることができないのでしょうか。
Q2 特別寄与者というのは、被相続人の親族に限られるのですか。
Q3 特別寄与者が相続人に対し、特別寄与料の請求をしても応じてもらえない場合、どうすればよいのでしょうか。
Q4 相続人が複数いる場合、どの相続人にどのような金額の特別寄与料を請求したらよいのでしょうか。
第4部 最近の相続法改正について
Q24 最近の相続法の改正について教えてください
Q1 相続法については、まず平成30年に大きく民法の相続編が改正されていますが、どの点について変更がされたのでしょうか。
Q2 同じく平成30年に自筆証書遺言を法務局で保管をする制度ができましたが、これはどのような内容でしょうか。
Q3 所有者不明土地問題の解決のため、相続法に影響を与える法改正として国庫帰属法がありますが、これはどのようなものでしょうか。
Q4 令和3年改正法により、民法の共有に関する規定の改正が行われました。相続に影響を与える改正内容を教えてください。
Q5 所有者不明土地の解消を目的とする法改正に伴い、相続法に影響を与えたのはどのような点でしょうか。
Q6 令和5年改正法による相続法の改正がありますか。
おわりに
付録(参照条文)