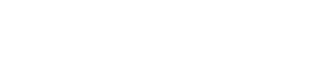労働基準法の実務相談(令和7年度)
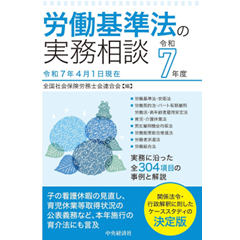
販売価格: 3,520円 税込
- 数量
労働基準・安全衛生、労働契約・パート・高年齢者雇用、育児介護、機会均等、派遣等実務を解説。子の看護休暇見直し、育児休業等取得状況の公表義務等、最新の育介法に言及。
目次
第1編 労働基準法・安衛法
1 総則
Q1 正社員・嘱託・パートの違いと労働条件格差
Q2 外国人の雇用と均等待遇の原則
Q3 使用人兼務役員や執行役員は労働者か
Q4 出向者と労基法の適用関係
Q5 兼務出向と労働関係法令の適用
Q6 慶弔見舞金・住宅補助等の福利厚生的給付と労基法上の賃金
Q7 平均賃金算定の起算日
Q8 欠勤・休業期間と平均賃金の算定
Q9 通勤定期券の支給と平均賃金の算定
Q10 労基法上の権利の消滅時効の改正
2 労働契約
Q11 労基法に違反すると何が問題か
Q12 長期労働契約締結の禁止の原則と例外
Q13 雇用保障期間と長期労働契約締結の禁止の関係
Q14 期間雇用者の労働条件の明示
Q15 期間雇用者に限らない労働条件の明示
Q16 採用内定・内々定と労働条件明示義務
Q17 採用時の労働条件明示義務の対象範囲
Q18 労働契約締結時の条件明示の程度
Q19 電子メールによる労働契約締結時の労働条件明示
Q20 損害賠償の誓約書と賠償予定の禁止,秘密保持義務・競業避止義務
3 解雇・退職
Q21 採用内定者(内々定者)と労基法の適用
Q22 定年制と解雇制限
Q23 休職期間満了による退職・解雇と解雇予告
Q24 試用期間中のパワハラと欠勤休職制度の適用,解雇問題
Q25 休職期間の延長拒否は解雇となるか
Q26 有期契約の更新拒否と解雇
Q27 退職願い・退職届の撤回(取消し)
Q28 解雇予告の必要な場合・不要な場合
Q29 解雇予告除外認定
Q30 解雇予告と解雇予告手当
Q31 条件を付して解雇する,という通知の意味・有効性
Q32 解雇予告と同時に休業を命じた場合の賃金
Q33 諭旨退職・諭旨解雇と解雇予告
Q34 3カ月前の退職申出を義務付けられるか
Q35 退職金の支払時期
Q36 退職後に懲戒解雇事由が明らかになった場合
Q37 無断で欠勤し,出社しなくなった者の取扱い
4 賃金
Q38 賃金の直接払いの原則と本人以外の者への賃金の支払い
Q39 旅行積立金・会社立替金の賃金・退職金からの控除
Q40 通貨払いの原則とデジタルマネーでの賃金支払い
Q41 賃金の締切日・支払日の変更
Q42 毎月払いの原則と割増賃金の翌月支払い
Q43 賃金支払日以降の中途採用者の当月分賃金の支払時期
Q44 賃金の端数の計算・支払い
Q45 賃金の計算違いによる過払い・不足払いの清算
Q46 賞与算定期間中勤務した者と支給日在籍者のみへの支給の定め
Q47 無断退職者・所在不明者への賃金の支払い
Q48 死亡退職金の受給権者
Q49 賃金・退職金と会社債権の相殺
Q50 最低賃金との比較において除外される賃金
Q51 パートタイマーの賃金と最低賃金の比較
Q52 賃金明細書の交付の義務
Q53 賃金・退職金の差押え
5 労働時間・休憩・休日
① 労働時間
Q54 労基法上の労働時間とは
Q55 eラーニングによる自己啓発と労働時間
Q56 始業時刻10分前までの出勤の義務
Q57 1カ月単位の変形労働時間制における月末月初の時間外労働管理
Q58 新しいフレックスタイム制
Q59 変形労働時間制と割増賃金
Q60 副業・兼業と時間外労働規制の適用
Q61 事業場外労働のみなし労働時間制とは
Q62 在宅勤務と労働時間管理
Q63 在宅勤務者の非常呼び出しの場合の通勤時間は労働時間か
Q64 企画業務型裁量労働制:対象業務に常態として従事する者
Q65 裁量労働制の見直し
② 休憩
Q66 終業時刻繰上げのための休憩カット・長時間労働と休憩の追加付与
Q67 一斉休憩・休憩の自由利用の原則と例外
③ 休日
Q68 休日と休暇の違い
Q69 労基法上の休日と国民の休日
Q70 欠勤日の休日扱い
Q71 代休と休日の振替
Q72 暦日休日の原則と例外
Q73 出張の場合の休日の取扱い
④ 時間外労働・休日労働
Q74 「過労死等ゼロ」緊急対策とは
Q75 労働者の過半数代表者の要件等
Q76 社外の人物を労働者の過半数代表者とすることの可否
Q77 過半数代表者の選出母体
Q78 時間外労働の上限規制 ①時間外労働の限度時間管理の留意点
Q79 時間外労働の上限規制 ②3カ月単位の限度時間協定,所定時間外労働時間数・所定休日労働日数の協定と三六協定の届出
Q80 時間外労働の上限規制 ③転勤の場合の限度時間の適用
Q81 時間外労働の上限規制 ④三六協定の特別条項
Q82 時間外労働の上限規制 ⑤三六協定の特別条項発動の手続
Q83 時間外労働の上限規制 ⑥令和6年4月以降の新たな上限規制の対象となる業種
Q84 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
Q85 自己申告制の残業の過少申告と使用者の管理責任
Q86 休日労働時間と新しい残業時間規制
Q87 特別条項による面接指導を行う「一定時間」とは何時間でなければならないのか
Q88 年間960時間の時間外・休日労働の可能性
Q89 長時間労働と使用者の健康管理責任
Q90 三六協定の効力範囲
Q91 3カ月単位のフレックスタイム制と三六協定・割増賃金
Q92 フレックスタイム制と労働時間の上限・下限枠の設定
Q93 フレックスタイム制と三六協定の特別条項,時間外・休日労働月100時間未満等の制約の適用
Q94 事業場外労働と三六協定・時間管理
Q95 テレワークガイドライン
Q96 裁量労働と三六協定・時間管理
Q97 裁量労働従事者の時間管理に対する使用者の指導・責任
Q98 週休2日制の場合の休日労働
Q99 休日振替と時間外労働
Q100 三六協定の従業員代表の退職と協定の効力
Q101 協定後の労働者数の増減と協定の効力
6 割増賃金
Q102 長時間労働の場合の割増賃金の特別ルール
Q103 法内超勤と割増賃金
Q104 1年以内の変形制と時間外割増賃金
Q105 所定労働時間数の変更と割増賃金
Q106 遅刻した者・半日年休を取得した者が残業した場合の割増賃金
Q107 定額残業手当
Q108 年俸制適用者についても割増賃金は別枠で支給しなければならないか
Q109 三六協定の限度を超えた残業と割増賃金
Q110 残業時間の端数はどう処理するか
Q111 休日労働と時間外・深夜手当
Q112 法定休日・法定外休日と割増賃金
Q113 休日振替・代休と割増賃金
Q114 時間外労働が深夜から翌日に及んだ場合
Q115 時間外労働が休日に及んだ場合
Q116 管理職の深夜労働と割増賃金
Q117 皆勤手当は割増賃金の算定基礎に入るか
Q118 家族手当類似の生活補助手当や住宅手当は算定基礎から除外できるか
Q119 夜勤手当は算定基礎から除外できるか
Q120 マイカー通勤者のガソリン代補給費は算定基礎に含めるか
Q121 在宅勤務における在宅勤務手当(テレワーク手当)は算定基礎に含めるか
Q122 危機管理対策としてのホテル宿泊待機は宿直の許可や割増賃金が必要か
7 年次有給休暇
Q123 パートタイマー等の休暇日数
Q124 年度の途中・年度初めに所定労働日数が変わった場合
Q125 期間雇用者と年休
Q126 定年後再雇用者の年休はどうなるか
Q127 年休はいつまで使えるのか
Q128 年休は最高何日まで利用できるか
Q129 退職の際,未消化の年休はすべて利用させなければならないか
Q130 解雇の場合,未利用年休は買い上げなければならないか
Q131 年休の出勤率算定に当たって出勤とみなす日は
Q132 遅刻・早退した日は出勤率の計算上どう評価するのか
Q133 半日単位の年休利用,時間単位の利用は可能か
Q134 欠勤・休職中の年休利用の可否
Q135 計画年休とはどのようなものか
Q136 使用者の時季指定義務とその後の変更
Q137 休職・復職者と使用者の時季指定義務
Q138 希望日の聴取と付与時季の調整
Q139 法定の出勤率要件を満たさない者への対応
Q140 いわゆるダブルトラックの場合の付与の例
Q141 年休の斉一的取扱い
Q142 年休・半日年休・時間年休の賃金
Q143 休職発令の前提となる長期欠勤は年休利用により中断されるか
Q144 賞与査定上,年休を欠勤と同視できるか
8 管理監督者・監視断続労働従事者・高度プロフェッショナル制度
Q145 労基法上の管理監督者の範囲
Q146 裁判例や行政解釈通達で見る管理監督者の考え方
Q147 出向と管理監督者の扱い
Q148 臨時的に監視断続労働に従事する場合
Q149 許可を受けた勤務態様と現実が異なる場合
Q150 高度プロフェッショナル制度導入の可否の検討
Q151 高度プロフェッショナル制度の勤務態様
9 女性・年少者の労働時間・休日・深夜労働
① 女性
Q152 女性・妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜労働
② 年少者の雇用・労働時間・休日・深夜労働
Q153 高校生等年少者をアルバイト雇用する条件
10 産前産後休業・生理休業・育児時間
Q154 産前6週間・産後8週間の計算
Q155 流産・早産と産前産後休業
Q156 産前産後の休業期間中の年休利用
Q157 育児時間はまとめて1時間利用できるか
Q158 始終業時刻に接着した育児時間利用
Q159 生理休暇は半日単位でも利用できるか
11 就業規則
Q160 正社員5人・パートタイマー5人でも就業規則は必要か。少数のアルバイト等にも専用のものが必要か
Q161 パートタイマー用就業規則作成の場合の意見を聴く相手方は
Q162 聴取した意見はどこまで規則内容に反映させなければならないか
Q163 就業規則にはいわゆる内規なども記載が必要か
Q164 就業規則と労働契約・労働協約の関係
Q165 就業規則の不利益変更と既存の労働契約
Q166 就業規則の定めと異なる労使慣行の効力
12 懲戒・賃金台帳・労働者名簿・記録の保存
Q167 減給の制裁として給与の10分の1を6カ月間減額することは違法か
Q168 賞与減額と減給の制裁の制限
Q169 降職・降格・昇給延伸は減給の制裁か
Q170 出勤停止は7日以内でなければならないのか
Q171 遅刻・早退による賃金減額と減給の制裁
Q172 賃金台帳・労働者名簿のコンピュータ処理
Q173 アルバイト・日々雇用者の賃金台帳・労働者名簿
Q174 労基法関係書類の保存年限
Q175 労基法関係書類の記録の保存方法
Q176 会社で雇用した社長の家事使用人
Q177 親族で運営する事業と労基法の適用
13 労働安全衛生法
Q178 総括安全衛生管理者は事業場のトップでなければならないのか
Q179 安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者の選任
Q180 安全管理者・衛生管理者の専属・専任の意味
Q181 産業医の二事業場兼任
Q182 産業医の機能強化と事業主の責任
Q183 産業医の選任と活動
Q184 長時間労働と医師による面接指導
Q185 労働時間の状況把握と本人等への情報提供
Q186 安全委員会・衛生委員会の活動
Q187 情報通信機器を用いた安全委員会等の開催の条件
Q188 企業全体で1つの衛生委員会とすることの可否
Q189 社員の採用と健康診断
Q190 eラーニング等による安全衛生教育等の実施条件
Q191 出向の受入れと採用時健診
Q192 健康診断実施後の措置・保健指導・面接指導
Q193 情報通信機器を用いた医師による面接指導の条件
Q194 メンタルヘルス・ストレスチェックの義務
Q195 受動喫煙防止ガイドライン
第2編 労働契約法・パート・有期雇用労働法・高年齢者雇用安定法
1 労働契約法
Q196 均衡考慮・ワークライフバランス配慮条項の意味と効果
Q197 労働契約の書面確認と理解の促進
Q198 就業規則の不利益変更と労働契約の関係
Q199 採用時の特約はいつまで有効か
Q200 有期契約の解約
Q201 有期契約の無期契約への転換
Q202 1年契約の更新回数を4回に限ることにすれば転換問題は生じないか
Q203 有期契約の更新みなし制度
Q204 有期契約の無期契約への転換の特例
2 パート・有期雇用労働法
Q205 差別的取扱いが禁止されるパート・有期雇用労働者の範囲
Q206 禁止される差別的取扱いとは何か
Q207 通常の労働者との均衡を考慮した賃金決定の努力義務
Q208 教育訓練についての規制
Q209 福利厚生制度についての配慮
Q210 通常の労働者への転換措置
Q211 雇入れ時及び求めがあった場合の説明義務と不利益取扱いの禁止
Q212 相談体制の整備と相談窓口の明示義務
Q213 勧告と公表制度
2-2 同一労働同一賃金
Q214 いわゆる日本型同一労働同一賃金とは
Q215 正規・非正規の間に仕事の差異を設ければ,均等・均衡待遇の議論は生じないのか
Q216 同一労働同一賃金ガイドライン(指針)違反の処遇の帰趨
Q217 定年前労働者と定年後継続雇用労働者の処遇格差
Q218 賃金の決定基準や算定のルールが違う場合
3 高年齢者雇用安定法
Q219 定年制と定年後継続雇用制度
Q220 継続雇用制度の雇用先の特例
Q221 経営不振を理由に継続雇用制度の一時運用停止をすることの可否
Q222 高年齢者雇用確保措置の対象者からの除外
Q223 60歳を雇止年齢とする期間雇用の場合の雇用確保措置は
Q224 再雇用対象者の雇用拒否・解雇は可能か
Q225 一定年齢以下を条件とする募集採用は許されないのか
Q226 どんな場合に高年齢者再就職援助措置や求職活動支援書が必要なのか
Q227 多数離職届はどんな場合に必要か
Q228 70歳までの就業機会確保措置
第3編 育児・介護休業法
Q229 育児・介護休業制度の概要
Q230 介護休暇・子の看護休暇の取得単位(半日単位から時間単位に)
Q231 育児休業は期間雇用者・パートタイマーにも認めなければならないか
Q232 育児休業の期間はいつまで認められるのか
Q233 育児休業期間の延長や短縮は可能か
Q234 勤続年数や継続勤務の意思があることを育児休業の条件とできるか
Q235 育児休業の回数制限
Q236 育児休業中に次の子を妊娠した場合
Q237 出生時育児休業は育児休業と何が違うのか
Q238 出生時育児休業中の就労
Q239 原職復帰は絶対条件か
Q240 育児休業の期間は勤続年数に算入するか
Q241 育児休業中の労働・社会保険料
Q242 所定労働時間の短縮措置等
Q243 所定外労働・時間外労働の制限・深夜業の制限
Q244 所定時間短縮措置やこれに代わる始業時刻変更等の措置は,従業員の希望する内容のものでなければならないか
Q245 介護休業はだれでも利用できるのか
Q246 介護休業の対象となる家族の範囲は
Q247 介護休業の期間・回数は
Q248 介護休業期間の延長や短縮は可能か
Q249 介護休業と平均賃金・年次有給休暇
Q250 勤務時間の短縮,所定外労働・時間外労働の制限
Q251 育児や介護のために退職する者についての再雇用特別措置とは何か
Q252 看護等休暇・介護休暇
第4編 男女雇用機会均等法
Q253 男女を問わず性別を理由とした差別禁止法に
Q254 女性であること・男性であることを理由にした差別とは
Q255 均等取扱いとは
Q256 コース別雇用管理制度と均等法
Q257 「間接差別」とは
Q258 家族手当・住宅貸付等の対象となる「世帯主」と間接差別
Q259 男女の勤続年数差と長期勤続者を対象とする住宅貸付制度
Q260 男女別の新入社員研修は均等法に反するのか
Q261 外部委託研修における差別的研修内容と事業主の責任
Q262 独身寮は男女共用にしなければならないのか
Q263 女性のみを対象にした「結婚退職祝金」・「仕事と子育て両立支援金」
Q264 妊娠・出産,育児休業等を理由とする不利益取扱い
Q265 マタハラについて使用者は何をしなければならないのか
Q266 セクハラ問題について使用者は何をしなければならないのか
Q267 セクハラ行為と事業主・法人の責任
Q268 雇用均等・セクハラトラブルの紛争処理システム
Q269 男性差別にならないポジティブアクションとは
第5編 労働施策総合推進法
Q270 パワハラについての事業者の義務①;定義等
Q271 パワハラについての事業者の義務②;パワハラの6類型と具体例
Q272 パワハラについての事業者の義務③;事業者が雇用管理上講ずべき措置の内容
Q273 パワハラについて,事業者が行うことが望ましい取組みの内容
Q274 パワハラについて,事業者が行うことが望ましい取組み;労働者以外の者に対する言動・顧客からの迷惑行為等
第6編 労働者派遣法
Q275 出向と労働者派遣の違い
Q276 業務請負・業務委託と労働者派遣の違い
Q277 派遣と請負の区分に関する疑義応答集
Q278 労働者派遣の利用可能な期間の改正とその影響
Q279 派遣先を離職後1年以内の者の派遣受入禁止
Q280 労働契約申込みみなし制度
Q281 派遣受入れを予定したスタッフとの事前面接
Q282 派遣先企業の責任にはどのようなことがあるのか
Q283 受入れ派遣労働者の苦情処理
Q284 派遣労働者の残業は自社従業員と同様に命じられるか
Q285 派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合
Q286 派遣先が講ずべき措置に関する指針とは
Q287 派遣先の事情や派遣労働者の勤務状況により派遣契約を解除する場合の留意事項
Q288 派遣契約中途解除の場合の雇用確保措置義務
Q289 紹介予定派遣と通常の派遣の違い
Q290 紹介予定派遣に関する事項の定めの義務化
Q291 派遣先の情報提供義務
第7編 労働組合法
Q292 外部組合からの団交要求
Q293 少数社員が結成した組合からの三六協定締結の要求
Q294 交渉議事録への署名の要求
Q295 労働条件の決定・変更についての組合への事前説明の必要性
Q296 団体交渉と労使協議の違い
Q297 互いの主張を譲らない団体交渉はいつまで続けなければならないのか
Q298 労働組合の側には誠実団交義務はないのか
Q299 組合役員の異動については,組合の同意が必要か
Q300 組合活動家の組合活動に対する懲戒処分についての留意事項
Q301 非組合員の処遇条件についても団交に応じなければならないのか
Q302 団交や労使協議での資料要求にはどこまで応じなければならないか
Q303 時間外・休憩時間中ならビラ配り等の情宣活動は会社の中でも自由にできるのか
Q304 団交のテーマや参加メンバーについては,組合の要求に応じなければならないのか
目次
第1編 労働基準法・安衛法
1 総則
Q1 正社員・嘱託・パートの違いと労働条件格差
Q2 外国人の雇用と均等待遇の原則
Q3 使用人兼務役員や執行役員は労働者か
Q4 出向者と労基法の適用関係
Q5 兼務出向と労働関係法令の適用
Q6 慶弔見舞金・住宅補助等の福利厚生的給付と労基法上の賃金
Q7 平均賃金算定の起算日
Q8 欠勤・休業期間と平均賃金の算定
Q9 通勤定期券の支給と平均賃金の算定
Q10 労基法上の権利の消滅時効の改正
2 労働契約
Q11 労基法に違反すると何が問題か
Q12 長期労働契約締結の禁止の原則と例外
Q13 雇用保障期間と長期労働契約締結の禁止の関係
Q14 期間雇用者の労働条件の明示
Q15 期間雇用者に限らない労働条件の明示
Q16 採用内定・内々定と労働条件明示義務
Q17 採用時の労働条件明示義務の対象範囲
Q18 労働契約締結時の条件明示の程度
Q19 電子メールによる労働契約締結時の労働条件明示
Q20 損害賠償の誓約書と賠償予定の禁止,秘密保持義務・競業避止義務
3 解雇・退職
Q21 採用内定者(内々定者)と労基法の適用
Q22 定年制と解雇制限
Q23 休職期間満了による退職・解雇と解雇予告
Q24 試用期間中のパワハラと欠勤休職制度の適用,解雇問題
Q25 休職期間の延長拒否は解雇となるか
Q26 有期契約の更新拒否と解雇
Q27 退職願い・退職届の撤回(取消し)
Q28 解雇予告の必要な場合・不要な場合
Q29 解雇予告除外認定
Q30 解雇予告と解雇予告手当
Q31 条件を付して解雇する,という通知の意味・有効性
Q32 解雇予告と同時に休業を命じた場合の賃金
Q33 諭旨退職・諭旨解雇と解雇予告
Q34 3カ月前の退職申出を義務付けられるか
Q35 退職金の支払時期
Q36 退職後に懲戒解雇事由が明らかになった場合
Q37 無断で欠勤し,出社しなくなった者の取扱い
4 賃金
Q38 賃金の直接払いの原則と本人以外の者への賃金の支払い
Q39 旅行積立金・会社立替金の賃金・退職金からの控除
Q40 通貨払いの原則とデジタルマネーでの賃金支払い
Q41 賃金の締切日・支払日の変更
Q42 毎月払いの原則と割増賃金の翌月支払い
Q43 賃金支払日以降の中途採用者の当月分賃金の支払時期
Q44 賃金の端数の計算・支払い
Q45 賃金の計算違いによる過払い・不足払いの清算
Q46 賞与算定期間中勤務した者と支給日在籍者のみへの支給の定め
Q47 無断退職者・所在不明者への賃金の支払い
Q48 死亡退職金の受給権者
Q49 賃金・退職金と会社債権の相殺
Q50 最低賃金との比較において除外される賃金
Q51 パートタイマーの賃金と最低賃金の比較
Q52 賃金明細書の交付の義務
Q53 賃金・退職金の差押え
5 労働時間・休憩・休日
① 労働時間
Q54 労基法上の労働時間とは
Q55 eラーニングによる自己啓発と労働時間
Q56 始業時刻10分前までの出勤の義務
Q57 1カ月単位の変形労働時間制における月末月初の時間外労働管理
Q58 新しいフレックスタイム制
Q59 変形労働時間制と割増賃金
Q60 副業・兼業と時間外労働規制の適用
Q61 事業場外労働のみなし労働時間制とは
Q62 在宅勤務と労働時間管理
Q63 在宅勤務者の非常呼び出しの場合の通勤時間は労働時間か
Q64 企画業務型裁量労働制:対象業務に常態として従事する者
Q65 裁量労働制の見直し
② 休憩
Q66 終業時刻繰上げのための休憩カット・長時間労働と休憩の追加付与
Q67 一斉休憩・休憩の自由利用の原則と例外
③ 休日
Q68 休日と休暇の違い
Q69 労基法上の休日と国民の休日
Q70 欠勤日の休日扱い
Q71 代休と休日の振替
Q72 暦日休日の原則と例外
Q73 出張の場合の休日の取扱い
④ 時間外労働・休日労働
Q74 「過労死等ゼロ」緊急対策とは
Q75 労働者の過半数代表者の要件等
Q76 社外の人物を労働者の過半数代表者とすることの可否
Q77 過半数代表者の選出母体
Q78 時間外労働の上限規制 ①時間外労働の限度時間管理の留意点
Q79 時間外労働の上限規制 ②3カ月単位の限度時間協定,所定時間外労働時間数・所定休日労働日数の協定と三六協定の届出
Q80 時間外労働の上限規制 ③転勤の場合の限度時間の適用
Q81 時間外労働の上限規制 ④三六協定の特別条項
Q82 時間外労働の上限規制 ⑤三六協定の特別条項発動の手続
Q83 時間外労働の上限規制 ⑥令和6年4月以降の新たな上限規制の対象となる業種
Q84 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
Q85 自己申告制の残業の過少申告と使用者の管理責任
Q86 休日労働時間と新しい残業時間規制
Q87 特別条項による面接指導を行う「一定時間」とは何時間でなければならないのか
Q88 年間960時間の時間外・休日労働の可能性
Q89 長時間労働と使用者の健康管理責任
Q90 三六協定の効力範囲
Q91 3カ月単位のフレックスタイム制と三六協定・割増賃金
Q92 フレックスタイム制と労働時間の上限・下限枠の設定
Q93 フレックスタイム制と三六協定の特別条項,時間外・休日労働月100時間未満等の制約の適用
Q94 事業場外労働と三六協定・時間管理
Q95 テレワークガイドライン
Q96 裁量労働と三六協定・時間管理
Q97 裁量労働従事者の時間管理に対する使用者の指導・責任
Q98 週休2日制の場合の休日労働
Q99 休日振替と時間外労働
Q100 三六協定の従業員代表の退職と協定の効力
Q101 協定後の労働者数の増減と協定の効力
6 割増賃金
Q102 長時間労働の場合の割増賃金の特別ルール
Q103 法内超勤と割増賃金
Q104 1年以内の変形制と時間外割増賃金
Q105 所定労働時間数の変更と割増賃金
Q106 遅刻した者・半日年休を取得した者が残業した場合の割増賃金
Q107 定額残業手当
Q108 年俸制適用者についても割増賃金は別枠で支給しなければならないか
Q109 三六協定の限度を超えた残業と割増賃金
Q110 残業時間の端数はどう処理するか
Q111 休日労働と時間外・深夜手当
Q112 法定休日・法定外休日と割増賃金
Q113 休日振替・代休と割増賃金
Q114 時間外労働が深夜から翌日に及んだ場合
Q115 時間外労働が休日に及んだ場合
Q116 管理職の深夜労働と割増賃金
Q117 皆勤手当は割増賃金の算定基礎に入るか
Q118 家族手当類似の生活補助手当や住宅手当は算定基礎から除外できるか
Q119 夜勤手当は算定基礎から除外できるか
Q120 マイカー通勤者のガソリン代補給費は算定基礎に含めるか
Q121 在宅勤務における在宅勤務手当(テレワーク手当)は算定基礎に含めるか
Q122 危機管理対策としてのホテル宿泊待機は宿直の許可や割増賃金が必要か
7 年次有給休暇
Q123 パートタイマー等の休暇日数
Q124 年度の途中・年度初めに所定労働日数が変わった場合
Q125 期間雇用者と年休
Q126 定年後再雇用者の年休はどうなるか
Q127 年休はいつまで使えるのか
Q128 年休は最高何日まで利用できるか
Q129 退職の際,未消化の年休はすべて利用させなければならないか
Q130 解雇の場合,未利用年休は買い上げなければならないか
Q131 年休の出勤率算定に当たって出勤とみなす日は
Q132 遅刻・早退した日は出勤率の計算上どう評価するのか
Q133 半日単位の年休利用,時間単位の利用は可能か
Q134 欠勤・休職中の年休利用の可否
Q135 計画年休とはどのようなものか
Q136 使用者の時季指定義務とその後の変更
Q137 休職・復職者と使用者の時季指定義務
Q138 希望日の聴取と付与時季の調整
Q139 法定の出勤率要件を満たさない者への対応
Q140 いわゆるダブルトラックの場合の付与の例
Q141 年休の斉一的取扱い
Q142 年休・半日年休・時間年休の賃金
Q143 休職発令の前提となる長期欠勤は年休利用により中断されるか
Q144 賞与査定上,年休を欠勤と同視できるか
8 管理監督者・監視断続労働従事者・高度プロフェッショナル制度
Q145 労基法上の管理監督者の範囲
Q146 裁判例や行政解釈通達で見る管理監督者の考え方
Q147 出向と管理監督者の扱い
Q148 臨時的に監視断続労働に従事する場合
Q149 許可を受けた勤務態様と現実が異なる場合
Q150 高度プロフェッショナル制度導入の可否の検討
Q151 高度プロフェッショナル制度の勤務態様
9 女性・年少者の労働時間・休日・深夜労働
① 女性
Q152 女性・妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜労働
② 年少者の雇用・労働時間・休日・深夜労働
Q153 高校生等年少者をアルバイト雇用する条件
10 産前産後休業・生理休業・育児時間
Q154 産前6週間・産後8週間の計算
Q155 流産・早産と産前産後休業
Q156 産前産後の休業期間中の年休利用
Q157 育児時間はまとめて1時間利用できるか
Q158 始終業時刻に接着した育児時間利用
Q159 生理休暇は半日単位でも利用できるか
11 就業規則
Q160 正社員5人・パートタイマー5人でも就業規則は必要か。少数のアルバイト等にも専用のものが必要か
Q161 パートタイマー用就業規則作成の場合の意見を聴く相手方は
Q162 聴取した意見はどこまで規則内容に反映させなければならないか
Q163 就業規則にはいわゆる内規なども記載が必要か
Q164 就業規則と労働契約・労働協約の関係
Q165 就業規則の不利益変更と既存の労働契約
Q166 就業規則の定めと異なる労使慣行の効力
12 懲戒・賃金台帳・労働者名簿・記録の保存
Q167 減給の制裁として給与の10分の1を6カ月間減額することは違法か
Q168 賞与減額と減給の制裁の制限
Q169 降職・降格・昇給延伸は減給の制裁か
Q170 出勤停止は7日以内でなければならないのか
Q171 遅刻・早退による賃金減額と減給の制裁
Q172 賃金台帳・労働者名簿のコンピュータ処理
Q173 アルバイト・日々雇用者の賃金台帳・労働者名簿
Q174 労基法関係書類の保存年限
Q175 労基法関係書類の記録の保存方法
Q176 会社で雇用した社長の家事使用人
Q177 親族で運営する事業と労基法の適用
13 労働安全衛生法
Q178 総括安全衛生管理者は事業場のトップでなければならないのか
Q179 安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者の選任
Q180 安全管理者・衛生管理者の専属・専任の意味
Q181 産業医の二事業場兼任
Q182 産業医の機能強化と事業主の責任
Q183 産業医の選任と活動
Q184 長時間労働と医師による面接指導
Q185 労働時間の状況把握と本人等への情報提供
Q186 安全委員会・衛生委員会の活動
Q187 情報通信機器を用いた安全委員会等の開催の条件
Q188 企業全体で1つの衛生委員会とすることの可否
Q189 社員の採用と健康診断
Q190 eラーニング等による安全衛生教育等の実施条件
Q191 出向の受入れと採用時健診
Q192 健康診断実施後の措置・保健指導・面接指導
Q193 情報通信機器を用いた医師による面接指導の条件
Q194 メンタルヘルス・ストレスチェックの義務
Q195 受動喫煙防止ガイドライン
第2編 労働契約法・パート・有期雇用労働法・高年齢者雇用安定法
1 労働契約法
Q196 均衡考慮・ワークライフバランス配慮条項の意味と効果
Q197 労働契約の書面確認と理解の促進
Q198 就業規則の不利益変更と労働契約の関係
Q199 採用時の特約はいつまで有効か
Q200 有期契約の解約
Q201 有期契約の無期契約への転換
Q202 1年契約の更新回数を4回に限ることにすれば転換問題は生じないか
Q203 有期契約の更新みなし制度
Q204 有期契約の無期契約への転換の特例
2 パート・有期雇用労働法
Q205 差別的取扱いが禁止されるパート・有期雇用労働者の範囲
Q206 禁止される差別的取扱いとは何か
Q207 通常の労働者との均衡を考慮した賃金決定の努力義務
Q208 教育訓練についての規制
Q209 福利厚生制度についての配慮
Q210 通常の労働者への転換措置
Q211 雇入れ時及び求めがあった場合の説明義務と不利益取扱いの禁止
Q212 相談体制の整備と相談窓口の明示義務
Q213 勧告と公表制度
2-2 同一労働同一賃金
Q214 いわゆる日本型同一労働同一賃金とは
Q215 正規・非正規の間に仕事の差異を設ければ,均等・均衡待遇の議論は生じないのか
Q216 同一労働同一賃金ガイドライン(指針)違反の処遇の帰趨
Q217 定年前労働者と定年後継続雇用労働者の処遇格差
Q218 賃金の決定基準や算定のルールが違う場合
3 高年齢者雇用安定法
Q219 定年制と定年後継続雇用制度
Q220 継続雇用制度の雇用先の特例
Q221 経営不振を理由に継続雇用制度の一時運用停止をすることの可否
Q222 高年齢者雇用確保措置の対象者からの除外
Q223 60歳を雇止年齢とする期間雇用の場合の雇用確保措置は
Q224 再雇用対象者の雇用拒否・解雇は可能か
Q225 一定年齢以下を条件とする募集採用は許されないのか
Q226 どんな場合に高年齢者再就職援助措置や求職活動支援書が必要なのか
Q227 多数離職届はどんな場合に必要か
Q228 70歳までの就業機会確保措置
第3編 育児・介護休業法
Q229 育児・介護休業制度の概要
Q230 介護休暇・子の看護休暇の取得単位(半日単位から時間単位に)
Q231 育児休業は期間雇用者・パートタイマーにも認めなければならないか
Q232 育児休業の期間はいつまで認められるのか
Q233 育児休業期間の延長や短縮は可能か
Q234 勤続年数や継続勤務の意思があることを育児休業の条件とできるか
Q235 育児休業の回数制限
Q236 育児休業中に次の子を妊娠した場合
Q237 出生時育児休業は育児休業と何が違うのか
Q238 出生時育児休業中の就労
Q239 原職復帰は絶対条件か
Q240 育児休業の期間は勤続年数に算入するか
Q241 育児休業中の労働・社会保険料
Q242 所定労働時間の短縮措置等
Q243 所定外労働・時間外労働の制限・深夜業の制限
Q244 所定時間短縮措置やこれに代わる始業時刻変更等の措置は,従業員の希望する内容のものでなければならないか
Q245 介護休業はだれでも利用できるのか
Q246 介護休業の対象となる家族の範囲は
Q247 介護休業の期間・回数は
Q248 介護休業期間の延長や短縮は可能か
Q249 介護休業と平均賃金・年次有給休暇
Q250 勤務時間の短縮,所定外労働・時間外労働の制限
Q251 育児や介護のために退職する者についての再雇用特別措置とは何か
Q252 看護等休暇・介護休暇
第4編 男女雇用機会均等法
Q253 男女を問わず性別を理由とした差別禁止法に
Q254 女性であること・男性であることを理由にした差別とは
Q255 均等取扱いとは
Q256 コース別雇用管理制度と均等法
Q257 「間接差別」とは
Q258 家族手当・住宅貸付等の対象となる「世帯主」と間接差別
Q259 男女の勤続年数差と長期勤続者を対象とする住宅貸付制度
Q260 男女別の新入社員研修は均等法に反するのか
Q261 外部委託研修における差別的研修内容と事業主の責任
Q262 独身寮は男女共用にしなければならないのか
Q263 女性のみを対象にした「結婚退職祝金」・「仕事と子育て両立支援金」
Q264 妊娠・出産,育児休業等を理由とする不利益取扱い
Q265 マタハラについて使用者は何をしなければならないのか
Q266 セクハラ問題について使用者は何をしなければならないのか
Q267 セクハラ行為と事業主・法人の責任
Q268 雇用均等・セクハラトラブルの紛争処理システム
Q269 男性差別にならないポジティブアクションとは
第5編 労働施策総合推進法
Q270 パワハラについての事業者の義務①;定義等
Q271 パワハラについての事業者の義務②;パワハラの6類型と具体例
Q272 パワハラについての事業者の義務③;事業者が雇用管理上講ずべき措置の内容
Q273 パワハラについて,事業者が行うことが望ましい取組みの内容
Q274 パワハラについて,事業者が行うことが望ましい取組み;労働者以外の者に対する言動・顧客からの迷惑行為等
第6編 労働者派遣法
Q275 出向と労働者派遣の違い
Q276 業務請負・業務委託と労働者派遣の違い
Q277 派遣と請負の区分に関する疑義応答集
Q278 労働者派遣の利用可能な期間の改正とその影響
Q279 派遣先を離職後1年以内の者の派遣受入禁止
Q280 労働契約申込みみなし制度
Q281 派遣受入れを予定したスタッフとの事前面接
Q282 派遣先企業の責任にはどのようなことがあるのか
Q283 受入れ派遣労働者の苦情処理
Q284 派遣労働者の残業は自社従業員と同様に命じられるか
Q285 派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合
Q286 派遣先が講ずべき措置に関する指針とは
Q287 派遣先の事情や派遣労働者の勤務状況により派遣契約を解除する場合の留意事項
Q288 派遣契約中途解除の場合の雇用確保措置義務
Q289 紹介予定派遣と通常の派遣の違い
Q290 紹介予定派遣に関する事項の定めの義務化
Q291 派遣先の情報提供義務
第7編 労働組合法
Q292 外部組合からの団交要求
Q293 少数社員が結成した組合からの三六協定締結の要求
Q294 交渉議事録への署名の要求
Q295 労働条件の決定・変更についての組合への事前説明の必要性
Q296 団体交渉と労使協議の違い
Q297 互いの主張を譲らない団体交渉はいつまで続けなければならないのか
Q298 労働組合の側には誠実団交義務はないのか
Q299 組合役員の異動については,組合の同意が必要か
Q300 組合活動家の組合活動に対する懲戒処分についての留意事項
Q301 非組合員の処遇条件についても団交に応じなければならないのか
Q302 団交や労使協議での資料要求にはどこまで応じなければならないか
Q303 時間外・休憩時間中ならビラ配り等の情宣活動は会社の中でも自由にできるのか
Q304 団交のテーマや参加メンバーについては,組合の要求に応じなければならないのか