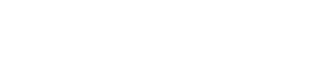判例分析 遺言の有効・無効の判断


販売価格: 6,380円 税込
- 数量
遺言の効力をめぐる理論と裁判例の傾向がわかる!
◆遺言能力の有無や遺言の有効性について裁判例と紐付けて詳しく解説しています。
◆遺言の効力をめぐる明治以降の膨大な裁判例を網羅的に取り上げ、争点と判断を一覧表形式で掲げています。
◆認知症等の医学的知見についても解説しています。
目次
序章 遺言の歴史
第1 遺言書と遺書
第2 我が国における遺言制度の成り立ちと推移
第3 遺言に関する統計
第4 遺言と相続争いとの関係
第1章 遺言無能力及び遺言無効確認訴訟一般
第1 社会情勢
第2 遺言能力の意義
1 定義
2 遺言能力の相対性
3 遺言能力の定義と実務上の位置付け
第3 遺言能力の有無を争点とする遺言無効確認訴訟の主張整理
1 訴訟物
2 請求の趣旨
3 請求原因及び攻撃防御方法
(1)請求原因
(2)抗弁以下の攻撃防御方法
4 争点の具体的提示及び主張整理の必要性
5 当事者適格等
(1)原告適格
(2)被告適格
(3)遺言執行者がある場合
(4)共同訴訟の類型
第4 遺言能力の有無の判断基準
1 裁判例から推察される判断の手法
2 医学・生物学的要因の判断要素
(1)精神疾患の特定
(2)各精神疾患の特徴
(3)疾患の特定及びその重症度の認定のための判断要素
3 遺言時点での判断能力についての法的判断
(1)遺言時及びその前後の言動等
(2)遺言内容の難易
(3)遺言内容の合理性・遺言に至る動機等
(4)遺言能力の有無に関する経験則
4 一見矛盾しているように見える裁判例の分析
(1)長谷川式簡易評価スケールが5点以下であっても遺言能力ありとされているケース
(2)長谷川式簡易評価スケールが15点以上であっても遺言能力なしとされているケース
(3)小括
第5 審理上の留意事項
1 調停前置
2 訴訟提起
(1)訴え利益
(2)管轄裁判所
(3)訴状に添付する書証の例
3 主張内容についての留意事項
(1)医学的要素に関する主張
(2)医学的要素以外の遺言能力の評価根拠事実・評価障害事実に関する主張
4 立証について
(1)書証関係
(2)鑑定
(3)人証
5 審理期間等
6 訴訟の終局場面(和解)について
第6 まとめ
○別表1<精神上の疾患の重症度を推認させる関連事情の一覧表>
○別表2<裁判所の鑑定が実施された判例について>
資料1 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
資料2 Mini-Mental State(MMS)
第2章 遺言者の意思表示の瑕疵・欠缺
第1 身分行為である遺言に意思表示の規定の適用があるか
第2 遺言と虚偽表示
第3 遺言と心裡留保・意思の欠缺
第4 遺言と錯誤
第5 遺言と強迫・詐欺
第3章 法律行為としての有効要件の欠如
第1 総説
第2 確定可能性の要件
第3 遺言と確定可能性の要件
第4 実現可能性の要件
第5 遺言と実現可能性の要件
第6 適法性の要件
第7 遺言と適法性の要件
第8 いわゆる「跡継ぎ遺贈」
第9 社会的妥当性の要件
第10 遺言と社会的妥当性の要件
1 相続1人のみに対する遺贈
2 事情変更と公序良俗違反
3 不貞相手にたいする遺贈
(1)総説
(2)裁判例
(3)まとめ
第4章 法定の形式的要件の欠如
第1節 自筆証書遺言
第1 要式行為としての遺言
第2 方式の厳格性の緩和とその限界
第3 「氏名」の要件
1 趣旨
2 「氏」を欠く場合
3 同姓同名の場合
4 通称名の使用の可否
5 氏名の記載場所
6 遺言書上に氏名がニつ記載されている場合
第4 「押印」の要件
1 趣旨
2 実印の要否
3 拇印・指印の可否
4 サインの可否
5 「封印」を「押印」に代えられるか
6 「契印」の要否
7 「割印」の要否
8 いわゆる「花押」を「押印」に代えられるか
9 押印の代行の可否
10 押印のない遺言書の効力
(1)有効とした裁判例
(2)無効とした裁判例
11 押印が2個ある場合
第5 「日付」の記載
1 趣旨
2 日付の記載のない遺言書の効力
3 「年月」の記載はあるが「日」の記載のない遺言書の効力
4 日付らしき記載はあるものの多義的である場合
5 「吉日」と記載した遺言書の効力
6 「末日」と記載した遺言書の効力
7 「正月」と記載した遺言書の効力
8 日付の記載と遺言書の実際の作成日が異なっていた場合の遺言書の効力
9 日付の記載を数字のみで行った遺言書の効力
10 日付の記載場所
11 日付の後に「より」と記載された遺言書の効力
12 日付の記載が複数ある場合の遺言書の効力
13 日付の誤記と遺言書の効力
14 誤記とは認められない不実の日付の記載と遺言書の効力
15 危急時遺言の日付の記載の要否
第6 「全文」・「自書」の要件
1 意義・趣旨
2 民法改正と「全文」・「自書」の例外
3 目の見えない人の「自書」の可否
4 他人が作成した書面に遺言者が署名した場合の効力
5 カーボン紙の使用と「自書」
6 タイプライターの使用と「自書」
7 図面の使用と「自書」
8 遺言書の偽造
(1)総説
(2)自書性を肯定した裁判例
(3)自書性を否定した裁判例
9 他人による添え手と「自書」
(1)無効とした裁判例
(2)有効とした裁判例
10 録音・映像による遺言の可否
11 筆記具と記録媒体の問題
第2節 公正証書遺言
第1 公正証書遺言の作成手続
第2 証人の立会いとその趣旨
第3 証人欠格者
第4 証人・立会人欠格者の範囲
第5 耳・目の不自由な者の証人適格
第6 証人適格者と証人欠格者が立ち会った遺言書の効力
第7 証人の立会い時期
第8 証人の立会いを欠く遺言書の効力
1 遺言書を無効とした裁判例
2 遺言書を有効とした裁判例
第9 署名の代行の可否
第10 押印の代行の可否
第11 公証人の署名の有無が争われた裁判例
第12 本人確認手続に関する誤記と遺言書の効力
第13 秘密証書遺言における「筆者」の意義
第14 「口授」について
1 趣旨等
2 口頭を伴わない身体的挙動と「口授」
3 「口授」と遺言能力の関係
4 「口授」と伝達機関
5 「口授」を肯定した裁判例
6 「口授」はどこまで具体的に行うのか
7 「口授」と「筆記」の順序
8 文案・メモ等の使用と「口授」
9 筆記の場所は遺言者の面前に限られるか、及び筆記の代行の可否
10 読み聞かせの代行の可否
第15 危急時遺言における「口授」の要件
1 公正証書遺言の場合と同じか
2 「口授」と「筆記」の順序
3 口授の場所と筆記の場所が異なっていてもよいか
4 確認の申立期間等
第5章 共同遺言の禁止
第1 趣旨
第2 共同遺言とは認められなかった裁判例
第3 共同遺言と認められ無効とされた裁判例
第6章 遺言の撤回及び取消し
第 1総説
第 2法定撤回
1 抵触遺言による撤回擬制
2 遺言後の生前処分その他の法律行為による撤回擬制
3 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
第7章 遺言の代理の禁止
第1 総説
第2 遺言書を無効とした裁判例
第3 遺言書を有効とした裁判例
第8章 遺言書の隠匿・破棄等
第1 隠匿
第2 偽造・変造
第3 破棄
第9章 遺言書の加除・訂正
第1 意義・趣旨
第
◆遺言能力の有無や遺言の有効性について裁判例と紐付けて詳しく解説しています。
◆遺言の効力をめぐる明治以降の膨大な裁判例を網羅的に取り上げ、争点と判断を一覧表形式で掲げています。
◆認知症等の医学的知見についても解説しています。
目次
序章 遺言の歴史
第1 遺言書と遺書
第2 我が国における遺言制度の成り立ちと推移
第3 遺言に関する統計
第4 遺言と相続争いとの関係
第1章 遺言無能力及び遺言無効確認訴訟一般
第1 社会情勢
第2 遺言能力の意義
1 定義
2 遺言能力の相対性
3 遺言能力の定義と実務上の位置付け
第3 遺言能力の有無を争点とする遺言無効確認訴訟の主張整理
1 訴訟物
2 請求の趣旨
3 請求原因及び攻撃防御方法
(1)請求原因
(2)抗弁以下の攻撃防御方法
4 争点の具体的提示及び主張整理の必要性
5 当事者適格等
(1)原告適格
(2)被告適格
(3)遺言執行者がある場合
(4)共同訴訟の類型
第4 遺言能力の有無の判断基準
1 裁判例から推察される判断の手法
2 医学・生物学的要因の判断要素
(1)精神疾患の特定
(2)各精神疾患の特徴
(3)疾患の特定及びその重症度の認定のための判断要素
3 遺言時点での判断能力についての法的判断
(1)遺言時及びその前後の言動等
(2)遺言内容の難易
(3)遺言内容の合理性・遺言に至る動機等
(4)遺言能力の有無に関する経験則
4 一見矛盾しているように見える裁判例の分析
(1)長谷川式簡易評価スケールが5点以下であっても遺言能力ありとされているケース
(2)長谷川式簡易評価スケールが15点以上であっても遺言能力なしとされているケース
(3)小括
第5 審理上の留意事項
1 調停前置
2 訴訟提起
(1)訴え利益
(2)管轄裁判所
(3)訴状に添付する書証の例
3 主張内容についての留意事項
(1)医学的要素に関する主張
(2)医学的要素以外の遺言能力の評価根拠事実・評価障害事実に関する主張
4 立証について
(1)書証関係
(2)鑑定
(3)人証
5 審理期間等
6 訴訟の終局場面(和解)について
第6 まとめ
○別表1<精神上の疾患の重症度を推認させる関連事情の一覧表>
○別表2<裁判所の鑑定が実施された判例について>
資料1 改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
資料2 Mini-Mental State(MMS)
第2章 遺言者の意思表示の瑕疵・欠缺
第1 身分行為である遺言に意思表示の規定の適用があるか
第2 遺言と虚偽表示
第3 遺言と心裡留保・意思の欠缺
第4 遺言と錯誤
第5 遺言と強迫・詐欺
第3章 法律行為としての有効要件の欠如
第1 総説
第2 確定可能性の要件
第3 遺言と確定可能性の要件
第4 実現可能性の要件
第5 遺言と実現可能性の要件
第6 適法性の要件
第7 遺言と適法性の要件
第8 いわゆる「跡継ぎ遺贈」
第9 社会的妥当性の要件
第10 遺言と社会的妥当性の要件
1 相続1人のみに対する遺贈
2 事情変更と公序良俗違反
3 不貞相手にたいする遺贈
(1)総説
(2)裁判例
(3)まとめ
第4章 法定の形式的要件の欠如
第1節 自筆証書遺言
第1 要式行為としての遺言
第2 方式の厳格性の緩和とその限界
第3 「氏名」の要件
1 趣旨
2 「氏」を欠く場合
3 同姓同名の場合
4 通称名の使用の可否
5 氏名の記載場所
6 遺言書上に氏名がニつ記載されている場合
第4 「押印」の要件
1 趣旨
2 実印の要否
3 拇印・指印の可否
4 サインの可否
5 「封印」を「押印」に代えられるか
6 「契印」の要否
7 「割印」の要否
8 いわゆる「花押」を「押印」に代えられるか
9 押印の代行の可否
10 押印のない遺言書の効力
(1)有効とした裁判例
(2)無効とした裁判例
11 押印が2個ある場合
第5 「日付」の記載
1 趣旨
2 日付の記載のない遺言書の効力
3 「年月」の記載はあるが「日」の記載のない遺言書の効力
4 日付らしき記載はあるものの多義的である場合
5 「吉日」と記載した遺言書の効力
6 「末日」と記載した遺言書の効力
7 「正月」と記載した遺言書の効力
8 日付の記載と遺言書の実際の作成日が異なっていた場合の遺言書の効力
9 日付の記載を数字のみで行った遺言書の効力
10 日付の記載場所
11 日付の後に「より」と記載された遺言書の効力
12 日付の記載が複数ある場合の遺言書の効力
13 日付の誤記と遺言書の効力
14 誤記とは認められない不実の日付の記載と遺言書の効力
15 危急時遺言の日付の記載の要否
第6 「全文」・「自書」の要件
1 意義・趣旨
2 民法改正と「全文」・「自書」の例外
3 目の見えない人の「自書」の可否
4 他人が作成した書面に遺言者が署名した場合の効力
5 カーボン紙の使用と「自書」
6 タイプライターの使用と「自書」
7 図面の使用と「自書」
8 遺言書の偽造
(1)総説
(2)自書性を肯定した裁判例
(3)自書性を否定した裁判例
9 他人による添え手と「自書」
(1)無効とした裁判例
(2)有効とした裁判例
10 録音・映像による遺言の可否
11 筆記具と記録媒体の問題
第2節 公正証書遺言
第1 公正証書遺言の作成手続
第2 証人の立会いとその趣旨
第3 証人欠格者
第4 証人・立会人欠格者の範囲
第5 耳・目の不自由な者の証人適格
第6 証人適格者と証人欠格者が立ち会った遺言書の効力
第7 証人の立会い時期
第8 証人の立会いを欠く遺言書の効力
1 遺言書を無効とした裁判例
2 遺言書を有効とした裁判例
第9 署名の代行の可否
第10 押印の代行の可否
第11 公証人の署名の有無が争われた裁判例
第12 本人確認手続に関する誤記と遺言書の効力
第13 秘密証書遺言における「筆者」の意義
第14 「口授」について
1 趣旨等
2 口頭を伴わない身体的挙動と「口授」
3 「口授」と遺言能力の関係
4 「口授」と伝達機関
5 「口授」を肯定した裁判例
6 「口授」はどこまで具体的に行うのか
7 「口授」と「筆記」の順序
8 文案・メモ等の使用と「口授」
9 筆記の場所は遺言者の面前に限られるか、及び筆記の代行の可否
10 読み聞かせの代行の可否
第15 危急時遺言における「口授」の要件
1 公正証書遺言の場合と同じか
2 「口授」と「筆記」の順序
3 口授の場所と筆記の場所が異なっていてもよいか
4 確認の申立期間等
第5章 共同遺言の禁止
第1 趣旨
第2 共同遺言とは認められなかった裁判例
第3 共同遺言と認められ無効とされた裁判例
第6章 遺言の撤回及び取消し
第 1総説
第 2法定撤回
1 抵触遺言による撤回擬制
2 遺言後の生前処分その他の法律行為による撤回擬制
3 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
第7章 遺言の代理の禁止
第1 総説
第2 遺言書を無効とした裁判例
第3 遺言書を有効とした裁判例
第8章 遺言書の隠匿・破棄等
第1 隠匿
第2 偽造・変造
第3 破棄
第9章 遺言書の加除・訂正
第1 意義・趣旨
第