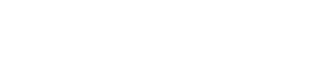日本銀行 虚像と実像 検証25年緩和
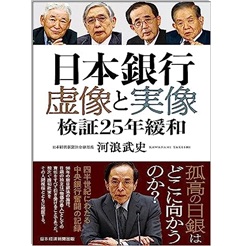
販売価格: 1,980円 税込
- 数量
停滞が続く日本経済。閉塞感とポピュリズムが同時に強まる間、日銀はスケープゴートにされ、ラストリゾートにされ、常に主役の一人で居続けた。速水氏、福井氏、白川氏、黒田氏、そして植田氏と、日銀トップが何を考え、裏で誰が動き、結果として日本経済に何をもたらしたのか。歴史的事実を掘り起こしながら、25年間の日銀緩和を検証する。
●日銀の25年を検証。
98年の新日銀法は、日銀の独立性を高め、自由度も高めたはずだったが、それぞれの総裁が政争に巻き込まれ、手足を縛られる状態が続いた。リーマン・ショック、東日本大震災の前後には政権交代などもあり、方針は二転三転。「日銀の独立」を主張したことで、そっぽを向かれた総裁もいた。
本書は4月の新総裁誕生とともに日銀に注目が集まる中、これまでの25年を振り返る内容。人事抗争なども精緻に書かれ、金融読み物として読む人を飽きさせない。「誰も総裁をやりたくない」とまで言われる日銀の課題は何かを、過去から検証する。
【目次】
1章)初の経済学者総裁、植田氏
日銀候補の本命とされた雨宮氏は官邸からの打診を固辞し続けた。山口広秀元副総裁、森信親元金融庁長官らが候補に挙がる中、岸田官邸が最終的に選んだのは、初の経済学者総裁となる植田和男元東大教授だった。その人選を後押ししたのは、なんと本命候補だった雨宮氏。植田氏は初回の金融政策決定会合で「25年間の金融緩和のレビューを開始する」と宣言。日銀は長期の金融緩和の修正へと動き出した。
2章)アベノミクス、世紀の実験
日銀の異次元緩和の仕掛け人は誰か。安倍晋三首相の周囲に集まる衆院議員、元財務官僚、リフレ派学者が「アベノミクス」をつくり上げた。その大元にいるのは、バーナンキ氏、クルーグマン氏といった米国のマクロ経済学者だ。安倍官邸が総裁候補として検討したのは4人。最終的に黒田東彦氏が選ばれたが、本命候補は別にいた。13年4月の量的・質的金融緩和は「黒田バズーカ」と呼ばれたが、そこには日銀の組織防衛を目的とするいくつかの仕掛けがあった。円安誘導によって2%のインフレ目標の達成が近づいたかにみえたが…。
3章)最長総裁、黒田氏の無念
10年間という歴代最長の任期となった黒田総裁。退任直前の22年12月、突如として異次元緩和の修正に追い込まれた。静かに圧力をかけたのは古巣の財務省。そこには国内マネーが日本から逃げ出すキャピタルフライトへの焦りがあった。インフレ率は目標の2%をついに突破。それでも日銀は、大手を振って金融緩和を解除できない。膨張した国家財政、低金利に慣れきった民間企業…。長期緩和のツケが黒田氏の異次元緩和の成功を最後に阻んだ。
4章)「アクシデントの総裁」白川氏
日銀総裁人事が政争の具になった08年。福田政権の武藤昇格案は、ねじれ国会の中で野党民主党に否決される。急きょ、登板したのは白川方明氏。最初のG7で自らを「Accidental Governorだ」と紹介して場を和ませたが、その後はまさにアクシデントの連続だった。リーマン・ショック、東日本大震災、相次ぐ政権交代…。歴史的な円高にも見舞われ、白川日銀は政治、財界からの緩和圧力を受け続けた。政府との「アコード」を受け入れて白川氏が最後に決断するのは、任期終了直前の辞任だった。
5章)デフレの始まり、福井氏・速水氏
1998年、日銀は新法で政策運営の独立性を勝ち取った。皮肉にもそのとき深刻化していたのは平成金融危機と長期デフレだった。新日銀法下での初代総裁となった速水優氏は、ゼロ金利、量的緩和と大胆な策を打ち出すが、金融危機もデフレも止まらない。03年に総裁に就いた本命・福井俊彦氏は「動く日銀」を印象づけたものの、量的緩和解除によって安倍晋三氏の日銀批判を招く。バブル崩壊後の問題の先送りが、日本経済を脱出困難な長期停滞に追いやるとは、このとき誰も想像していなかった。
6章)苦悶のパウエルFRB
トランプ米大統領によって指名されたパウエルFRB議長。「ミスター普通」と呼ばれる同氏が闘うことになるのは、人類を危機に陥れた新型コロナウイルスだった。FRBは歴史的なインフレを阻止できず、急激な利上げを余儀なくされて地方銀行の連鎖破綻まで引き起こしてしまう。筆者は「マエストロ」と称されたグリーンスパン元FRB議長を訪れて、金融政策の本質を問う。その回答は、自らを神格化した「金融政策万能論」への率直な疑念だった。
7章)魔法の杖はない
日本経済は長期停滞にある。90年代以降の投資減退が日本の潜在成長力を損ない、それによる成長期待の弱まりがさらに投資減退を呼ぶ負の循環にある。賃下げを受け入れる特異な社会風土が長期デフレの一因となった。魔法の杖にすがりつきたい人々の心理が、安易な金融緩和頼みの土壌を生んだ。日本経済を再生するには、イノベーションにつながる地道な改革を積み重ねるしかない。