裁判所における少年事件の実務 THE BASICS AND BEYOND

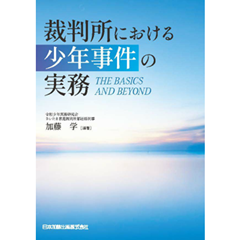
販売価格: 4,950円 税込
少年事件の“いま”を読み解く――実務の現場に直結する知見が凝縮!
令和少年実務研究会(※肩書は発刊当時のものです)
加藤学(さいたま家庭裁判所部総括判事)
岩﨑貴彦(横浜地方裁判所小田原支部判事)
河畑勇(東京地方裁判所立川支部判事)
佐藤傑(東京高等裁判所判事)
柴田雅司(仙台高等裁判所判事)
髙田浩平(最高裁判所事務総局家庭局付)
福嶋一訓(司法研修所刑事裁判教官)
藤永祐介(大阪地方裁判所判事)
横澤慶太(東京地方裁判所判事)
● 従来の文献では得られない、裁判所の判断基準とノウハウを凝縮 少年事件の流れに沿った具体的な事例を通じて、裁判官がどのような思考で判断をしているのか、そのプロセスを詳細に解説。
● 現場の生の声が詰まった座談会 裁判官だけでなく、弁護士、書記官、調査官も参加。各専門職の役割や、より良い連携の在り方がわかる。
● 実務上の課題解決に直結 審判運営上の工夫や、事件係属時の対応など、他の書籍にはない実践的なノウハウが満載。
● 『家庭の法と裁判』で好評を博した連載を、令和3年改正少年法の最新運用状況を反映し、加筆・再編成。
<例えばこんな実務に役立つ!>
■裁判所
現場の課題解決に直結
少年事件の性質が変化する中で生じる新たな論点に対し、現職裁判官が自らの経験に基づいた判断基準や考え方を解説しており、日々の業務における具体的な指針となる。
実務上の工夫やノウハウの共有
審判運営上の工夫や、事件係属時・審判前の準備など、他の書籍では触れられていない実務上の工夫を詳細に紹介している。座談会形式のパートでは、書記官や調査官も交えた議論が掲載されており、部署内での知識共有にも役立つ。
■弁護士
裁判所の「思考回路」がわかる
現職裁判官がどのような視点で事件を捉え、判断を下しているのか、その思考プロセスを理解できる。これにより、より効果的な弁護方針を立てることが可能になる。
付添人活動のヒントが満載
実際の事例研究を通じて、少年事件における付添人として留意すべき点や、裁判所との連携のあり方が具体的にわかる。座談会には付添人弁護士も参加しており、率直な意見交換が反映されている。
実務のアップデートに最適
令和3年改正少年法の施行後の運用状況や、それに伴う新たな論点について解説しているため、最新の実務動向を効率的にキャッチアップできる。
■書記官・調査官
各専門職の役割と連携の理解
裁判官だけでなく、調査官や書記官も交えた座談会形式のパートが用意されており、それぞれの専門職が事件全体の中でどのような役割を果たし、どのように連携すべきかがわかる。
職場の課題解決へのヒント
少年を取り巻く環境の変化に伴い生じる新たな課題について、他の裁判官や専門家がどのように考え、対処しているのかを知ることで、自部署の運営や工夫の参考にすることができる。
少年事件に携わるすべての実務家に確かな指針を示す一冊!
目次
第1部 少年事件の実務上の諸問題
1 移送・回付をめぐる諸問題
設問1 少年が両親宅から家出している場合の両親の住所地への移送
設問2 少年が単身居住する住所地への移送
設問3 少年の進学先の住所地への移送
設問4 少年事件の併合管轄
設問5 付添人の意向と移送
設問6 否認事件の移送
設問7 年齢切迫事件の移送
設問8 原則検察官送致対象事件・裁判員対象事件の移送
設問9 少年事件の回付
設問10 収容継続申請事件の移送
設問11 再度の強制的措置許可申請事件の移送
2 観護措置をめぐる諸問題
設問1 複数事件が係属する場合の観護措置の可否
設問2 A事実で観護措置中の少年をB事実で逮捕することの可否・当否
設問3 みなし観護措置の際の告知と聴聞,付添人選任権告知の要否
設問4 期間満了と異議申立ての利益
3 国選付添人をめぐる諸問題
設問1 家庭裁判所の裁量による国選付添人の選任要件及び基準とその実情
設問2 管轄区域外の弁護士の国選付添人選任
設問3 国選付添人の複数選任の可否及び基準
設問4 裁量国選付添人の権限が及ぶ事件の範囲
4 年齢切迫事件をめぐる諸問題
設問1 「少年」=「20歳に満たない者」の意義
設問2 年齢切迫少年への対応①〔観護措置等〕
設問3 年齢切迫少年への対応②〔余罪がある場合の処遇判断等〕
5 児童相談所長からの送致事件に関する諸問題
設問1 一時保護中の少年の観護措置
設問2 非行事実の審理・認定(補強証拠の要否等)
設問3 非行事実の審理・認定(調査票の利用)
設問4 児童自立支援施設送致に係る処遇判断等
設問5 強制的措置許可申請事件
6 ぐ犯保護事件の諸問題(その1)
設問1 事件受理に当たっての留意点
設問2 ぐ犯事実の認定に当たっての留意点
設問3 ぐ犯事実と犯罪事実が同時に係属した場合の問題
設問4 試験観察中のぐ犯と再度の観護措置をめぐる問題
7 ぐ犯保護事件の諸問題(その2)
設問 犯罪保護事件とそれに吸収されるぐ犯保護事件が係属した場合等の諸問題
8 検察官送致に関する諸問題
設問1 身柄事件の検察官送致に伴う諸問題
設問2 他庁から移送を受けた事件の身柄付き検察官送致に伴う諸問題
設問3 在宅事件の検察官送致に伴う諸問題
9 原則検察官送致対象事件に関する諸問題(被害者に関する諸制度を含む)
設問 原則検察官送致対象事件の判断枠組み,受理時の対応の在り方,被害者関係の諸制度
10 責任能力の要否
設問 保護処分賦課と責任能力
11 少年事件と精神保健福祉法、医療観察法
設問1 精神保健福祉法,少年法,医療観察法による医療等
設問2 少年事件と精神保健福祉法
設問3 心神喪失の少年と医療観察法
設問4 措置権行使における都道府県知事と指定医の役割分担
12 特定少年の保護処分及び18歳年迫少年の審判運営等をめぐる諸問題
設問1 少年院送致の許容性及び収容期間の定め方等
設問2 2年の保護観察の許容性及び少年院への収容可能期間の定め方
設問3 18歳年迫少年の審判運営,観護措置
設問4 18歳年迫少年の試験観察,特定少年の親の取扱い
第2部 座談会 少年事件の調査・審判の工夫
1 少年事件の調査・審判
第1 事件係属当初の検討
第2 調査進行中の連携
第3 審判直前の準備
1 少年調査票・鑑別結果通知書
2 付添人の意見書
3 審判直前の裁判所の準備
第4 審判での工夫
1 非行事実の確認
2 要保護性の審理
3 少年に語らせること
4 保護者への質問
5 調査官・付添人の視点
第5 決定告知の工夫
2 非行事実に争いがある事件の審理
第1 早期の審理計画の策定
1 送付された記録の読込み
2 国選付添人選任の要否
3 検察官関与の要否
4 家庭裁判所,付添人,検察官の打合せ
第2 証拠調べ等
1 少年本人質問
2 証人尋問
3 主観的併合
4 補充捜査
第3 認定事実の告知
1 中間審判での告知
2 告知内容と審判調書の記載
第4 社会調査
1 調査時期
2 調査命令を出す時期
第5 裁定合議
1 合議にすべき事件
2 審理の工夫─受命裁判官
3 記録のコピー
第6 全体的なスケジュール感
3 試験観察の実際
第1 どのような場合に試験観察に付するか
1 収容処遇と在宅処遇の見極め
2 環境調整,教育的措置の活用,被害弁償を目的とすることの可否
3 身柄付き補導委託
4 在宅事件での試験観察
第2 試験観察決定前にすべきこと
1 裁判所,調査官及び付添人の連携
2 少年及び保護者への働きかけ
第3 試験観察中の調査,教育的措置,社会資源,付添人との連携
1 試験観察中の調査,教育的措置
2 社会資源,付添人との連携
3 少年鑑別所との連携
4 短期補導委託の活用
第4 低調な場合や不良行状時の対応
1 低調な場合の対応
2 不良行状時の対応
3 少年院送致になった事例の受止め
補論 家庭裁判所からみた弁護士付添人との連携と協働 ─カンファレンスの在り方を中心に─
第1 はじめに
第2 裁判所における少年審判の審理
1 事件受理時の検討
2 調査進行中の調査官との連携とカンファレンス
3 審判運営と処遇選択
第3 裁判所が期待する付添人活動の視点
第4 非行事実の審理における連携(主に否認事件)
1 早期の記録閲覧と主張立証方針の検討
2 非行事実の争点整理等のための早期カンファレンス
3 まとめと具体例
第5 要保護性の審理における連携(主に自白事件)
1 少年に対する働きかけや環境調整活動
2 審理の過程を踏まえた随時の主張や活動報告
3 付添人中間カンファレンス
4 まとめと具体例
第6 おわりに
判例索引
事項索引
令和少年実務研究会(※肩書は発刊当時のものです)
加藤学(さいたま家庭裁判所部総括判事)
岩﨑貴彦(横浜地方裁判所小田原支部判事)
河畑勇(東京地方裁判所立川支部判事)
佐藤傑(東京高等裁判所判事)
柴田雅司(仙台高等裁判所判事)
髙田浩平(最高裁判所事務総局家庭局付)
福嶋一訓(司法研修所刑事裁判教官)
藤永祐介(大阪地方裁判所判事)
横澤慶太(東京地方裁判所判事)
● 従来の文献では得られない、裁判所の判断基準とノウハウを凝縮 少年事件の流れに沿った具体的な事例を通じて、裁判官がどのような思考で判断をしているのか、そのプロセスを詳細に解説。
● 現場の生の声が詰まった座談会 裁判官だけでなく、弁護士、書記官、調査官も参加。各専門職の役割や、より良い連携の在り方がわかる。
● 実務上の課題解決に直結 審判運営上の工夫や、事件係属時の対応など、他の書籍にはない実践的なノウハウが満載。
● 『家庭の法と裁判』で好評を博した連載を、令和3年改正少年法の最新運用状況を反映し、加筆・再編成。
<例えばこんな実務に役立つ!>
■裁判所
現場の課題解決に直結
少年事件の性質が変化する中で生じる新たな論点に対し、現職裁判官が自らの経験に基づいた判断基準や考え方を解説しており、日々の業務における具体的な指針となる。
実務上の工夫やノウハウの共有
審判運営上の工夫や、事件係属時・審判前の準備など、他の書籍では触れられていない実務上の工夫を詳細に紹介している。座談会形式のパートでは、書記官や調査官も交えた議論が掲載されており、部署内での知識共有にも役立つ。
■弁護士
裁判所の「思考回路」がわかる
現職裁判官がどのような視点で事件を捉え、判断を下しているのか、その思考プロセスを理解できる。これにより、より効果的な弁護方針を立てることが可能になる。
付添人活動のヒントが満載
実際の事例研究を通じて、少年事件における付添人として留意すべき点や、裁判所との連携のあり方が具体的にわかる。座談会には付添人弁護士も参加しており、率直な意見交換が反映されている。
実務のアップデートに最適
令和3年改正少年法の施行後の運用状況や、それに伴う新たな論点について解説しているため、最新の実務動向を効率的にキャッチアップできる。
■書記官・調査官
各専門職の役割と連携の理解
裁判官だけでなく、調査官や書記官も交えた座談会形式のパートが用意されており、それぞれの専門職が事件全体の中でどのような役割を果たし、どのように連携すべきかがわかる。
職場の課題解決へのヒント
少年を取り巻く環境の変化に伴い生じる新たな課題について、他の裁判官や専門家がどのように考え、対処しているのかを知ることで、自部署の運営や工夫の参考にすることができる。
少年事件に携わるすべての実務家に確かな指針を示す一冊!
目次
第1部 少年事件の実務上の諸問題
1 移送・回付をめぐる諸問題
設問1 少年が両親宅から家出している場合の両親の住所地への移送
設問2 少年が単身居住する住所地への移送
設問3 少年の進学先の住所地への移送
設問4 少年事件の併合管轄
設問5 付添人の意向と移送
設問6 否認事件の移送
設問7 年齢切迫事件の移送
設問8 原則検察官送致対象事件・裁判員対象事件の移送
設問9 少年事件の回付
設問10 収容継続申請事件の移送
設問11 再度の強制的措置許可申請事件の移送
2 観護措置をめぐる諸問題
設問1 複数事件が係属する場合の観護措置の可否
設問2 A事実で観護措置中の少年をB事実で逮捕することの可否・当否
設問3 みなし観護措置の際の告知と聴聞,付添人選任権告知の要否
設問4 期間満了と異議申立ての利益
3 国選付添人をめぐる諸問題
設問1 家庭裁判所の裁量による国選付添人の選任要件及び基準とその実情
設問2 管轄区域外の弁護士の国選付添人選任
設問3 国選付添人の複数選任の可否及び基準
設問4 裁量国選付添人の権限が及ぶ事件の範囲
4 年齢切迫事件をめぐる諸問題
設問1 「少年」=「20歳に満たない者」の意義
設問2 年齢切迫少年への対応①〔観護措置等〕
設問3 年齢切迫少年への対応②〔余罪がある場合の処遇判断等〕
5 児童相談所長からの送致事件に関する諸問題
設問1 一時保護中の少年の観護措置
設問2 非行事実の審理・認定(補強証拠の要否等)
設問3 非行事実の審理・認定(調査票の利用)
設問4 児童自立支援施設送致に係る処遇判断等
設問5 強制的措置許可申請事件
6 ぐ犯保護事件の諸問題(その1)
設問1 事件受理に当たっての留意点
設問2 ぐ犯事実の認定に当たっての留意点
設問3 ぐ犯事実と犯罪事実が同時に係属した場合の問題
設問4 試験観察中のぐ犯と再度の観護措置をめぐる問題
7 ぐ犯保護事件の諸問題(その2)
設問 犯罪保護事件とそれに吸収されるぐ犯保護事件が係属した場合等の諸問題
8 検察官送致に関する諸問題
設問1 身柄事件の検察官送致に伴う諸問題
設問2 他庁から移送を受けた事件の身柄付き検察官送致に伴う諸問題
設問3 在宅事件の検察官送致に伴う諸問題
9 原則検察官送致対象事件に関する諸問題(被害者に関する諸制度を含む)
設問 原則検察官送致対象事件の判断枠組み,受理時の対応の在り方,被害者関係の諸制度
10 責任能力の要否
設問 保護処分賦課と責任能力
11 少年事件と精神保健福祉法、医療観察法
設問1 精神保健福祉法,少年法,医療観察法による医療等
設問2 少年事件と精神保健福祉法
設問3 心神喪失の少年と医療観察法
設問4 措置権行使における都道府県知事と指定医の役割分担
12 特定少年の保護処分及び18歳年迫少年の審判運営等をめぐる諸問題
設問1 少年院送致の許容性及び収容期間の定め方等
設問2 2年の保護観察の許容性及び少年院への収容可能期間の定め方
設問3 18歳年迫少年の審判運営,観護措置
設問4 18歳年迫少年の試験観察,特定少年の親の取扱い
第2部 座談会 少年事件の調査・審判の工夫
1 少年事件の調査・審判
第1 事件係属当初の検討
第2 調査進行中の連携
第3 審判直前の準備
1 少年調査票・鑑別結果通知書
2 付添人の意見書
3 審判直前の裁判所の準備
第4 審判での工夫
1 非行事実の確認
2 要保護性の審理
3 少年に語らせること
4 保護者への質問
5 調査官・付添人の視点
第5 決定告知の工夫
2 非行事実に争いがある事件の審理
第1 早期の審理計画の策定
1 送付された記録の読込み
2 国選付添人選任の要否
3 検察官関与の要否
4 家庭裁判所,付添人,検察官の打合せ
第2 証拠調べ等
1 少年本人質問
2 証人尋問
3 主観的併合
4 補充捜査
第3 認定事実の告知
1 中間審判での告知
2 告知内容と審判調書の記載
第4 社会調査
1 調査時期
2 調査命令を出す時期
第5 裁定合議
1 合議にすべき事件
2 審理の工夫─受命裁判官
3 記録のコピー
第6 全体的なスケジュール感
3 試験観察の実際
第1 どのような場合に試験観察に付するか
1 収容処遇と在宅処遇の見極め
2 環境調整,教育的措置の活用,被害弁償を目的とすることの可否
3 身柄付き補導委託
4 在宅事件での試験観察
第2 試験観察決定前にすべきこと
1 裁判所,調査官及び付添人の連携
2 少年及び保護者への働きかけ
第3 試験観察中の調査,教育的措置,社会資源,付添人との連携
1 試験観察中の調査,教育的措置
2 社会資源,付添人との連携
3 少年鑑別所との連携
4 短期補導委託の活用
第4 低調な場合や不良行状時の対応
1 低調な場合の対応
2 不良行状時の対応
3 少年院送致になった事例の受止め
補論 家庭裁判所からみた弁護士付添人との連携と協働 ─カンファレンスの在り方を中心に─
第1 はじめに
第2 裁判所における少年審判の審理
1 事件受理時の検討
2 調査進行中の調査官との連携とカンファレンス
3 審判運営と処遇選択
第3 裁判所が期待する付添人活動の視点
第4 非行事実の審理における連携(主に否認事件)
1 早期の記録閲覧と主張立証方針の検討
2 非行事実の争点整理等のための早期カンファレンス
3 まとめと具体例
第5 要保護性の審理における連携(主に自白事件)
1 少年に対する働きかけや環境調整活動
2 審理の過程を踏まえた随時の主張や活動報告
3 付添人中間カンファレンス
4 まとめと具体例
第6 おわりに
判例索引
事項索引